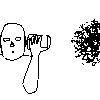HR 第3話『息子にラブレターを』執筆:ROU KODAMA
SCENE:030

食事が終わり、皆が出ていった後、俺たちはあらためて婦人と向かい合った。ベトナム人の1人が入れてくれた緑茶。婦人は湯呑みに手を伸ばし、上品な手つきで、口元に運ぶ。
「ごめんなさいね。失礼な態度で」
そう言いつつ、夫人の顔には穏やかな笑みが浮かんでいる。まるで何かを懐かしむように目を細め、ゆっくりと茶を飲んだ。
「彼は、いつから?」
室長がやんわりと聞く。ここに初めて来てまだ数時間なのに、婦人とは長年の茶飲み友達のように見える。なんとなく邪魔してはいけないような気がして、俺は視線を落とし、黙る。
「そうね、9年と3ヶ月になります」
即答する婦人に、思わず目を上げた。室長もまた、湯呑みに伸ばしかけた手を止め、婦人を見つめる。
「ずいぶん具体的ですね。覚えてるんですか?」
室長の言葉に、婦人の笑みに悲しげな影が差した。
「ええ、忘れもしません。あの子が来てくれたのは、息子が亡くなってすぐのことだったから」
衝撃を受けた。
息子が亡くなった。
こんなにも明るくて穏やかな婦人から出た言葉とは思えなかった。
「そうでしたか……息子さんが」
室長の言葉に驚きの色はなかった。それまで通りの口調で言い、ズズッと音を立てて茶を飲む。それに促されるように婦人も湯呑みを口に運び、呼吸とほぼ変わらない小さな溜息をつくと、話を続けた。
「交通事故でした。大学を卒業して、一度は別の企業に就職したんですが、やっとうちに戻ってきてくれて、3ヶ月くらい経った頃。だいぶ仕事も覚えてこれからというところだったんだけど」
「そうでしたか……」
「あの日……息子が亡くなった日、病院に一番に飛んで来てくれたのがタカちゃんでした。あの子は息子の小学校からの親友でね。うちにもよく遊びに来てました。夜の待合で呆然としてる私と主人に駆け寄って、泣きながら頭を下げるんですよ」
「……そりゃまた、どうして」
「俺のせいだ、あいつが死んだのは俺のせいだ、なんて言うもんだから、私たちもわけが分からなくてね。タカちゃんも泣きじゃくってて、何を言っているかわからなくて」
婦人はそう言って、悲しげな顔でふふ、と笑い声を漏らす。
「何とか落ち着かせて話を聞いてみたら……どうやら事故の前日、息子と会ってたらしいんです。タカちゃんが息子を誘ってね。タカちゃん、仕事のことでいろいろ悩んでたみたいで、息子に相談したかったんだって。うちの子、あんまりお酒は得意じゃないんだけど、タカちゃんが塞ぎ込んでいるもんだから、つきあうつもりだったんでしょう、珍しくたくさん飲んだらしいの」
「なるほど」
「タカちゃんも、いろいろ溜め込んでいたんでしょうね。ずいぶん遅くまで話し込んだみたい。それで、別れて、次の日の事故でしょう。責任を感じていたみたいなのね」
「そうだったんですか」
「でも、そんなわけないでしょう? だいたい、その事故はね、トラックの居眠り運転が原因なのよ。大きなトラックが、息子の走ってる反対車線に急に飛び出してきて、正面衝突した。だから、当たり前だけど、タカちゃんのせいじゃないの」
婦人はそう言って何度か頷いた。まるで、ここにいない高本に向かってそうするように。
「何度もそう言ったわ。あなたのせいなんかじゃない。それどころか、きっと息子は、あなたがいてくれたおかげでとても救われたはずだって。……うちの子、繊細な子でね。小さな頃からなかなか友達もできなくて。中学時代には、ちょっとしたイジメも……。それを救ってくれたのがタカちゃんなのよ。タカちゃんと仲良くなってからは、息子も随分明るくなって……だから、そんな風に言わないでって、あなたのせいなんかじゃないって」
沈黙が降りる。遠くから、機械が動く音だろうか、微かな振動音が聞こえる。
室長は再び茶に手を伸ばし、ゆっくりとした動作で飲んでから、噛みしめるように言った。
「でも、彼は納得しなかった」
「その通り」
婦人は視線を落としたまま、微笑む。
「あの子、次の日には会社を辞めてきちゃった。それで何て言ったと思う? 俺を中澤工業に入れてくれ。俺があいつの分まで働くからって。……もちろん、止めたわよ。バカなことを言ってるんじゃないって、主人も怒りました。タカちゃん、すごくいい企業に務めてたんですよ。聞けば誰でも知ってるような、大きな企業。いいから今すぐ戻って頭を下げろって、辞表を出したけど、ナシにしてくれって頼んでこいって、説得しましたよ。……でも、彼はうんと言わなかった。そこで、あの人は正直に話すことにした」
「正直に?」
「ええ。実はあの頃、うちの会社は大変だったんです。大口の取引先が倒産しちゃって、それで、売上がガクッと減ってしまっていて。息子はわかった上で入社してくれたんだけど。でも、タカちゃんまで巻き込むわけにはいかないでしょう? だから、ダメよって。タカちゃんをそんな泥舟に乗せるわけにはいかないって、もう全部話したわ。でも……」
高本の性格的に、むしろその告白は彼の決心を固める結果になったのだろう。出会って数時間だが、彼を見ていればその時の様子が想像できた。
「何度言ってもタカちゃんは毎日やって来たわ。それで、勝手に工場に行って仕事を覚えるようになったの。当時いた社員さんに、しつこいくらい機械のことを聞いていた。彼、そういう経験は全くなかったから、苦労していたわね。でも、気持ちという意味では、誰よりも強かった。体を壊すからやめなさいって言っても、毎日毎日夜中まで勉強して、部品の試作をして……そんなことをされたら、私たちものんびりしてられないじゃない? 社員たちもなんというか、彼の一生懸命さにほだされちゃってね。皆して頑張るようになってね」
婦人はそう言って、笑った。「彼が、皆を変えちゃったんだ」と室長も笑う。
「そうなの。で、そういう頑張りが功を奏したのかしら、あるメーカーさんが突然やって来て、部品を作ってくれないかって言うわけ。でも、当時の私たちにそれを作る技術はなかったの。求められたのはずっとずっと小さな規格だったから。だからうちの主人は断ろうとした。だって、できないんだもの。作れないものの注文を受けるわけにはいかないわよね。……でも、タカちゃんがね、やろうって。きっとできる、俺がやってみせるって。……それで何ヶ月か後、本当に実現してしまった。それも、今までウチで使っていた機械を改造して、作っちゃったのよ」
「それはすごい」
「それで会社は持ち直した。いろんなところから注文をいただくようになって。そうやってタカちゃんは、自分の努力で、ウチになくてはならない人材に成長していったの」
「なるほど」
「それに……」
婦人はそう言ったが、続きを言うのを躊躇するように視線を落とした。
「それに?」
室長が促す。
「……伝わるかはわからないのだけどね」
「ええ」
「会社にとってだけじゃなくて、そう……あの子はもう、私たち夫婦にとってもなくてはならない子になっていた。……息子が死んで、ぽっかりと空いてしまった私たちの心の穴に、あの子は入ってきた。息子のことを悲しむ間もなく、あの子は私たちの前に現れて、どれだけ出て行けと言っても出ていかなかった。……それからもう9年よ。あの子がどれだけ私と主人の心を助けてくれたか。もうあの子は、私と主人にとって、息子同然の存在なんです」
「……そうですか」
「だからこそ、今回、あの子のお母様のことを聞いた時、ハッとした。私たちがタカちゃんの重荷になってどうするんだって。あの子を息子同様に想っている私たちがそんなじゃ、本末転倒じゃないかって。だって、多分あの子は、お母様と、私たちを天秤にかけなきゃいけないような状況にあるのよ。そんなの、どれだけ苦しいかわかりゃしない」
そして婦人は、姿勢を正すようにして、俺達を見た。
「宇田川さん、村本さん」
「は……」
「あの子、私たちの前ではああだけど、本当は今すぐにお母さんの所に帰りたいと思ってるはずなんです。誰よりも優しい子だから。でも同時に、私たちに対する責任感から、動けずにいる。新しい人が入ってきたら、口ではどういうかわからないけれど、あの子は開放されるはずなんです。だから……ぜひお願いします。何とか、新しい人を見つけてください」