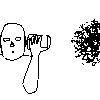「好きを仕事に」。
若い人をリクルーティングするにおいて、おそらく永遠に使われる誘い文句です。
これから就職する若者や、こんなはずじゃなかった…と日々思っている若者にとって、現実に対抗しうる数少ないイメージのひとつがこのヴィジョンに違いありません。
かくいうわたくしも若かったときに一定期間それを追いかけて、結果的にうまくいかなかった経験があります。
もちろんある分野で夢を追い、自身がスターになる人が一握り存在することは事実であり、それはリスクを顧みずになにかに賭けた決断があったからにほかなりませんが、大多数はそうではありません。
なぜ、「好きを仕事に」の発想がうまくいかない、または成功例が限られるのでしょうか。
端的にいえば、仕事の場で「好きな何か」は仕事の構成要素のごく一部でしかないからです。
クルマが好きな人がそれに関わる仕事に就くとき、販売業界にいるとしたらクルマは「商品」であり、ドライバーの仕事ならば「道具」であり、製造の仕事であれば「製品」という一要素にすぎません。
仕事においては、クルマと自分の間に入ってくる人間やお金や時間の方が、取り扱う「対象」としてのクルマよりも存在としての比重が大きいのはどんな分野の仕事でも共通しています。
では、独立して、自分でなにもかもコントロールすれば、すべては理想通りに動かせるのでしょうか。
いうまでもなく、そんなこともありません。
以上の背景により、社会人を長くやっている人で、若者のように「好きを仕事に」を胸に抱いている人はほとんどいないでしょう。
しかし、完全ではないにせよ、自分がスターになる以外にそれを実現に近づける方法として、仮説をひとつ申しあげたいと思います。
それは、会社などの組織に属し、組織のメリットを享受しつくすことです。
個人では扱えない規模のお金を出してもらい、苦手な仕事は他人にまかせて、会社の看板で物事を有利に進めることです。
独立していたら日々の稼ぎに消耗しなくてはいけませんが、会社員ならば要求しなくても収入があります。社会保険すら負担してくれます。
その結果、「好きでないことが仕事にない」という境地に達することができれば、それはもう、「好きを仕事に」のようなものといえるのでないでしょうか。
ただ、そこまでいったら、自分が会社や仕事に愛されていると思いこんでしまいそうですけどね……。