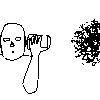「ちなみに、茂木さん以外の社員さんは?」
保科が言うと、茂木は悲しげに視線を落とした。
「辞めましたよ。店をリニューアルオープンしてから、少しずつ」
リニューアルオープンというのは、さっき保科が店で話していた移転のことだろうか。下北から新橋へ。二倍以上の広さの物件に引っ越したんだと言っていた。おそらくそれでオペレーションが変わったのだろう。それに不満を持った社員たちが辞めていった。
そういう話は、小中規模のクライアントを多く抱える営業三部や二部の人間からよく聞いていた。特に飲食店というのは、立地や客層のちょっとした変化で売上が大きく変わる。儲かっていたからと言って、そのビジネスモデルがどこでも通用するかと言えばそうではない。同じ地区内でも、通りを一本移動しただけでガクリと売上が落ちた、という話もあるくらいだ。
「大きな物件に移動したことで、オペレーションが大変になったんだ。それでしんどくなって辞めていった。そうでしょ?」
思わず言った。俺だって天下のAA、それもエリート揃いである「営業一部」の人間だ。まだ3年目の若手には違いないが、大手企業をいくつも担当してきたプライドはある。
しかし保科は「はあ?」という顔をした。
「社員たちが辞めたのは、店が移転したせいじゃねえよ」
「え?」
「メニュー刷新がキッカケだ。そうでしょ? 茂木さん」
保科がそう言うと、茂木は深く頷いた。
「そうです。その通りです」
「移転当初は、皆あんなにやる気だったのに?」
「え……ええ、そうです。移転に伴ってはバイトが数名辞めた程度で、社員は全員残ってました。状況が変わったのはメニューが変わった後です」
茂木が少し戸惑ったように言う。
「ちょっと保科さん、なんでそんなことまで知ってるんですか」
だが保科は俺の言葉を完全に無視し、「具体的には、何が変わったんです?」と茂木を促す。
「そうですね……それまでとは違って、効率とスピードが重視されて、そして何より、社長がいなくても作れるような簡単なレシピになりました。確かに回転率は上がったんです。客単価も200〜300円くらい下げたんで、新規の客もかなり増えましたし。でも、反対にスタッフのモチベーションはどんどん下がるばかりで……それで気づいたら一人、また一人と辞めていって」
「社長はそのことを知ってたわけでしょ。つまり、社員たちがどんどん辞めていってること。彼はその間、何してたんです?」
茂木の顔が暗くなる。
「店長……いや、すみません。以前は社長が店長をやってましたからそう呼んでたんです。……社長はその頃にはもう、社長業っていうんですか、そういうのに夢中になってて、現場にはほとんど顔を出さなくなってました。何とかコンサルタントとか、横文字の肩書の人たちとつきあうようになって、データとか生産性とか、そういう話ばかりするように……。そもそもメニュー刷新の件も、社員には何の相談もなく社長が決めたんです。多分、そういう外の人たちの入れ知恵だと思うんですけど。とにかく、なんというか、社長は変わってしまったんです。辞めていった社員のことも、あいつらは新しいシステムに対応できない古いタイプの人間だったんだ、って言って」
「なるほど……でも、茂木さんは残った。なぜです?」
「別に……俺しかいなかった、っていうだけのことです。正直、逃げ遅れたって感じですよね。気付いた時には社員は自分しか残っていなくて、だからバイトたちのシフトを増やすんですけど、店を任せられるほどモチベーションのあるバイトなんてなかなか見つからないじゃないですか。……いや、下北時代は自分含めてそういうバイトもいたんですけど……今はもう、1日3時間だけならとか、土日は無理とか、当日ギリギリになっての欠勤とか……そういうのが当たり前で。だから、結局、俺が店に立つしかないんです。別に残りたくて残ってたわけじゃありません」
「……」
「……」
俺も保科も何も言えなかった。茂木はこういう話を、もしかしたら初めて誰かにしたのかもしれない。だが、吐き出してスッキリした、という感じには見えなかった。どちらかと言えば、話す前より苦しそうですらある。その顔は、まるで先ほど店で見た社長のようだ。そんな人に、どんな言葉をかけられる。
沈黙を破ったのは、茂木だった。
「さっきも言いましたけど、社長の作るバーガーは本当にうまかったんです。バーガーの神様なんじゃないかって、社員たちの間ではよく言い合ってました。でももう、社長はあの頃の社長じゃない。バーガーの神様は、もうあの力をなくしちまったんでしょう」
保科は目を細めてそれを聞いていた。そしてちらりと壁掛け時計を確認し、言った。
「よし、茂木さん。確かめに行こう」
「……」
茂木は黙って保科を見返した。数秒間、二人は見つめ合った。やがて茂木がふっと笑みを浮かべ、頷いた。
「そうですね。そうしましょう」
いや、ちょっと待て。一体何の話をしてるんだ。
状況についていけず二人の顔を交互に見つめる俺に、保科がおかしなことを言った。
「よし、今すぐ店に戻るぞ」
「……は? なんでですか」
店というのは恐らく、ほんの30分ほど前までいたあの店、クーティーズバーガーのことだろう。だが、なぜ? 今からあそこに行って何をしようというのか。
呆気にとられていると、なぜか嬉しそうな顔をした保科が俺を見た。
「よし営業マン、速攻ダッシュして社長を引き留めとけ」
「は?」
「早くしないと社長、どっか行っちゃうかもしれないじゃん」
「い、いや……ちょっと待ってくださいよ、さっきから何を言ってるんです。どうして社長をーー」
思わず言い返す俺に、保科はいたずらっぽい笑みを浮かべた。
「だから、神様のつくる”幸せ”を、食いに行こうって言ってんだよ」
(SCENE:017につづく)※次回更新3/9

児玉 達郎|Tatsuro Kodama
ROU KODAMAこと児玉達郎。愛知県出身。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。デザイナーはデザイン専門、ライターはライティング専門、という「分業制」が当たり前の広告業界の中、取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。2017年フリーランス『Rou’s』としての活動を開始(サイト)。企業サイトデザイン、採用コンサルティング、飲食店メニューデザイン、Webエントリ執筆などに節操なく首を突っ込み、「パンチのきいた新人」(安田佳生さん談)としてBFIにも参画。以降は事業ネーミングやブランディング、オウンドメディア構築などにも積極的に関わるように。酒好き、音楽好き、極真空手茶帯。サイケデリックトランスDJ KOTONOHA、インディーズ小説家 児玉郎/ROU KODAMAとしても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート)。
お仕事のご相談、小説に関するご質問、ただちょっと話してみたい、という方は著者ページのフォームよりご連絡ください。