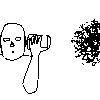HR 第4話『正しいこと、の連鎖』執筆:ROU KODAMA
この小説について
広告業界のHR畑(求人事業)で勤務する若き営業マン村本。自分を「やり手」と信じて疑わない彼の葛藤と成長を描く連載小説です。突然言い渡される異動辞令、その行き先「HR特別室」で彼を迎えたのは、個性的過ぎるメンバーたちだった。彼はここで一体何に気付き、何を学ぶのか……。これまでの投稿はコチラをご覧ください。
SCENE:040

正木、柳原と共に社長室を後にした俺たちは再度「ジャングル」にまで戻ってくると、複数あるらしい会議スペースの一つに通された。
遊びゴコロ満載の外観と違い、部屋の中は意外にもシンプルなつくりだった。白い壁に落ち着いた雰囲気の木製テーブル、黒いチェア。
「いろいろな内装のスペースを用意してあるんですよ。TPOに合わせて選択できるように」
柳原が言った。その表情、そして口調から固さが消えている。槙原社長から離れてホッとしているのかもしれない。それにしても、この男がクリエイター然とした服装なのも、BANDと高木生命との間で交わされた戦略的な理由によるものなのだろうか。確かにこのジャングルの案内役が、槇原のような古めかしいスーツを着ていたら変だ。
「さ、じゃあさっそく始めましょう。一応僕は同席しますけど、基本的には正木に話を聞いてもらえば」
俺と高橋が並んで座り、向かい側に正木、そして柳原は、自分は部外者だから話しかけるなと言わんばかりに、テーブルの隅の席に腰を下ろす。
「じゃ、あらためてよろしくお願いします」
高橋が言い、高そうなレザーカバーのかかったノートを開く。正木は笑顔のまま「はい!」とまた大きな声で答えた。柳原と違い、この男は社長室を出ても変わらない。体育会系と言うか言動が大袈裟というか、不自然といえば不自然だが、AAにもこういうタイプはいる。
「それでは、取材を始めさせてもらいます」
俺たち求人広告屋は、どんな仕事をするのか、どんな労働環境なのかを、広告を通じて読者に伝えなければならない。だからこうして現場の人間に話を聞き、その詳細情報を得る。いわゆる「取材」である。営業活動ではない後工程。見方によっては「1円にもならない時間」なので、この工程を嫌う営業マンも少なくない。かく言う俺も、その一人だった。取材に時間をかけるくらいなら、オフィスでリスト片手にテレアポしている方がずっと生産的だと思っている。
だが、いや、だからこそ、俺は高橋がどんな取材をするのか気になった。先日の保科しかり、室長しかり、HR特別室の人間は「普通」じゃない。
「入社1年目ということですけど、BAND JAPANに入ったのはいつですか?」
高橋が聞くと、正木は「はい!」とまた大きな声を出す。
「入社したのは、昨年の11月です。ですから今、だいたい半年ほどになります」
「なるほど。現在の仕事内容は?」
「営業として、PO製品の拡販を行っています」
「それは、どんなお客様にどんな切り口で営業するのですか?」
「はい、家電量販店やスーパーのイベント担当者さんに、PO製品の取り扱いや売り場の拡大を営業します。それから、ECサイトの人や広告代理店の方とプロモーション戦略についての打ち合わせをしたりすることもあります」
「なるほど」
PO(ピーオー)はBAND社の運営するモバイルバッテリーを中心としたPCアクセサリー機器のブランドだ。最近ではコードレスイヤホンや高速充電器なども発売し、やはりクリエイター層を中心に人気を得ている。大手ECプラットフォームや公式オンラインショップでの販売のイメージが強いが、確かに言われてみれば、最近では家電量販店の売り場でPO製品を見ることもある。
「失礼ですが、年収はどれくらいでしょう」
「はい、650万円ほどもらっています」
「完全歩合、というわけではないのでしょう?」
「そうですね。最低保証額として25万円が設定されています。あとは歩合です」
……ということは、賞与を無視するとすれば、正木は25万円に加え、月30万円近くも歩合給をもらっていることになる。入社1年目で、月収50万円以上? かなりの数字だ。
「すごいですね。入社1年目でそれほどの結果を出せるなんて」
俺と同じ感想を持ったのだろう、高橋が言うと、正木はさらに笑顔を深くし、いえいえ、と手を振る。
「私なんてまだまだです。先輩の中には、年収1000万円を超えている人がたくさんいらっしゃいますから」
マジかよ、と心の中で思う。いくら今をときめくブランド企業だとしても、不動産屋や保険屋でもあるまいし、イチ営業で1000万円がゴロゴロって……
と考えたところで、何かが引っかかった。
隣を見ると、高橋も口元に手をやって何かを考えていた。そしてゆっくりと正木を見据えると、言った。
「BAND JAPANの営業が扱っているのは、PO製品だけですか?」
呟きのような高橋の質問に、ごくり、と正木が唾を飲むのがわかった。
「そうです」
「現状では、ということですか」
「あの……それは……」
「新規事業と関係するから、言えない?」
新規事業? そういえば高橋は先程、BAND JAPANの新規事業は「金融」だと言っていた。それと関係があるのだろうか。
いずれにせよ、正木の反応はわかりやすかった。社長室で会った時から今まで、ずっと保っていたその過剰なほどの明るさが崩れかけている。笑顔がこわばり、笑っているのに泣いているような奇妙な表情になっている。
「高橋さん、それ以上はちょっと」
ずっと黙っていた柳原が、上ずった声で割り込んだ。柳原の顔も青くなっている。
……一体何なのだ、この会社は。二人は一体何に怯え、何を隠しているのか。
だが高橋は「わかりました」とあっさり言った。
「話を変えます。正木さんは入社1年目ということですが、この仕事にやりがいは感じてらっしゃいますか?」
高橋の質問に、正木は安定を取り戻した。自分の表情を確かめるようにグッと笑顔を深くし、「はい!」と大きな返事を寄越す。
「さっき槇原社長も仰っていたように、この会社に入ってずいぶん成長できたと思っています。いまは毎日張り合いがあって、すごく楽しいんですよ」
「楽しい。どんなときに楽しさを感じますか?」
「そうですね、営業なので、やはり契約いただけたときですかね。それに、それを上司や先輩に報告すると、褒めてもらえるんです。やっぱりそれが嬉しいかなあ」
正木はそう言って、自分ではははと笑った。別の場所からも笑い声が聞こえたので見ると、さっきまで青い顔をしていた柳原も、不自然なほどの声で笑っているのだった。
その後高橋は、労働条件や1日の過ごし方などを淡々と聞いていった。正木はやはり笑顔のまま、その一つ一つに明るく、だがどこか曖昧で捉えどころのない返答を寄越す。正味十五分ほどだろうか、「ありがとうございます」と高橋が言い、あっさりと席を立った。
え? もう終わり?
拍子抜けした気分だった。保科や室長のような、明らかに常識とは違う方法で情報を得るようなことはなく、マニュアル通りの質問を重ね、その答えを特に深掘りすることもない。つまり高橋の「取材」は、その時間を後工程、つまり「金を生み出さない無駄な時間」と考える、俺たちのような営業マンのそれと大差なかったのだ。
柳原に先導されてジャングルを抜け、俺達はBAND JAPANを後にした。