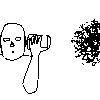HR 最終話「エピローグ」
駅から徒歩数分の巨大なオフィスビル。BAND JAPANのあった六本木のビルに勝るとも劣らない大きなエレベーターで上階に向かい、一週間ぶりに営業一部のオフィスに向かう。
その立派なエントランス、広い廊下、今風の設えを前に、思わず苦笑いが浮かんだ。雑多な新橋、飲み屋街ど真ん中の雑居ビルにあったHR特別室とはまるで別世界だ。もちろんここには、オフィスのど真ん中に真っ赤なソファが置かれていることもなければ、そこでぐうぐうイビキをかく室長の姿もない。
一週間ぶりに戻ってきた“職場”だ。
さすが営業一部というべきか、始業までまだ1時間近くあるのに既に大勢の社員が出社してきていた。だが、俺はすぐに、違和感を覚えた。
多いどころじゃない。ほとんどの席に社員が座っている。それに、普段なら黙々とPCに向き合って作業していることが多い彼らが、なぜか一様に電話で何かを話している。話し終えて受話器を置いたと思えば、すぐに新たな番号をプッシュする。
――テレアポしてるのか?
テレアポというのは、新規顧客獲得のための営業電話のことだ。社名と連絡先の書かれたリストに沿って手当たり次第電話をかけ、「求人のご用命はありませんか」と営業する。
当たり前だが、そこで話が進むことは稀だ。10件に1件興味を持つ会社があればいい方で、100件以上かけて成果ゼロということも珍しくない。求人のニーズがなければどれだけ営業しても意味がないし、そもそもどこの誰とも知らない人間からの電話は煙たがられる。
客単価が低く、日常的にクライアントが入れ替わり続ける営業三部のようなチームでは、頻繁にこういうテレアポの時間を設けていると聞いた。だが、クライアント数が少なく一社あたりの単価が大きい営業一部では、これまでほとんどテレアポをしてこなかった。現Sから紹介案件を取ろうというキャンペーンが一度二度、あった程度だ。
営業一部らしからぬ風景を不審に思いつつ自分の席まで行くと、隣であの島田までもがまじめくさった顔で電話をかけていた。いつもの間延びした大声ではなく、なんとなく淡々とした、疲れたような口調。そういえばこいつ、テレアポが大の苦手だと言っていたっけ。そりゃそうだ、と思う。こいつのように一社一社に全力を尽くし、結果紹介をもらってクライアントを広げていくタイプの営業は、こんな無差別爆撃のような営業は合わないのだろう。
「はあ……そうですよね、はい、失礼しました」
ため息混じりに受話器を置いたタイミングを見計らい、声をかけた。
「おい、島田」
それで俺がいることに初めて気づいたらしい。島田は一瞬眠たそうな表情で俺を見上げ、そしてすぐに破顔した。
「あ、村本くんじゃない! 久しぶり〜」
いつもの呑気な顔に戻って言う島田にどこかでホッとしつつ、声を落として言う。
「これ……何やってんだよ、皆」
「何って、テレアポだよテレアポ」
「いや、それは見りゃわかるけどな。なんでウチでテレアポなんてやってんだ。しかもまだ始業前だろうが」
「そうなんだよねえ」
島田はまたため息をつき、そして、周囲の目を避けるように身体を縮ませる。そして手元に手を添え、言った。
「こないだ電話で言ったでしょ? 先週ビッグSが立て続けに落ちたって」
ああ、と思う。確かにそういう話を聞いた。
「それで先週の金曜、マネージャー以下リーダー全員が集まって緊急会議さ。それで今日から、全体でテレアポタイムを設けるってことになって。落ちたSの代わりに新しい取引先を見つけようってことだね」
「そうだったのか」
「それに、なんかアポ数を増やせっていうんだよね。1日最低3件回れとか、1件の商談は最長1時間までとか、そんな話もチラホラ出てきててさ。効率を上げろ、生産性をあげろって、もうすごい鼻息だよ」
「……」
確かに、理屈は間違っていない。顧客が減ったなら、それを増やす努力をするのは当たり前だ。
だが、なにか強烈な違和感がある。その違和感は、エリート部署の営業一部がテレアポをする、ということに対するものではないように思えた。
「それ……なんかおかしくねえか」
ボソリと言う。
「うん、僕もそう思うんだけど、でもーー」
「おい! 何サボってんだ」
どこからかそんな声が聞こえ、見れば俺と島田の上司である岡田リーダーがすごい形相でこちらに近づいてくるところだった。あっという間に俺たちのそばまで来ると、島田の肩口を乱暴に掴む。
「おい! 無駄口たたいている暇があるなら電話しろよ!」
「あ……すみません」
声を荒らげられた島田は怯えた表情で言い、受話器に手を伸ばした。ドラえもんのような丸っこい手で、リストにある電話番号をプッシュする。俺がその様子を黙って見ていると、岡田は「村本、お前ちょっとこっち来い」と奥の会議室の方を顎で示した。
会議室に入るやいなや、岡田は言った。
「村本、お前は先週いなかったから知らないだろうが、今日から毎日、朝に2時間、テレアポをすることになったんだ」
「……はあ」
「お前も明日からは参加しろ。わかったな?」
それだけ言って部屋を出ていこうとする岡田を、「あの」と呼び止めた。
「……なんだ」
「テレアポって……そんなことより先に、見直すべきところがあるんじゃないですか?」
思わず言った俺に、岡田は信じられないという表情を見せた。やがてその顔は怒りの色に染まっていった。
「何言ってやがる。この状況は、お前がM社から切られたことだって原因の1つなんだぞ! お前の尻拭いを皆でしているのに、他人事みたいに言うな!」
岡田はそう言い放つと、心底憎そうに俺を睨み、乱暴に扉を開けて会議室を出ていった。
◆
一人部屋に取り残された俺は、そのままぼんやりと立ち尽くした。確かに、今の発言はまずかった。岡田が怒るのも無理はない。実際、俺のM社の一件がキッカケの一つになってしまったのだろう。
だが、俺の心は妙に静かだった。あんな風に怒鳴られ、睨まれたのに、何の動揺もない。
もちろん新規開拓というのは大切なことだ。AAを知らない相手に、自らの存在を知らせることには大きな意味がある。だが、今オフィスから電話をかけている人間のどれくらいが、「相手に価値を提供しよう」と心から考えているだろうか。自分もそうだったからよくわかる。俺たち営業マンの頭にあるのは、「契約を取って、自分の営業目標を達成すること」だけなのだ。
そんなスタンスの人間がいくら電話をかけまくったところで、根本的な解決にはならないのではないか。仮に新たな客が見つかったとして、俺たちが本気で彼らに向き合うことができなければ、きっと遅かれ早かれ、ウチとの取引は停止されてしまうだろう。
ーー本気。
自分の中から、その言葉が自然と出てきたことに、驚きを覚えた。
本気。
本気の提案。
1週間前の俺には、その言葉の示すものが何なのか、さっぱりわからなかった。
だが、今は――
頭の中に、新橋の雑居ビルに集まる、“頭のおかしい先輩たち”の顔が浮かんだ。
あの人たちなら――
あの人たちなら、どうするだろうか。
そんな風に自問していると、さっき岡田が出ていった扉が再び開いた。
入ってきたのは――1週間ぶりに見る、イタリアマフィアだった。
鬼頭部長はスタバのコーヒー片手に、どこか物憂げな表情で中に入ってきた。俺に向けて肩をすくめてみせると、「こんな騒がしい営業一部は初めて見たな」とこめかみを掻く。
「部長の指示じゃないんですか。このテレアポ施策は」
「まあ、なにか対策を打てと指示したのは俺だ。……ちょっと強く言い過ぎたのかもしれん」
そう言って鬼頭部長は扉を振り返る素振りをする。
そして俺を改めて見ると、「どうだ、久しぶりの東京は?」と聞いてくる。
「……新橋だって東京ですよ。山手線でたった2駅です」
「ほう。意外な答えだ。“意識高い系”筆頭の言葉とは思えん」
今度は俺が肩をすくめる番だった。鬼頭部長は愉快そうに目を細め、ゆっくりとコーヒーを飲んだ。
「――で? どうだった。HR特別室での“研修”は」
「……わかりません」
俺は正直に答えた。
HR特別室で過ごした1週間が、俺の何かを変化させたのは事実だろう。だが、それが何なのか、どんな意味を持つのかは、俺自身にもまだわからない。
「ただ――」
「ただ?」
俺は小さくため息をついた。それはある種、自分の敗北を認めた証拠のように思えた。自分、そう、これまでの自分の敗北。
「部長の仰っていた通り、HR特別室は甘くありませんでした」
「……そうか」
そう言ってしばらく間を置いた鬼頭部長は、何気ない風に言った。
「延長を申し出たそうだな、研修の」
誰かが話したらしい。室長か、高橋か――。
だが、事実だ。酔った勢いもあっただろうが、俺は、HR特別室に留まることを望んでいた。
「ええ」
「だが、断られた」
「でも、今はそれでよかったんだと思ってます」
俺は先ほど見たオフィスの状況、そして俺を怒鳴りつけた岡田の様子を思い出しながら、言った。
「ほう、なぜだ」
「宇田川室長に言われたんです。僕の中に起こった変化を、職場に持ち帰って皆に伝える責任があるんだって。その時はよくわからなかったんですが、ここに戻ってきた今は、なんとなくわかるような気もするんです」
「皆に伝える、か。お前は一体何を伝えると言うんだ、AAのエリート共が集まる営業一部に?」
「……それはまだわかりません。でも、そうだな、今朝から皆がやってるテレアポですが、あれはあんまり意味がないんじゃないかとか」
「言うじゃないか。だが、今はそれくらいに切羽詰った状況だとも言える。テレアポの代わりに、お前は何をするんだ?」
鬼頭部長にそう言われたとき、当たり前のように、俺の頭の中に一つの答えが浮かんだ。
「クライアントに会いに行きます。そして、理解しようと努めます」
「これまたお前らしくない答えだな。それで売上が上がるか?」
「さあ、それはわかりません」
「……」
「ただ、売上を上げるためだけの提案なんて、これからの時代、通用しない気がするんです。クライアントは僕たちに、そんな提案は求めていない」
俺の答えに、鬼頭部長がニヤリと笑った。
「そうか。わかった。……じゃあまあ、よろしくな」
俺は一礼して、鬼頭部長の前を通り過ぎた。扉に手をかけたとき、ふと思い出して振り返った。
「部長」
「ん、なんだ」
「志望動機を聞きましたよね、この間」
「ん、ああ。そうだったな。思い出したのか?」
「いえ、それは相変わらず思い出せないんですが」
そして俺は言った。
「でも、もし就職活動をやり直せるとしても、僕はまたこの業界に入る気がします」
「……そうか」
強面の鬼頭部長が嬉しそうに笑い、行け、と手で示した。
俺は頷いて扉を開け、皆が暗い顔でテレアポを続けるオフィスへと進んでいった。
(HR 終)

児玉 達郎|Tatsuro Kodama
ROU KODAMAこと児玉達郎。愛知県出身。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。デザイナーはデザイン専門、ライターはライティング専門、という「分業制」が当たり前の広告業界の中、取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。2017年フリーランス『Rou’s』としての活動を開始(サイト)。企業サイトデザイン、採用コンサルティング、飲食店メニューデザイン、Webエントリ執筆などに節操なく首を突っ込み、「パンチのきいた新人」(安田佳生さん談)としてBFIにも参画。以降は事業ネーミングやブランディング、オウンドメディア構築などにも積極的に関わるように。酒好き、音楽好き、極真空手茶帯。サイケデリックトランスDJ KOTONOHA、インディーズ小説家 児玉郎/ROU KODAMAとしても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート)。
お仕事のご相談、小説に関するご質問、ただちょっと話してみたい、という方は著者ページのフォームよりご連絡ください。