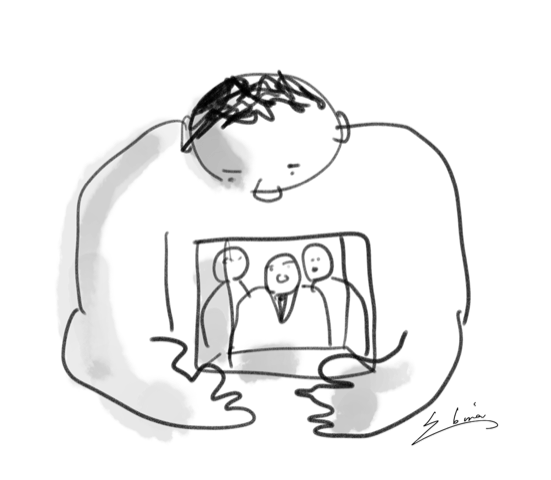このコラムについて
「担当者は売り上げや組織の変革より、社内での自分の評価を最も気にしている」「夜の世界では、配慮と遠慮の絶妙なバランスが必要」「本音でぶつかる義理と人情の営業スタイルだけでは絶対に通用しない」
設立5年にして大手企業向け研修を多数手がけるたかまり株式会社。中小企業出身者をはじめフリーランスのネットワークで構成される同社は、いかにして大手のフトコロに飛び込み、ココロをつかんでいったのか。代表の高松秀樹が、大手企業とつきあう作法を具体的なエピソードを通して伝授します。
本日のお作法/ウチの会社の良いところ?
某大手さん、「採用部門/若手チーム」のmtgに同席しました。
「御社の良いところは、どんな点ですか?」
「就活生からよく聞かれる質問」に対して、5名の若手さんたちが意見交換をしていたのですが、そこでのやりとりが印象深かったので共有を。
若手だろうが、ベテランだろうが、管理職だろうが、役員だろうが、多くの方がこう答えるようです。
「風通しが良くて、人が良いところですね」
定番回答のようで、
「確かに、ウチって『いい人が多い』ですよね」
「部署を越えて『協力しあえる文化』みたいなのもあるじゃ無いですか」
「確かにそうよね。概ね『事実』やろうし、おそらく『嘘』でもないよな」
「でも、全体会議の時には『部門ごとの縄張り意識』も出てくるよな、、」
「その件については『ウチは担当外なので』のひと言、よく聞くよね、、」
「事前連絡をSlackで送っても『既読スルー』がほとんどやしね、、」
なにやらそんな「現実」も「同居」しているようなのです。
「本音で言えばさ、、」
と、若手たちの場は盛り上がりを続けます。
「ぶっちゃけ、うちの会社のいいところって、『仕事が遅くなってても怒られない』ところじゃない?」
「多くの人が『残業』してるから、自分も帰りにくいのが逆に『絆』を生み出してるよな」
「『あいまいな報告』でも、『まあまあそんな感じか』って、わかった気になってくれる『器の大きな上司』も多いよね」
「完璧さを求められない『ユルさ』こそがウチの良いところやな」
mtg終了後のホワイトボードには、こんな言葉が残されていました。
・とりあえず誰かが助けてくれる妙な安心感
・あいまいな中でもなんとなく回る、謎の順応力
・「良いところ」とは、「説明しにくい」ものである