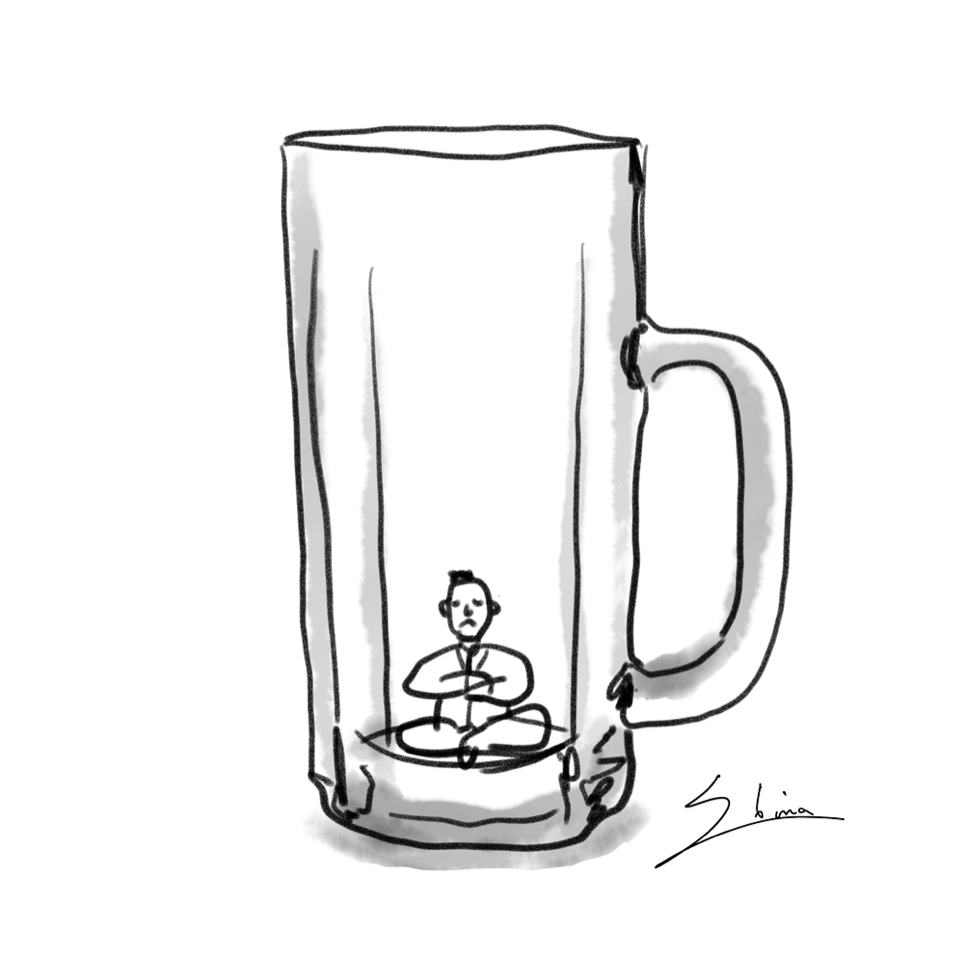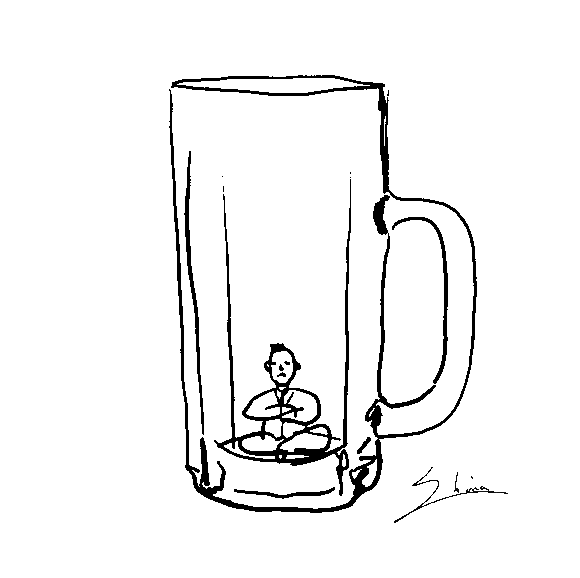このコラムについて
「担当者は売り上げや組織の変革より、社内での自分の評価を最も気にしている」「夜の世界では、配慮と遠慮の絶妙なバランスが必要」「本音でぶつかる義理と人情の営業スタイルだけでは絶対に通用しない」
設立5年にして大手企業向け研修を多数手がけるたかまり株式会社。中小企業出身者をはじめフリーランスのネットワークで構成される同社は、いかにして大手のフトコロに飛び込み、ココロをつかんでいったのか。代表の高松秀樹が、大手企業とつきあう作法を具体的なエピソードを通して伝授します。
本日のお作法/ビールが止まる瞬間
「アサヒのビールが届かない」
そんな「切実な声」が現場から聞こえ始めたのは、9月末のこと。
「アサヒグループホールディングス」が受けたサイバー攻撃によって、国内の受注・出荷・生産が一斉に停止。新商品の発売延期や飲食店での品薄も報じられ、その影響は広がりました。
(同社発祥の地である大阪の居酒屋さんにて、入店直後に「本日、ビールがありません、、」という場面に出会したタカマツです、、)
被害の原因とされるのは、「ランサムウェア」によるシステム暗号化。
デジタル技術を「業務の根幹」に据える現代企業にとって、これはもはや“全社停止”と同義です。
アサヒでは急遽、手作業で受注を続ける対応が取られたようですが、納品量は大幅に落ち込みました。。
興味深いのは、この混乱が自社内にとどまらなかった点です。ビール業界では「複数社の商品」をまとめて配送する「共同配送」が進んでおり、今回の「アサヒ倉庫の障害」が他社製品の物流にも波及。。
「効率化」の裏側に、「連鎖的な脆弱性」が潜んでいたことが明らかとなったのであります。
この構図は、他業界も同様で、
たとえば、出版大手「KADOKAWA」では2024年6月、ランサムウェア被害でシステムが停止。約25万人分の「個人情報流出」も確認されたといい、業績も大きく圧迫されました。
また、保険業界でも、「東京海上日動あんしん生命」が委託先企業を通じてランサムウェア攻撃を受け、「顧客情報漏洩」の可能性を公表した例もあります。
こうした事例はいずれも、「自社内だけでは防ぎ切れないリスク」の深刻さを教えてくれます。
改めて問われるのは、「リスク管理の設計力」です。
・BCP(事業継続計画)だけでなく、最悪時の「代替路線」「アナログ退避経路」の備え
・取引先・物流パートナーを含むサプライチェーン全体のセキュリティ強化
・定期的な侵入検査、模擬演習、システム分離・分散化
・攻撃発生時の早期検知・隔離能力と復旧訓練
特に、流動性の高い商品を扱う企業では、“停止の時間”そのものが「信頼の揺らぎ」にもつながります。
「効率化と高速運用」を追求するほど、その裏側に「止まったときの衝撃」を緩衝する仕組みを設計しておかなければならない。
アサヒの事例は、まさに現代企業にとっての「リスク管理の常識」を問い直す警鐘であり、他業界も「他山の石」とすべき教訓でしょう。
そんなことを考えている現在、ワタクシ、PCとクラウドのバックアップ更新にて「重大なエラー」を生じさせてしまい、、その「復旧作業」に勤んでいる最中なのであります、、