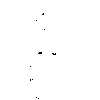HR 第2話『ギンガムチェックの神様』執筆:ROU KODAMA
SCENE:011

160センチ位か、ぶかぶかのスウェットにスキニーパンツ、汚れたVANSのスニーカー。キャップを後ろ前に被り、そこから肩まで長い黒髪が垂れている。性別不詳と言うか、一瞬女かと思うような顔立ちなのに、その視線は冷たく、妙な圧力がある。
誰だ……こいつ。
俺は頭をフル回転させる。もしこいつが客だったとしたら、一応俺はAAの社員として迎えなければならない。だが、こんな格好でオフィスを訪ねてくる客がいるだろうか。どう反応すればいいのかわからぬまま口ごもっていると、男の方が口を開いた。
「あんた誰?」
誰って……そりゃ俺のセリフだと思いながらも応えられずにいると、その小柄な男は無言で俺の横を通り抜けた。思わずその背中を追う。
男はソファでイビキをかいている宇田川部長にも特に関心を示すことなく、壁際の椅子の一つに座り、慣れた手つきでPCの電源を入れた。
……まさか、室長の言ってた「メンバー」って、あいつか?
短い間にいろいろなことが起こりすぎて、頭がついていかない。
……そうだ、俺はここから出ていくつもりだったんだ。
今更のように思い出す。そうだ、とにかくここを出て、鬼頭部長に連絡を取る。恐ろしいなどと言っている場合じゃない。研修先の準備が全く整っていないと知れば、鬼頭部長も考えを改めるに違いない。
よし。
俺は小さく深呼吸し、再び扉に向き直った。そしてドアノブに手を伸ばしたとき、扉の向こう側、つまりエレベーターホールがにわかに騒がしくなった。エレベーターを降りてきた誰かが、携帯電話で話しているらしい。甲高い女の声が外から近づいてきて、やがて派手な音を立てて扉が開いた。
「だーかーらー、忙しいって言ってんだろこのエロオヤジ!」
入ってきたのは、異様に顔の整った女だった。若くはない。40代か50代か……ひと目で高級だとわかる灰色のスーツ。タイトなスカートから伸びる足には網タイツを履き、足元は真っ赤なピンヒールだ。まるでアナウンサーのような、いや、銀座のホステスのような存在感。
「用事があるときはこっちから電話するから、それまでおとなしく待ってなさい!」
年季の入ったガラケーにそのおばさんは叫び、相手の返事を聞く間もなく携帯を畳んでしまった。
「まったく、ちょっといい顔するとこれだからなー……あれ? 何かの業者さん?」
「……あ、いや、私は今日から研修に来た者で……」
まるで芸能人のような姿に、緊張が高まる。
「研修? なにそれ」
「いや、あの、それが……」
容姿も言動も派手だが、やっと話が通じそうな相手が見つかった。俺はこれまであったことを伝えようと話しだしたのだが、質問をしておいてそのおばさんは、話し始めた俺を置き去りに部屋の奥へとさっさと入っていってしまった。やはりソファでいびきをかく宇田川室長には目もくれず、先程のキャップの男の隣の席に腰を下ろす。
「いまの電話、斉田さんでしょ」
キャップの男がPCディスプレイを見ながらおばさんに言い、おばさんが頷く。
「あ、やっぱわかった? 上場企業の社長のくせに、言うことが相変わらずケチ臭くてダメね」
……上場企業?
……の社長の、斉田?
ちょっと待て、それってもしかして、あのT物産の……?
「なんて言われたの?」
「それが、10万円払うから飲みに行こうだって」
キャップの男がぶっと吹き出す。
「いいじゃん、もらえるものはもらっとけば。高橋さんの若さも有限なんだし」
「バカ、私が客から金を取るのは仕事の時だけよ。知ってんでしょ。適当なことばっか言ってんじゃないわよ」
「へいへい。うるさいオバハンだなあ」
「なんだとこのバカ保科、いい加減にーー」
俺を完全に置き去りに話す二人を見て、怒りがわいてきた。一体どういうつもりだ。別に俺は客ではないが、研修に来たAA営業一部の社員だ。こんな舐めた扱いを受ける謂れはない。だいたい、もしあの二人ーーキャップの男が保科、派手なおばさんが高橋というらしいーーがここのメンバーだったとして、あんな社会人としての振る舞いもできない人間から何を学べというのか。
もう我慢の限界だった。俺は無言で二人に近づいた。
「あの、すいませんけど」
「……ん、何よ、ていうかあんた誰よ」
おばさんが振り返り噛み付くように言う。だから研修に来たんだって言ってるじゃねえか。ここの奴らは誰も人の話を聞いていねえのか?
「ええと、ですから、研修に来たんです」
いい加減ムカついていた俺は、とっておきの名前を出してやった。
「……鬼頭部長の命令で」
「……」
「……」
どうだ、この野郎。「HR特別室」がいったいどんな部署なのか知らないが、あの鬼頭部長の名前を出されてビビらないはずがない。何しろ鬼頭部長はAAの統括部長で、取締役だ。それにあの存在感、誰も逆らうことなどできはしない。
だが、次の瞬間、俺は耳を疑った。
「ああ、あのバカの差し金か」
きれいなおばさんーー高橋があっさりとそう言ったからだ。