SCENE:004

「え? キャンセル?」
片側に十脚以上のチェアが並んだ広い会議室。俺と向かい合って座っている女性人事は、かけていた黒ぶちメガネをゆっくりはずしながら、「そうです」と言った。
「全部……ですか?」
「そうです」
既にOKをもらっていたはずの約250万円の契約。あとは俺が作ってきたこの企画書を上司に上げてもらえば終わりのはずだった。それを突然キャンセルすると言い出したのだ。いや、厳密に言えば契約前の話なのだから、キャンセルというより「契約を見送る」ということなのだが、延期でもリスケでもなく、女性人事は明確に「キャンセル」という言葉を使った。
「ちょ、ちょっと待ってください、どうして急に」
女性人事はメガネを閉じたままのノートパソコンの上に置くと、微かに眉間にしわを寄せ、言った。
「そうですね、他の会社から、いい提案があったものですから」
殴られたような衝撃があった。他の会社?
「そんな……どこですか……どこがどんな提案を?」
このAAが他社に抜かれるなど、あっていいことではない。それも、こんなビッグクライアントを。思わず強い口調で言い返すと、女性人事は一瞬怯えたような表情を浮かべたが、やがて何かを決心したように俺の顔を見つめ、はっきりと言った。
「そこまで村本さんにお伝えする必要はないと思いますが」
「え……いや……」
違う。いつもと全く違う。一体何が起こったというのか。
思えば会議室に入ってきた時からおかしかった。この女性人事は、俺のことを気に入っているはずだった。それが単に仕事のパートナーとしてという枠を超えたものであることを、顔を合わせるたびに見せる笑顔が物語っていた。だが今日は、最初から妙に強張った表情をしていた。席につく足取りもどこか重く、企画書を取り出して説明を始めても、心ここにあらずといった雰囲気だった。いま思えば、あの時点で既に契約キャンセルの件は決まっていたのだろう。
あの時点で……そうか。
そして俺は今更のように気付いた。
……上の判断か。
総務課長か、人事部長か、大企業のイチ担当者に過ぎないこの女性人事の権限など知れている。彼女の判断がどうであれ、自分の頭越しに物事が決まってしまうこともあるのだろう。そうに違いないという気がした。本当は彼女は、こんな話をしたくはなかったのだ。
「……なるほど」
俺は独り言のように呟いた。上が決めたことなら、このテーブルで状況を覆すのは不可能だ。課長や部長と面識がないわけではないが、こちらの影響力を行使できるほどの間柄にはない。いや、そもそもキャンセルを決めたのが彼らなのだとしたら、俺がどれだけアポイントを求めても応じてくれないだろう。「他の会社がいい提案をしてきた」という先ほどの言葉も、上司からそう言えと指示されただけなのかもしれない。
実際、そういうことは当たり前にある。むしろ俺たちの方が、こういった政治的なやり方で他の代理店の契約を奪ってきた。人事担当ではなくその上役をピンポイントで狙い撃ち、現場が知らぬ間に契約を上書きする。文句が出ようが後の祭り。日本の一般的な会社組織では、上役の判断を真っ向から批判できる部下などいるはずがない。そして、上役の判断だからこそ、その部下が誰かに責められることもない。
そう考えて、俺は微かな安堵を覚えた。250万円の契約がポシャる事実は変わらないにしても、それが俺と女性人事のあずかり知らぬ所で決まったことなのだとすれば、俺への責任追及はそこまで強く行われないだろうと考えたからだ。頭越しに行われた取引をひっくり返すには、その高さに手が届く立場の人間が出ていくしかない。末端営業マンの俺の手に負える話じゃないと、言い訳が立つ。
「上の判断なんですね」
女性人事に決定権がない以上、彼女に文句を言っても無駄だ。俺にしても、今回のキャンセルを不可抗力として既成事実化してしまった方がダメージが少なくてすむ。
「じゃあ、仕方がないですね。今日はおとなしく引き下がります」
聞き分けの良さをアピールした。それで人事はホッとするはずだ。契約を破棄したのは上司なのに、それを直接伝える役割を押し付けられた。嫌な役回りが無事に終わったことに安心するだろう。
だが、彼女の顔は変わらなかった。すっと息を吸い、そして言った。
「いえ、私の判断です」
絶句する俺を見て、彼女はやっと表情を変えた。だがそれは、俺に対する後ろめたさでも申し訳なさでもなく、まるで呆れたような、俺を見下すような冷たい表情だった。
彼女は小さく溜息をついて、言った。
「実は数か月前から、人事部内で今年度の採用計画について、複数社の提案を比較検討していました。それで今回、最も真剣に弊社のことを考えてくれている一社に全面的にお任せすることにしたんです。正直に申しまして、御社からの提案にはあまり熱意を感じられませんでした。村本さんからすれば唐突に感じられる話かもしれませんが、こちらとしては何ヶ月にも渡り、御社の、いえ、あなたの対応を注視していたんですよ」
「私の対応? ……と言うことは、原因は私にあると?」
「そう取っていただいて構いません」
「そんな……御社へのフォローはどの会社よりも時間をかけて……」
女性人事が笑ったように見えた。視線を落とし、小さく首を振る。
「村本さん、私たちが求めているのは、必要な人材が採用できる提案です。ご機嫌取りやお伺いではないんです」
頭がクラクラした。
こいつは一体何を言い出すのか。そもそもあの250万円がなくなることで俺の営業成績はガタガタだ。もしかしたらあのバカ島田にすら負けるようなことになるかもしれない。
ただでさえここ最近の俺は新規顧客が得られずに苦しんでいた。だから既存顧客のフォローを手厚くして単価を上げる戦略を選んでいたのだ。しかも、今回の件を「俺の責任」だと上が認識すれば、今後の出世にも響いてしまうかもしれない。
「こ、困ります……いや、あの、もう一度チャンスをください、もう一度提案させてください」
そう言うしかなかった。だが、返事はあまりにそっけなかった。
「弊社の採用状況はいま非常に厳しい状態にあります。残念ながら、本気の提案を行うことができない会社とつきあう余裕はないんです」
(Scene:005〜006につづく)

ROU KODAMAこと児玉達郎。愛知県出身。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。デザイナーはデザイン専門、ライターはライティング専門、という「分業制」が当たり前の広告業界の中、取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。2017年フリーランス『Rou’s』としての活動を開始(サイト)。企業サイトデザイン、採用コンサルティング、飲食店メニューデザイン、Webエントリ執筆などに節操なく首を突っ込み、「パンチのきいた新人」(安田佳生さん談)としてBFIにも参画。以降は事業ネーミングやブランディング、オウンドメディア構築などにも積極的に関わるように。酒好き、音楽好き、極真空手茶帯。サイケデリックトランスDJ KOTONOHA、インディーズ小説家 児玉郎/ROU KODAMAとしても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート)。
お仕事のご相談、小説に関するご質問、ただちょっと話してみたい、という方は下記「未来の小説家にお酒をおごる」よりご連絡ください(この方式はもちろん、『安田佳生の「こだわり相談ツアー」』が元ネタです)。






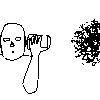











1件のコメントがあります