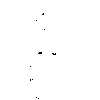SCENE:012
![]()
「ほんっとろくなことしないな、あいつ」
「な……」
「鬼頭さんって、高橋さんの後輩なんだっけ」
キャップの男が言う。こいつは確か、保科。
「後輩だなんてやめてよ、あんな勘違いバカは後輩とも思いたくないわ」
「……」
今度は俺が黙る版だった。高橋が鬼頭部長の先輩? ……いや、だからといって現役の役員にこの物言い、頭がおかしいとしか思えない。
「あ、俺、そろそろ行くわ」
呆然と立ち尽くす俺の前で、保科が荷物をまとめ始めた。そしてどう見てもビジネス用には見えないカジュアルなリュックを背負い、イヤホンを耳に入れながら扉の方に歩いて行く。
「あ、あの、ちょっと!」
なぜ声をかけたのか自分でもわからなかった。だが、このまま蚊帳の外なのには耐えられない。こいつらは多分、俺のことを知らないのだ。俺が20人以上いる同期の中で唯一の営業一部配属だったこと(島田は多分、何かの間違いで入っただけだ)、それからずっと、高い売上を保っていること。そういうことを知らないから、こんな態度に出ている。
立ち止まった保科が振り返り、言った。
「……なに?」
なに、と言われればよくわからない。だが、このまま終わるわけにはいかない。
「俺も連れてってください」
気付いた時にはそう言っていた。そうだ。さっき宇田川所長から、メンバーにアポに連れて行ってもらえと言われたのだ。それがここで俺が聞いた唯一理解できる「指示」だった。
「は? なんで?」
隠す気もないのか、はっきり眉間にしわを寄せて保科は言った。
「宇田川さん……室長にそう指示されました」
「はあ?」
その時、背後から高橋の声がした。
「いいじゃない、連れてってやんなよ。まあ、こいつの取材が参考になるとは思えないけど」
取材?
保科はこれから取材に行くというのか。
ということはこの人は、原稿を作る制作マンなのか?
そう考えると微かな納得感があった。
制作マン。つまり。求人広告のデザインやライティングを專門で請け負う職種。
AA本社にも原稿をつくる制作チームがあった。営業部とは違うフロアにあって、やりとりをするとしても電話かメールが多かったからあまり知らないが、クリエイティブ職だからというよくわからない理由で、彼らには確かにスーツ着用の義務はない。だがいくらスーツでなくていいとは言え、その格好で行くのか? いや、それ以前に、こんな社会性のない人間に取材などできるのだろうか。
「参考にならないんじゃなくて、できないの」
保科が俺越しに高橋に言い返し、「あら、それは失礼」と返ってくる。
保科はちっと舌打ちをして、俺の方を向いた。それからふと気付いたように、言った。
「あれ……あんた、営業マン?」
「え? ……ああ、そうですけど」
「そっか、じゃあ、行くか」
保科はいきなりそう言って、にやりと笑った。
なんなんだ、さっきまでは嫌がっていたくせに。
「先方、随分と怒ってるみたいだからさ」
「……は?」
「営業って、そういうの得意なんだろ。よろしく」
(SCENE:013につづく)

ROU KODAMAこと児玉達郎。愛知県出身。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。デザイナーはデザイン専門、ライターはライティング専門、という「分業制」が当たり前の広告業界の中、取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。2017年フリーランス『Rou’s』としての活動を開始(サイト)。企業サイトデザイン、採用コンサルティング、飲食店メニューデザイン、Webエントリ執筆などに節操なく首を突っ込み、「パンチのきいた新人」(安田佳生さん談)としてBFIにも参画。以降は事業ネーミングやブランディング、オウンドメディア構築などにも積極的に関わるように。酒好き、音楽好き、極真空手茶帯。サイケデリックトランスDJ KOTONOHA、インディーズ小説家 児玉郎/ROU KODAMAとしても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート)。
お仕事のご相談、小説に関するご質問、ただちょっと話してみたい、という方は下記「未来の小説家にお酒をおごる」よりご連絡ください(この方式はもちろん、『安田佳生の「こだわり相談ツアー」』が元ネタです)。