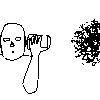HR 第2話『ギンガムチェックの神様』執筆:ROU KODAMA
この小説について
広告業界のHR畑(求人事業)で勤務する若き営業マン村本。自分を「やり手」と信じて疑わない彼の葛藤と成長を描く連載小説です。突然言い渡される異動辞令、その行き先「HR特別室」で彼を迎えたのは、個性的過ぎるメンバーたちだった。彼はここで一体何に気付き、何を学ぶのか……。これまでの投稿は
コチラをご覧ください。
SCENE:016

クーティーズバーガーの厨房にいた大きな体の男が店を出ていき、それを追うように保科が去っていった後。社長の怒りは嘘のように消え、ただ呆然とした表情でテーブルを見つめていた。
「じゃ、あと頼むわ」そう言って出ていった保科。めちゃくちゃだ。まともな大人とは思えない。だが、この店に入る前と今とでは、保科に対する印象が変わったような感じがする。どう変わったのか、そう聞かれてもよくわからない。あの小柄なキャップの男は、間違いなく頭がおかしい。おかしいが………しかし。
気づくと社長は、テーブルの上に置きっぱなしだった『美食の本懐』に手を伸ばし、静かにその表紙を開いた。黄ばんだページ、途中で千切れている赤いしおり紐。ビジネスマン、というより、やはり職人独特の節だった社長の指が、その表面を優しく撫でていく。その顔に浮かぶのは、もう感情とも呼べないような何かだ。笑っているようでもあり、泣いているようでもあり、そして何も感じていないようにも見える。
居たたまれなかった。黙って本のページをめくる社長を見ているのも、あるいは、その社長に見つめられるのも、嫌だった。だが、その理由がよくわからない。俺は正体不明の不快感に襲われていた。今すぐにここを出たい。こんな、何かが「剥き出し」になったような場所には、もういたくない。
「あの……じゃあ、また連絡しますから」
一方的に言って席を立った。
滞在時間は三十分程度だっただろう。だが、店を出た途端、長い夢から醒めたような感覚があった。
スーツを着たサラリーマン、みっしりと連なった飲食店。新橋の町は、三十分前と何も変わっていない。その「日常」に早く戻りたいと、俺は慌てて足を踏み出した。
HR特別室に戻ると、向かって左側のミーティングスペースに保科が座っていた。キャップを取り、それを左の指でクルクルと回している。途端に怒りが沸き起こった。
「ちょっと保科さん!」
だが次の言葉が出る前に、俺は思わず口をつぐんだ。保科の向かい側に、見覚えのある男が座っていたからだ。
「あ……あなたは……」
それは間違いなく、さっきの店、クーティーズバーガーで見たあの大男だった。汚れた調理服。ポマードのようなもので固められた黒髪。髭。その風貌に似合わぬおどおどした態度。
「来客中なんだ、静かにしろよ」
振り返った保科が、左手で弄んでいたキャップをかぶりつつ言う。その向かいで、大男が上目遣いに俺を見、小さく会釈する。
「……あの……先ほどはすみませんでした」
「え……あ、いえ」
状況が飲み込めない。保科はともかく、なぜこの男がここにいるのだ。いや、いま思えば確かに、保科はこの男を追って店を出たような感じだった。だが、一体何のために? そして、なぜ二人してここに来るんだ。
「あの、保科さん。どうしてこの人がここに……」
「取材してんの。つうかさ、そんなとこで突っ立ってられると気が散る。座るかどっか行くかして」
そう言われて、わけも分からず俺も腰を下ろすことになった。……いや、ちょっと待て。取材?
俺が混乱する横で、保科は向かいの男に話しかける。
「じゃ、茂木さん。あらためて聞かせてください。どうしてさっき、店を飛び出したりしたんです?」
男の名は茂木と言うらしい。まるで警察官に取り調べを受けているように、落ち着かない様子で視線を動かす。
「それは……」
茂木が口ごもる。確かにこの人はなぜ店を飛び出したのだろう。社長の驚きようからすると、あれは予定外の出来事だったに違いない。もしかしたら茂木自身も、自分がなぜ飛び出したのかわからないのかもしれない。
「茂木さん、これは採用のための取材だよ。あなたが話してくれないと、原稿なんて書きようがない」
原稿……。やはり保科は制作マンなのだ。だが、社長にあんな態度を取った以上、掲載依頼などもらえるはずがないではないか。原稿制作も、そのための取材も、無駄でしかない。
保科の言葉に、しばらく黙っていた茂木はやがて、意を決したように顔を上げた。
「もうダメだな、と思ったんです」
「ダメって?」
保科が先を促す。いつの間にか手元にノートを広げ、メモを取り始めていた。
「俺……ほぼ創業時からのメンバーなんです。下北の店ができて三ヶ月後くらいに入ったんで、もう10年以上になるんですけど」
「下北のOPEN3ヶ月後っていうと、2006年の秋頃か」
保科が即座に返す。
「そうですね。それくらいです。次の年の4月に正社員になって、そこからは一応ずっと、頑張ってきたんですけど。でも、もうダメだなって。ダメっていうか、あんな社長、もう見ていたくないっていうか」
社長の話が出て、なぜかドキリとした。ほんの10分か15分ほど前、魂が抜けたような顔で、保科の置いていった単行本を眺めていた社長の姿が思い出される。俺が店を出た後、社長はどうしただろうか。
「前の社長はどんなだったんです? 今とは違ってたわけでしょ」
「そりゃあもう」
保科の言葉に、茂木は大きく頷く。
「なんていうか、24時間ハンバーガーのことしか考えてないって感じの人でした。毎日のように新メニューを開発しては、俺たちに試食させるんです。テキトーな意見を言うと怒られてね」
「怒られる?」
思わず俺が口を挟むと、茂木は「ええ」とどこか照れたように笑う。
「うまい、とか、いい感じ、とか、そういうのじゃ納得しないんです。社長、これを食べてお前は何を考えた、少しでも幸せを感じたか、みたいな聞き方をするんですよ」
「幸せを」
「そうです。幸せは食から生まれる……ってのが社長の口癖で。……ほら、さっき保科さんが持ってきてたあの本、『美食の本懐』でしたっけ。あれの受け売りらしいんですけど。とにかくあの頃の社長は、バーガーを通じて人を幸せにするってことに全力を傾けてる感じでしたね。誰よりも早く店に来て、誰よりも遅く帰ってましたし、オーダーが溜まって大忙しなのに、ちょっとでもバーガーを残した客がいると店の外まで追っかけてって話を聞いたり」
「そりゃすごい」
保科がふっと鼻を鳴らす。
「そうやっていろんな人からいろんな意見を聞いて、どんどん新しいメニューを開発してました。その数は何百種類だと思いますよ。素材とかにもすごくこだわってて、バンズの新しい仕入先を探すためだけに2週間店を閉めたこともありました」
「なんか……バーガーづくりに取り憑かれてるって感じですね」
思わず言うと、茂木は頷く。
「ええ、まさに。……でも、俺はそんな社長が好きでした。俺だけじゃない、他の社員やバイトたちも皆そうだったと思います。社長がハンバーガーのことしか考えてないから組織体制とか待遇とか、そんなの全然整ってなかったし、給料だって安かったですよ。バンズの件で2週間店を閉じたときなんか、俺達の給料まで半分になるところだったんですから。……でも、それを不満になんて思わなかった。むしろ、社長がバーガーのことだけ考えていられるように、皆でフォローしようって言い合って」
「どうしてそんな風に思ったんですか」
保科が聞く。茂木は昔を懐かしむように天井を見上げ、ポツリと言った。
「社長の作るバーガー、本当にうまかったんですよね」
「なるほど」
保科はニヤリと笑い、深く頷いた。妙に楽しそうな様子で、ノートに何事かを書き込んでいく。
いや、何が「なるほど」なんだ。俺にはまったくピンと来なかった。
社長の作るバーガーがうまいと、なんで給料が減ってもいいと思うんだ。俺なら絶対にゴメンだ。どうして社長の道楽に社員がつきあわなきゃならないーー