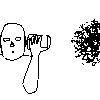HR 第3話『息子にラブレターを』執筆:ROU KODAMA
SCENE:020

HR特別室からほど近い中華料理屋で昼食をとっていると、テーブルの上に置いてあったiPhoneが震えだした。ちょうど大きな唐揚げを頬張っていた俺は、画面に表示された「本社」の文字を見て咽そうになり、思わず口を押さえる。
本社というのはもちろん、俺が所属する株式会社アドテック・アドヴァンスの本社のことだ。営業マン同士は基本的に携帯電話で連絡を取るから、固定番号からかかってくるということは、マネージャーや同僚からの連絡ではない。俺の頭には既に、鬼頭部長の顔が浮かんでいた。慌てて水を飲み、咳払いをして、受話ボタンを押す。
「は、はい。村本です」
「あ、村本くんご無沙汰〜」
体中に走っていた緊張が一気に消えていく。
「あれ? もしもし? 島田だけど」
わかっている。
島田というのは俺と同じ営業一部の営業マンだ。同期入社の20人の中で、もっとも呑気で、もっとも馴れ馴れしく、もっともウザい人間だ。上の嫌がらせか、営業一部のオフィスでは隣同士の席。これで営業成績も悪くないのだからたちが悪い。
「……なんで固定なんだよ」
「ん? なにが?」
「だから、なんで固定電話からかけてんだよ」
「ああ、僕今日、携帯電話忘れちゃって」
うふふと笑う島田に、殺意が湧く。何なんだこいつは。営業マンにとって携帯電話は必要不可欠な道具だろう。それを忘れてよくも笑えるものだ。
「なんの用だよ」
俺は言いながら周囲を見回す。遅めのランチだったこともあって店内は空いている。
「もう、そんな言い方ないじゃない。元気かなと思ってかけてるのに」
「うるせえな。どんだけ暇なんだ」
こいつと話しているとイライラしてくる。相手を怒らせる天才だ。こんなやつに発注するクライアントの気が知れない。
「で、そっちはどう? どんな研修受けてんのさ」
ふと、島田の声のトーンが真剣になった気がした。なんだ? と思いつつ「どうって……まあ、いろいろだよ」と答える。鬼頭部長からの命令でHR特別室に送り込まれて今日で3日目になるが、研修っぽいプログラムなど一度も受けていない。頭のおかしいメンバーに振り回されているだけだ。
「そっちこそどうなんだよ」
俺は話を変えた。こちらの状況をどう説明すればいいのかわからなかったからではなく、島田の声を聞いて、俺がこっちに来ている間、営業一部がどんな状況なのか気になってきたからだ。
「いや、それがさ」
「なんだよ」
「結構、苦戦してるんだよね、皆」
「……そうなのか?」
さすがに驚きを感じた。営業一部といえば、AAのエリートが集められた花形部署だ。担当するのも大企業ばかりなら、売上も全事業部中ダントツで1位。年々上がっていく売上目標も、なんなく達成し続けてきた。そんな営業一部が、苦戦している?
「でも、先週は達成してただろ、週報読んだぞ」
毎週金曜日の締め切り後、社員全体に広報される週報メールにて、営業一部がきちんと達成していることは知っていた。俺の担当顧客についても、原稿内容が毎週ほぼ変わらないという状況もあってだろうが、問題なく入稿されていた。その件で俺に連絡が入ることもなかった。だからこそ営業一部は、いつも通り危なげない達成をしたのだと思っていた。
「いや、あれ、ちょっと裏ワザ達成だよ」
「え……マジかよ」
裏ワザ達成。
様々なテクニックを駆使して、達成「したように見せる」ことをそう言う。いや、実際に受注しているわけだから達成には違いないのだが、普通なら2度3度に分けて計上する受注を1回にまとめたり、ルールの隙をついて既存顧客を新規顧客扱いにして高いマージンを得たり、キャンペーン情報をわざと伏せて割高な料金で受注したり、といった「グレー」なテクニックによって、辻褄を合わせているのだ。「お願い営業」と言って、仲のいい顧客に「今週どうしても数字が足りなくて……」と泣きついて、それほど必要のない受注をもらうことすらある。
一言で「達成」と言っても、中身はいろいろだ。二部三部ではこの裏ワザ達成が、毎週のように繰り返されているとも聞く。だが、営業一部に関しては、そういう「裏ワザ」をせずとも達成できるのが当然とされていた。だが、島田は続けて驚くべきことを言った。
「それに今日、いくつか大型案件が落ちてさ」
「え……どこだよ」
思わず聞くと、電話の向こうで島田が口元を押さえたのがわかった。今、島田のいるオフィスでは禁句なのだろう。
社名を聞いて、思わず息を呑んだ。先日俺が落としたM社レベル、いや、場合によってはもっと大きな受注をしていた大口顧客だったからだ。
「それ……今週だけか? それともAA自体が切られたのか」
「詳しいことはまだわからないけど、でも、なんかおかしいよね」
「おかしいって、なんだよ」
俺の質問に、いつも快活な島田が珍しく歯切れ悪く答える。
「うーん、なんとなく、流れが変わってきてるっていうか」
「なんだそれ、具体的に言えよ」
「今までのウチのやり方が、通用しなくなってきたのかもねえ」
話を続けたかったが、「あ、ごめん、呼ばれてるみたい」と島田は言い、一方的に電話を切った。
「なんなんだよ、全く」
言いながら、嫌な感覚を覚えた。俺のM社に続き、AAの営業一部がずっと担当してきていた大口顧客が数社、突然取引を停止した。何が起こっているのか。島田の「ウチのやり方が通用しなくなってきた」という言い方が耳に残っている。