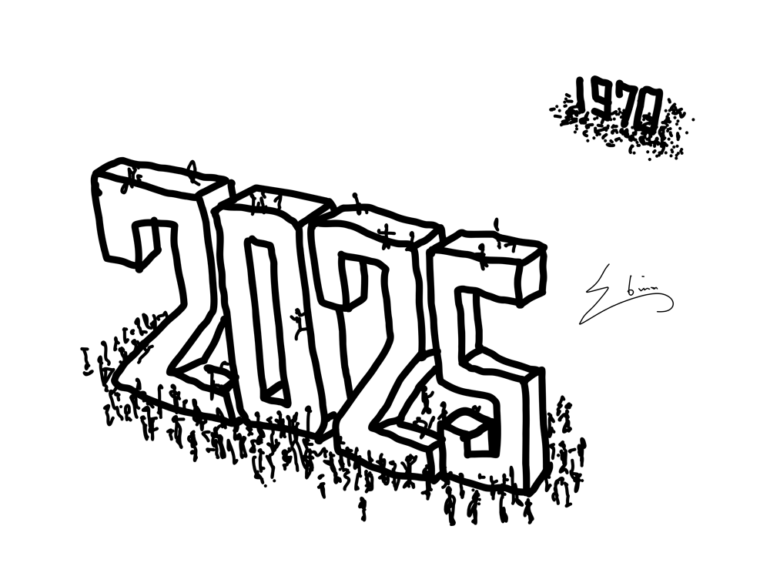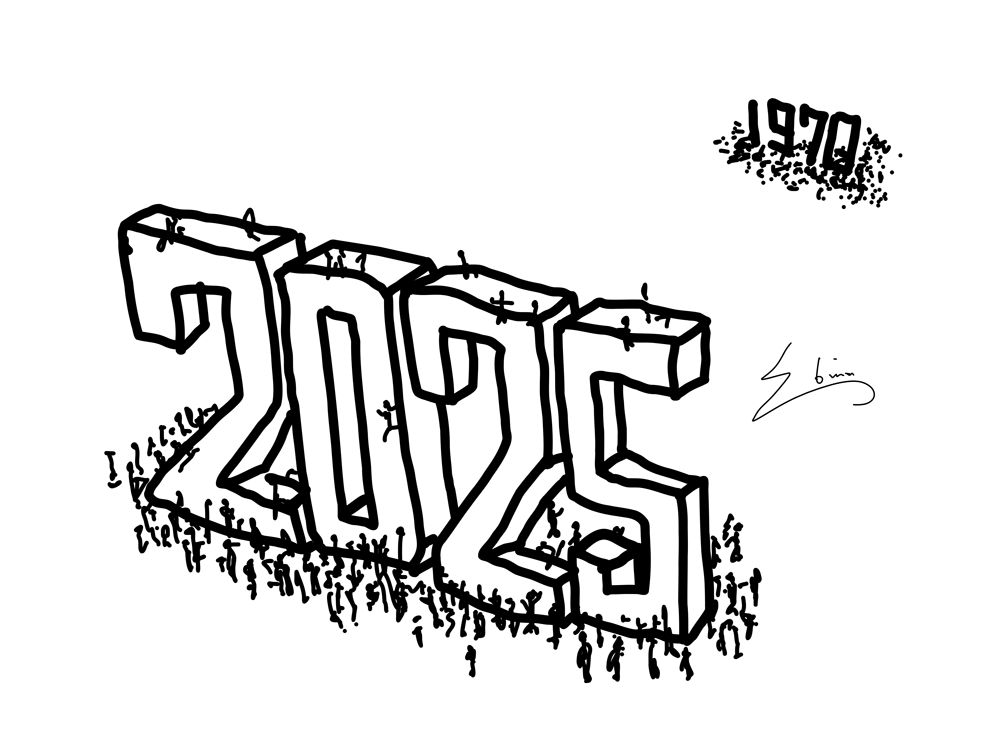このコラムについて
「担当者は売り上げや組織の変革より、社内での自分の評価を最も気にしている」「夜の世界では、配慮と遠慮の絶妙なバランスが必要」「本音でぶつかる義理と人情の営業スタイルだけでは絶対に通用しない」
設立5年にして大手企業向け研修を多数手がけるたかまり株式会社。中小企業出身者をはじめフリーランスのネットワークで構成される同社は、いかにして大手のフトコロに飛び込み、ココロをつかんでいったのか。代表の高松秀樹が、大手企業とつきあう作法を具体的なエピソードを通して伝授します。
本日のお作法/未来を語る場 〜万博開幕!〜
ついに2025年の「大阪・関西万博」が開幕しましたね。
「55年ぶり」となる日本開催の万博には、「世界中から熱い視線」が注がれていますが、開幕前からの「ネガティブな評判」に加えて、開幕直後には「通信障害、長蛇の列、、」と運営トラブルが重なり、スタートから「失敗のレッテル」を貼られている感も否めません、、(まだ現地に行ってもないので、あくまで現時点の感想です)
其れはさておき、振り返ってみますと、1970年の「昭和の大阪万博」でも、多くの大手企業がこぞって出展し、「未来への夢と技術力」を競い合いました。
たとえば当時は、「三菱グループ」が「月面基地」を模した未来都市を披露し、「松下電器(現パナソニック)」が「360度の映像体験」で来場者を驚かせ、「トヨタ」は「自動運転の原型」ともいえる都市交通システムを紹介。「電話の未来」を描いた「日本電信電話公社(現NTT)」や、「コンピュータによる社会予測」を掲げた「富士通」の展示も、当時の人々には「SFの世界」のように映ったことでしょう。
そして令和の今。再び万博に挑む企業の顔ぶれには、「時代の変化」が色濃く反映されています。
「NTT」は「バーチャル万博の中核」を担い、「パナソニック」は「共生社会」をテーマに「自然との共存」を探ります。「三菱未来館」は「脱炭素技術」を前面に押し出し、「ホンダやヤマハ」は「次世代モビリティ」を体験できる展示を行っています。
さらには、「バンダイナムコ」が「ガンダムパビリオン」で「エンタメと技術の融合」を提示するなど、「多様性の時代」にふさわしいラインナップが揃っています。
半世紀を経てもなお、万博は企業にとって「未来を語る場」であり続けています。
あのとき子どもだった来場者が、今度は親として、あるいは企業人として、「新たな万博」を見つめる。
時代は移り変わっても、企業が「未来に込める想い」は変わらないのかもしれません。
友人知人も多数関わっているようですので、暑い夏の季節に訪れてみようかと計画中なのであります!