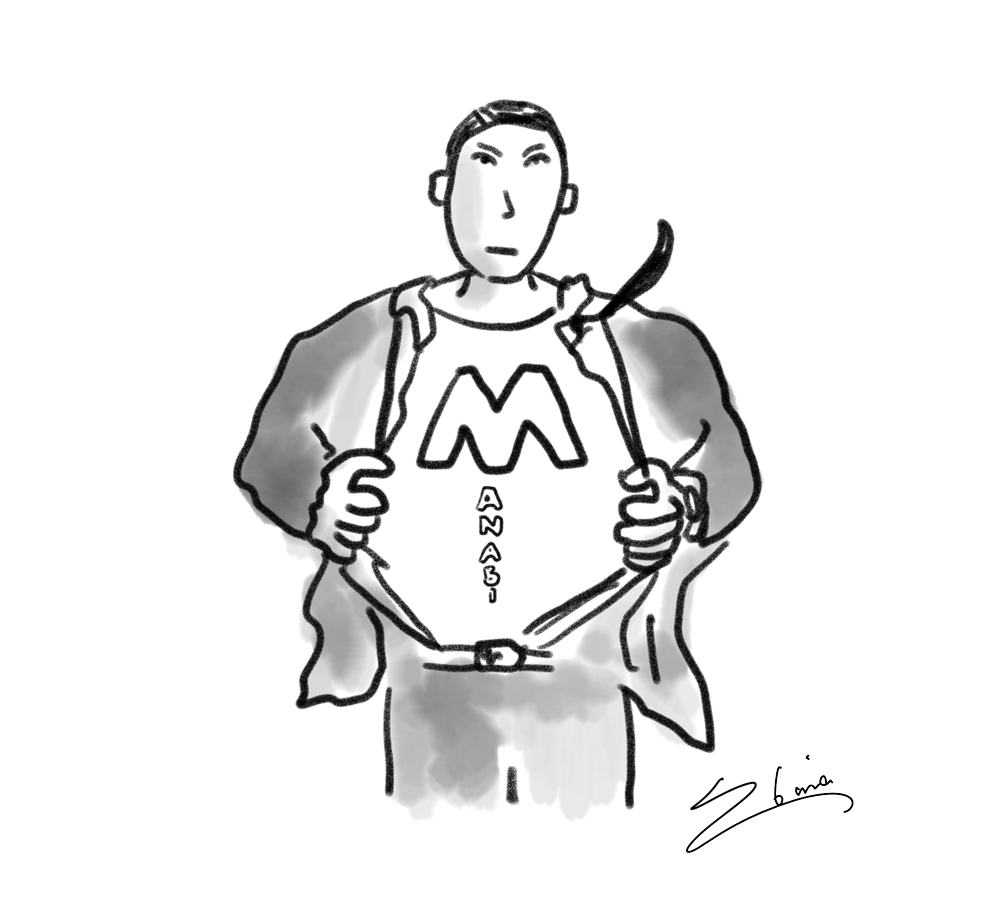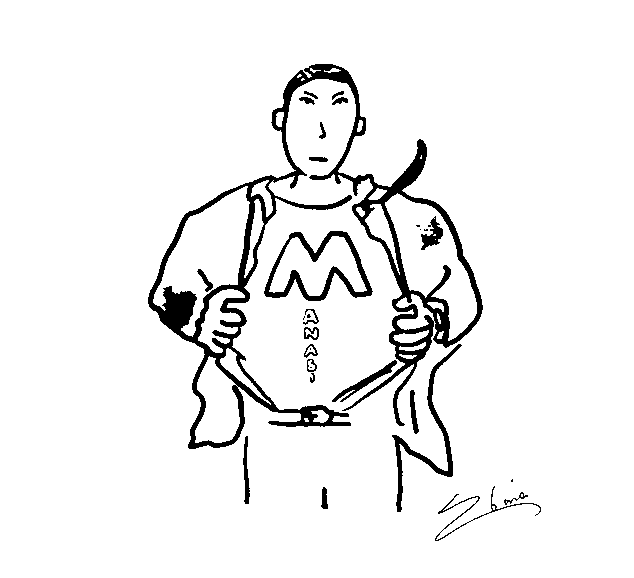このコラムについて
「担当者は売り上げや組織の変革より、社内での自分の評価を最も気にしている」「夜の世界では、配慮と遠慮の絶妙なバランスが必要」「本音でぶつかる義理と人情の営業スタイルだけでは絶対に通用しない」
設立5年にして大手企業向け研修を多数手がけるたかまり株式会社。中小企業出身者をはじめフリーランスのネットワークで構成される同社は、いかにして大手のフトコロに飛び込み、ココロをつかんでいったのか。代表の高松秀樹が、大手企業とつきあう作法を具体的なエピソードを通して伝授します。
本日のお作法/若手から教わる、学びの原点
先日、パートナー研修会社の「若手営業Mくんに同行」し、某大手さんの人事部門を訪問しましたが、彼の「気づき」の中に、「忘れがちな『本質』」が宿っていたのであります。
以下は、Mくんが「営業日報」に記していた内容です。
―――――――――――――――
応対してくださったのは、「部下育成に悩む」マネジャーさん。テーマは「若手育成」。営業としては「絶好の切り口」ですが、いきなり商材の説明に入るのではなく、まずは相手の「もやもや」を聴きにいく姿勢が大切です。
マネジャーいわく、「若手がなかなか自分で考えて動けない」「コミュニケーション力が弱く、報連相も不足気味」とのこと。
ここで私はすかさず「ちなみに、どんな場面で特にそう感じられますか?」と問いかけます。
「漠然としたお悩み」を「具体的な場面」に落とし込んでいくと、お客様自身も「『課題の輪郭』を再発見」していくのです。
さらに「理想的な若手像は、どんな姿ですか?」と質問すると、マネジャーは少し笑いながら「やっぱり、自分で課題を見つけて、『先回りして動ける存在』ですかね」と答えてくださいます。
ここで初めて、「その『理想と現状のギャップ』を埋める方法の一つとして、こうした研修があります」と商材を紹介。
単なる「商品紹介」ではなく、「課題とゴールを結ぶかけ橋」として研修を位置づけると、お客様も「納得感」を持って耳を傾けてくださいます。
営業現場で大切なのは、売り込むことではなく「お客様がまだ言語化できていない悩みを、一緒にほぐすこと」。若手育成の議論を通じて、改めて実感した一日でした。
――――――――――――――――――――
今週は、このMくんの気づきから、私自身も「学び直し」をさせてもらいました。(決して手抜きではございません、、Mくん、ありがとうございます)