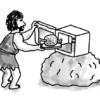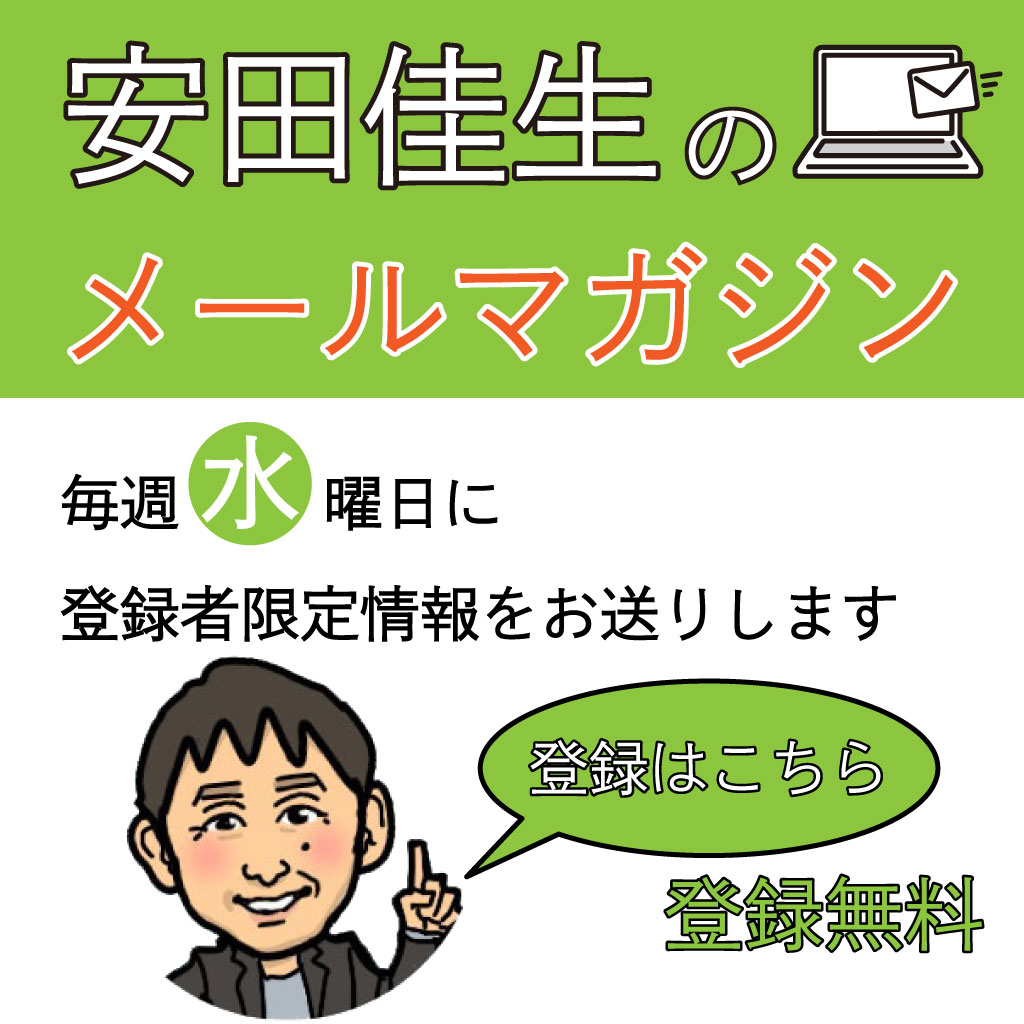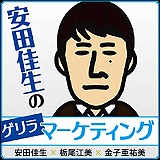この記事について
自分の絵を描いてもらう。そう聞くと肖像画しか思い浮かびませんよね。門間由佳は肖像画ではない“私の絵”を描いてくれる人。人はひとりひとり違います。違った長所があり、違った短所があり、違うテーマをもって生きています。でも人は自分のことがよく分かりません。だからせっかくの長所を活かせない。同じ失敗ばかり繰り返してしまう。いつの間にか目的からズレていってしまう。そんな時、私が立ち返る場所。私が私に向き合える時間。それが門間由佳の描く“私の絵”なのです。一体どうやってストーリーを掘り起こすのか。どのようにして絵を紡いでいくのか。そのプロセスをこのコンテンツで紹介していきます。
メディテーション絵画 |『時代の変化で注目されてきた「共創」の土台となる自己共感の誰でもいますぐできる基本とは』
ビジネスのスピードが加速し、変化へすぐに対応できなければ、個人や企業の存続に関わる‥‥という意識が高まり、注目されてきた言葉があります。
「共創」です。
例えば、企業で言えば、苦労して築き上げた競争優位であっても、ビジネス環境の急変で、ひとつの競合優位を長期継続的に維持することが難しくなった、連続的に競合優位を生みださなければ生き残れない、などと言われます。
また、「顧客との共創」を掲げ、お客様との関係を深化させる想いを経営方針としているところや、「共創サービスの体系化」を発表し、ブランドとして広めて行こうというところもあるようです。
個人でも、時代の流れが早くて世代間の考え方の大きなギャップがある、多様な情報の中でさまざまな考え方が横並びになるなど、違った考え方の人と触れる機会が増えました。
人と一緒に何かをしていくときに、想いを理解しあって「共に創る」姿勢の重要さが増していると考えられます。
どうやら、「共創」が大事な時代になってきています。
そこで、今回は良い「共創」をする始まりに、ちょっととっぴに聞こえるかもしれませんが、自己共感が必要では?と問いかけます。
いやいや、「共創」するのに、いちいち、自己共感なんて必要ないよ、という人もいるかもしれません。
でも、今、「共創」と共に、ビジネスの場でも自己共感が注目されてきています。
真に創造的、イノベーションな「共創」にはビジョンやミッションが必要と言われますが、効力のあるビジョンやミッションは、深い自己共感(企業レベルでも個人レベルでも)に基づいていると言われています。
私自身は、毎日眺めて自分や周囲が成長していく絵を目指す、ちょっと変わったオーダーメイド絵画を描いています‥‥ので、クライアントと画家で絵を【共創】しています。
描く傍ら、『クライアントと一緒に絵を考えて創っていくのがおもしろい』と声をかけられて、絵と言葉を行き来するオーダー絵画プロセスを、共感の心を軸に大学で研究もしています。
「共創」という言葉は、何か、を確認しておくと、
2004年、米ミシガン大学ビジネススクール教授、C.K.プラハラードとベンカト・ラマスワミが、共著『The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With Customers(邦訳:価値共創の未来へ-顧客と企業のCo-Creation)』で提起した概念と言われています。
そして、企業が、様々なステークホルダーと協働して共に新たな価値を創造するという概念「Co-Creation」の日本語訳が、「共創」です。今では、企業にとどまらず、文化芸術の分野にも浸透し始めています。
さて、ちょっと変わった画家の視点から、「共創」から自己共感までをあらためて考えてみます。
絵を一緒に創っていく共創の前に、クライアントと画家との共感があり、共感にはそれぞれの他者共感と自己共感があります。そして、絵のクライアントと話している場面を、研究者の視点で振り返ると、現代では自己共感が育みにくいと感じます。
ITにおける技術の進歩で、いつでも誰とでもつながれると同時に、一方では、いつでもどこでもつながる生活がやってきました。
共感をする能力は、経験によって育まれる部分があります。他者からの評価に触れる機会が多いと、他者に対する共感能力、他者共感の能力が育ちます。一方、自己共感を育むと言われる時間が減りました。
自己共感を育むのはどんなことか?
例えば、単なる‥‥、ぼーっとする時間。携帯の普及で減りました。ぼーっとする、のは、もっとも基礎的な自己共感を整える土台にできます。
なんだ、ぼーっとするって。と、侮るなかれ。
例えば、ノーベル賞を受賞した中村修二は、ぼーっとして、いろんなことから意識を一旦離す効用を著書の中で述べています。
画家やデザイナー、クリエイターなど、創造的な仕事をする人の間でも、ぼーっとするのを邪魔しないように、とよくいいます。
ぼーっとすることで、人は、内省したり、妄想したり、自分の感性を縦横に働かせて、一歩引いた視点でより良い答えを導くこともあります。
でも、それさえも、難しいのが今の時代かもしれません。
今、懐かしいと振り返られる昭和の時代。
そのころは、携帯電話もなく、パソコンもない。その時代は、自己共感の時間をおのずととることができました。
しかし、今は、便利であるがゆえに、意識的に自己共感の時間を取る必要があるのではないか、そのための自己共感のやり方も、あらためて振り返らなければいけないのでは、とクライアントとの対話から思います。
毎日眺めて自分や周囲が成長していく絵、自分のテーマの絵を目指す、ちょっと変わったオーダーメイド絵画を描いていく中で、自己共感を育むお手伝いを、さまざまな形でお手伝いしているので、
別の機会にまたそれをお話しします。
今回は、ちょっと肩の力を抜いてぼーっとできる、メディテーション絵画をお届けします。
今回完成した作品 ≫メディテーション絵画|ぼーっと肩の力を抜いて
著者の自己紹介

ビジョンクリエイター/画家の門間由佳です。
私にはたまたま経営者のお客さんが多くいらっしゃいます。大好きな絵を仕事にしようと思ったら、自然にそうなりました。
今、画廊を通さないで直接お客様と出会い、つながるスタイルで【深層ビジョナリープログラム】というオーダー絵画を届けています。
そして絵を見続けたお客様から「収益が増えた」「支店を出せた」「事業の多角化に成功した」「夫婦仲が良くなった」「ずっと伝えられなかった気持ちを家族に伝えられた」「存在意義を噛み締められた」など声をいただいています。
人はテーマを意識することで強みをより生かせるようになります。でも多くの人は自分のテーマに気がついていません。ふと気づいても、すぐに忘れてしまいます。
人生
の節目には様々なテーマが訪れます。
経営に迷った時、ネガティブになりそうな時、新たなステージに向かう時などは、自分のテーマを意識することが大切です。
また、社会人として旅立つ我が子や、やがて大人になって壁にぶつかる孫に、想いと愛情を伝えると、その後の人生の指針となるでしょう。引退した父や母の今までを振り返ることは、ファミリーヒストリーの貴重な機会となります。そして、最も身近な夫や妻へずっと伝えられなかった感謝を伝えることは、絆を強めます。そしてまた、亡くなった親兄弟を、残された家族や友人と偲び語らうことでみなの気持ちが再生されます。
こういった人生の起点となる重要なテーマほど、大切に心の中にしまいこまれてカタチにしづらいものです。
でも、絵にしてあげることで立ち返る場所を手に入れることができます。