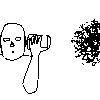十数年前、ロードバイクというスピードの出る自転車であちこち走ることを趣味にしておりました。
車に乗っている方だと邪魔だなと思ったことがあるかもしれませんが、ロードバイクとは、乗っている人がヘルメットをかぶり、すごく前かがみになっていて、かなりのスピードで走っている、アレです。
実際、乗っている人の体力にあまり関係なく、ふつうに漕いでいるだけで時速30kmくらい出る代物なので、人力で動く道具としては反則級にスピードが出るのです。
これも見たことがあるかもしれませんが、ロードバイクに乗っている人はたいていピチピチの服を着ています。空気抵抗を少しでもおさえるためです。
オートバイや車と違い、自転車の場合、エンジンはあくまで人間なので、空気抵抗はかなりのエネルギーロスになります。ゆとりのある服を着ていると、少しスピードを増しただけで、バタバタと服の裾が鳴り、その分推進力が失われるのが自分でわかります。
それを防ぐために、ロードバイクに乗るときの格好は必然的に全身タイツのようなものになるのです。
ロードバイク趣味の人々にとって、そのような服装をすることの妥当性は問うまでもありませんが、その格好の「取り扱い」については、人によりけっこう意見が割れていました。
すなわち、下半身にいたるまで体のラインをむき出しにした状態のままで、「飲食店に入っていいか」とか「電車で移動してもいいか」というような、公共の空間に入る際の線引きをどこに置くかが、人それぞれ違うのでした。
一方、ロードバイクのアパレルメーカーには、スポーツ向けとしての機能を強調したものだけでなく、中にはファッション性を追求するブランドもありました。
ジャージやパンツなど、ヨーロッパなどで行われているプロのレースを模範にした一般的なものだと、明るい色が多く、素材は最新のハイテクのものがほとんどです。対して、街で見てカッコいいものを意識したブランドというのは、色はモノトーンや暗色系を使い、生地に昔の機能性素材だったウールを使用するなど、より普段の洋服に近いテイストを盛りこんでいました。
個人的には、そういったブランドを、やりたいことはわかるが(高単価だし)、自己矛盾していると感じておりました。
なぜなら、やっぱりシルエットはピチピチだったからです。
ピチピチ感がなければロードバイクに乗る服ではなくなってしまいますが、それゆえに襟やボタンはもちろん、アパレル商品の顔であるシルエットを全部放棄しなくてはいけないというのは、豆腐を使って肉のようなものを作る料理のような苦しさが表れているのでした。
と同時に、服の役目とは人体を包むことであるにもかかわらず、ファッションの本質とは、いかに人体に沿わない形状を表現するかにあるのでは、と思ったりしたのでございます。