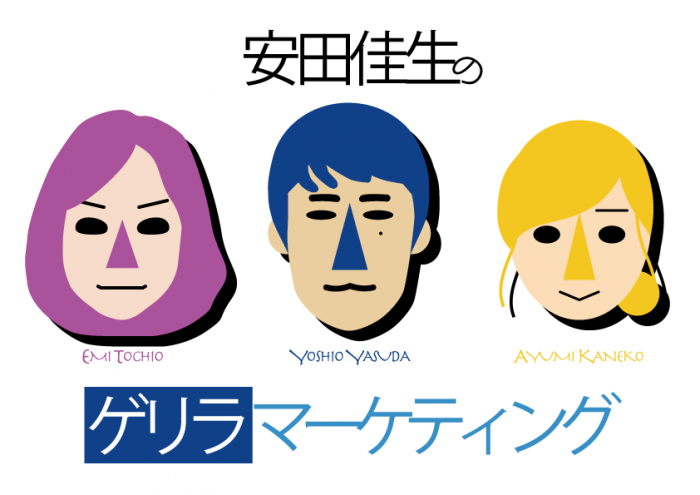前回も「やる気出ない」っていう話でしたけど、僕も数々の困難を今まで経験してきて、挫折してきまして、僕がたどり着いた結論は、体とか心を疲れさせないっていう。やる気が出ない状態をつくらないっていう。つまり、8月31日に追い込まれてから宿題をやるんじゃなくて、最初にちゃんとやろうねってことです。

こんにちは。いつも楽しくためになる情報をありがとうございます。みなさんの三者三様の切り口が面白く、新しい視点に驚かされます。私は有機農業のスタートアップ企業の経営者見習いで、3年目になりました。農業への参入は一時的なブームになっており各社が競って参入していますが、約7割が3年ももたずに撤退しています。当社も累積で3,000万円近い赤字を抱えていますが、まだまだ黒字化には時間がかかりそうです。農業は構造上儲けが出にくい仕組みのため、黒字化まで5年以上はみないとダメだと言われています。さて、このような儲かりにくい農業が日本には本当に必要なのでしょうか?その分の補助金などを工場にまわして、経済を強くするほうが国としてはよいのでは?と考えてしまいます。私は農業で生きていますが、この業界の未来が暗いものにしか見えません。みなさまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

いざとなったときに「おまえんところには一切食べ物を分けてやらん!」ってなったら、みんな飢え死にしちゃうじゃないですか。だから、「自給率、このぐらいは保っとかないとね」みたいなのがあって、それがどんどん輸入に頼ってるんで由々しき問題だとおっしゃる人もおりますと。

安田:どうなんですかね、国の捉え方にもよると思うんですけど、いろんな考えがあるんで、私は極端なんですが、僕は正直いって「食糧自給率とかは、もう今さらいいんじゃないのか」派ですね。たとえばエネルギーとかだって、結局頼らないといけなかったりするじゃないですか。

たとえば、だから、みんな国だと自給率とかって言うじゃないですか。でも、「新宿区3丁目の自給率どうなの?」って言わないじゃないですか。それは新潟とか広いとこでつくりゃいいじゃんってことで、でも新潟の人が「一切新宿のヤツには食糧を渡さん!」ってなったら同じことが起こるけど、「日本人どうしだし、そういうことにはなんないだろう」ということになってるわけじゃないですか。だから、もうちょっとそこは国とかじゃなくて、やっぱ日本って狭いですし、明らかに日本よりも安くて大量にジャガイモとかをつくれるところとかあると思うんで、ここでしかつくれない作物もあるでしょうし、日本人がすごいつくるのに向いてるのもあるでしょうし、人類全体で役割分担して、「分けてやんない」とかっていう意地悪なことを言わないで仲良くやろうよ、っていうのが私の考えです。

だから、補助金がもしなくなったらなくなったなりに、質の高いもの、以前ありましたけど嗜好品的なものを開発したりとか、あと、ブランドに工夫したりとか、どんどん生まれてくる気がちょっとしたんですけどね。

そう思います。だから、最終的には無理矢理関税とかで、最近トランプさんも「アメリカの製品買え」って言いますけど、結局欲しくなかったら買わないんで、最終的にはやっぱそういう税金ルールがだんだんとなくなっていって、「欲しいものは国境をまたいでちゃんと手に入るようにお互いしようね」っていうふうにたぶんなると思うんですよね。でも、今やっちゃうと「それに頼ってきた人どうなるの?」ってことがあるんで、政治家は、特に民主主義国家じゃできないじゃないですか。だって、選挙したら負けちゃうんで、その地域で。

打ち出そうとしたら、「もうちょっと自分たちでちゃんとやりなさい!」とか言ったら、そんな人誰が投票すんの?っていう。「私がみなさんの予算とってきます!」って言ったら入れるわけなんで、そこにも問題ありますよね。

まあでも、それより私が気になるのはですね、「この人農業やりたいのかな?」っていうのが。海外で通用するかどうかということも含めて、たぶん、自分が得意とか好きなことをやったほうがいいと思うんですよね。たとえばイチゴ農家さんがイチゴ育てんのがすごい好きで、美味しいイチゴつくりたくて、だけど、どうしてもコストが上がってしまうから、どうやって売ろうか、っていうのは後付けで考えることかなと思うんですけど。まず自分が農業をやりたいかどうかが大事で、僕はべつになくなんないと思いますし、やりたいんだったらやったらいいんじゃないのかなっていう。「国として」とか、あんま関係ないような気がするんですけど。
*本ぺージは、2018年12月19日、ポッドキャスト「安田佳生のゲリラマーケティング」において配信された内容です。音声はこちらから
ポッドキャスト番組「安田佳生のゲリラマーケティング」は毎週水曜日配信中。