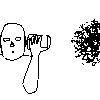人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第59回 損得勘定の先にある、心を満たすお金の使い方

今日は安田さんに「お金の使い方」について聞いてみたくて。というのも、前回のお話にあった金融リテラシーもそうですけど、「お金の使い方の教育」ってES(従業員満足度)においても大事だと思っているんですよ。

ああ、確かに皆さん意外とそこをわかってないんですよね。例えば売上1億円で1000万円の利益が出たビジネスがあったら、「1000万円儲かったね」としか見ない人が多い。そうじゃなくて「1000万円作るのに9000万円必要だったね」と見なければいけない。

ははぁ、面白い。そういえばDMMの亀山会長が「お金を稼ぐのは科学だけど、使うのはアートだ」と言っていましたが、さもありなんですね。実際、稼ぐより使う方が難しいんですよね。ハッキリした正解がない分、アート的なセンスが必要になってくる。

ふ〜む、会社が「お金の使い方を学べる場」になるってことですね。すごくいいと思います。日本人ってなぜかお金を使うことを隠したがる傾向がありますけど、もっともっとオープンにしていくべきだと思いますし。

同感です。いいお金の使い方をすれば人生がどんどん豊かになるっていうことを、皆に知ってもらいたい。「なるべく安くすます」「なるべく損をしないように生きる」みたいな発想を、できるだけ早く書き換える必要があるなと。

そうですね。私自身も消費者として、安くて美味しいお店を求める気持ちはもちろんあります。でもそれとは別に、応援したい生産者から買うとか、少し値が張っても情熱や技術に触れられるお店に通うとか、そういう選択も大事にしていて。

そういうお金の流れが社会を豊かにしていくんですよね。例えば「3万円のコース料理」とだけ聞けば多くの人は「高すぎる!」と言うでしょうけど、それが有名なフレンチのシェフが一生かけて培った技術をこめて作るものだとしたら、価値は3万円どころじゃない。

そうそう。支払うお金は単なる贅沢じゃなく、 その人の情熱や創造性への敬意でもあるわけですよね。寿司職人でも本当にこだわる人は、毎日最高のネタを仕入れたり、技術を磨いたりと大変な労力をかけている。そういうこだわりに対してお金を使えるかどうか。そういう観点では、貯金額がどうとかはあまり関係がないんですよね。

まぁ経営の場面では合理性は必要ですけどね。でも人生まで合理性だけで捉えてしまうと、すごく味気なくなると思うんです。「金銭的な価値」では測れないところにこそ、本当の価値がある場合も多いですから。そういった価値に気づけるかどうかが、人の人生を豊かにする鍵なのかもしれません。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。