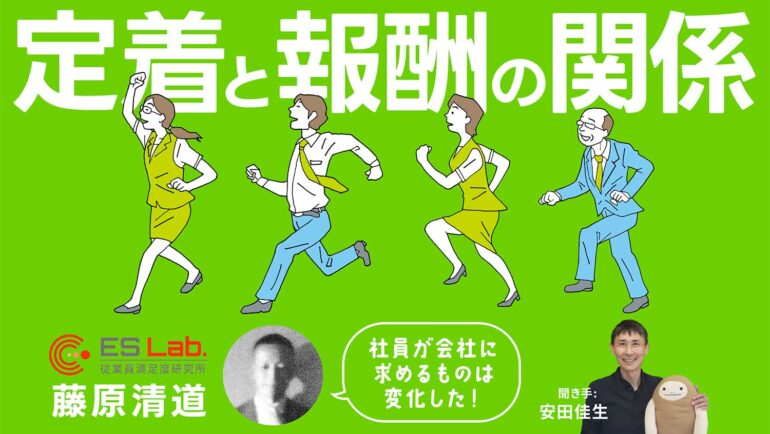人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第9回 「従業員」という言葉は使ってはいけない?

藤原さんが経営されている「従業員満足度研究所株式会社」ですが、なぜ「社員」ではなく「従業員」という言葉を選んだんですか? 従業員という言葉には、「従わせる」というニュアンスがあって少しネガティブな印象も受けるんですが……。

だから「事業に関わる全員」というニュアンスのある「従業員」を選んだ次第です。「理念」や「クレド」を掲げて同じ目的に向かっていく仲間たち全員、ということですね。そういう意味では社長だって「従業員」なんですよ。

まさにいま話していたように、どこか傲慢なニュアンスを感じさせてしまうからです。もちろん「従業員っていうのは、社長も含まれるんだよ」という話をすることもありますが、だからといってその定義付けを押しつける気もなくて。

その通りです。社長が「これは(自分じゃなく)君たちが守るルールだから」というスタンスで作ったものには意味がありません。当然、社長自身も守るんです。むしろ率先してそれを実行する人でなければならない。

いまこれを読んで「えっ、そうなの!?」なんて思っている経営者さんもいそうですが(笑)。でも国とかで考えると当然なんですよね。どんな偉い立場にいる人も、法律や憲法は守っている。それと同じで、つまり行動指針の方が社長命令より上になければいけない。

なるほど、すごくわかりやすいです。ちょっと話は変わりますが、海外ではエンプロイヤー(雇用主)とエンプロイ(雇用者)のように立場をハッキリと分けていますよね。日本でいう上級公務員などのキャリア組と、市役所の一般職員などのノンキャリア組みたいな。

ええ。社長だから偉いわけでもないし、パートさんだから偉くないわけでもない。だから、区別があることと従業員満足は必ずしも相関するわけではないと思います。区別があろうがなかろうが、それぞれの立場で何をするのか、どう伝えていくのかが重要なわけで。

なるほど。重ね重ねこれを読んで「マジかよ…」となっている経営者さんがいそうですが(笑)、でも本来行動指針や理念というのはそれくらいの覚悟を持って決めるものですよね。そうでなければ「絵に描いた餅」になってしまう。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。