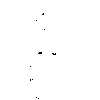「社長……あの……そうですよね」
何か言わなければと、適当な相槌を打った。すると社長はカッと目を見開いた。
「何がそうですよね、だ! あんたなんかに俺の気持ちがわかってたまるか! 会社に雇われて、ぬくぬく営業してりゃいいだけなんだからな! 採用ができようができまいが、あんたの懐は何も痛まない。だけどな、俺にとっちゃ、死活問題なんだよ! 採用できないことが、こんなに……こんなに……」
そして社長はまたうなだれ、頭を抱えるようにしながらこめかみを強く揉んだ。
社長は明らかにおかしかった。情緒不安定というか、人が狂う過程に立ち会っているような感じがする。そのキッカケを作ったのは俺たちなのかもしれない。だが、目を見開いてこめかみを激しく揉む社長を見ていると、何をそこまで苦しんでいるのかと違和感を覚える。
……たかが採用の話じゃないか。死活問題って……どうしてそこまで……
その時、背後でガロンガロンと鈴の音がした。ハッとして振り返る。
茂木と保科だった。緊張した面持ちの茂木と、いつも通り無表情の保科。やがて保科が茂木の大きな背をすっと押すと、茂木は頷いて、ゆっくりとこちらに近づいてくる。
俺の横を過ぎ、そして社長の前へ。視線を落としていた社長が、その気配にゆっくりと顔を上げる。
「……茂木、どこ行ってやがった。もうランチまで時間がーー」
「社長、いや、店長」
言葉を遮るようにして茂木が言う。
「俺と勝負してください」
その言葉に、社長は眉間にしわを寄せ、口をぽかんとあける。いや、俺も同じ気持ちだった。この人、一体何を言い出すのか。
「……お前、なにわけのわからないことを言ってんだ。いいから早く開店準備をーー」
「受けてくれなきゃ、この場で辞めます」
「な……」
驚く社長を残し、茂木は店の奥へと歩いていく。そしてそのまま、カウンターの向こう、つまり厨房に入っていってしまった。呆然とその背中を目で追っていた社長に、保科が声をかけた。
「審査員は俺たち、やりますから」
保科の細い腕が俺の肩口に置かれ、「な?」と言う。
「どっちのバーガーがうまいか、知りたいよな」
「え?」
「バーガーの神様がご健在かどうか、確かめないと」
保科の言葉に、俺より社長が反応した。
「神様……バーガーの……」
「おかしな話でしょ。でも、茂木さんがそう言うもんだから。社長は、いや、店長はバーガーの神様だったんだって。そうまで言われちゃ、確かめたくなるじゃないですか」
「……」
厨房の中に入った茂木は既に、調理のための準備を始めていた。その表情には、確かに覚悟の色が見て取れた。茂木は本当に、社長がこの勝負を断ったら辞める気なのだろうか。
先ほどHR特別室で見た、茂木の思い詰めた顔が浮かんだ。
微かに、納得感があった。あの人がいま対峙しているのは、職場としてのこの店ではないのだ。そうではなくて、10年以上にもわたってこの店につきあってきた、自分自身というものと対峙しているのだ。
「社長のハンバーガー、食べてみたいです。この勝負、受けてください」
気付いた時には、俺もそう言っていた。
(SCENE:018につづく)

ROU KODAMAこと児玉達郎。愛知県出身。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。デザイナーはデザイン専門、ライターはライティング専門、という「分業制」が当たり前の広告業界の中、取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。2017年フリーランス『Rou’s』としての活動を開始(サイト)。企業サイトデザイン、採用コンサルティング、飲食店メニューデザイン、Webエントリ執筆などに節操なく首を突っ込み、「パンチのきいた新人」(安田佳生さん談)としてBFIにも参画。以降は事業ネーミングやブランディング、オウンドメディア構築などにも積極的に関わるように。酒好き、音楽好き、極真空手茶帯。サイケデリックトランスDJ KOTONOHA、インディーズ小説家 児玉郎/ROU KODAMAとしても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート)。
お仕事のご相談、小説に関するご質問、ただちょっと話してみたい、という方は下記「未来の小説家にお酒をおごる」よりご連絡ください(この方式はもちろん、『安田佳生の「こだわり相談ツアー」』が元ネタです)。