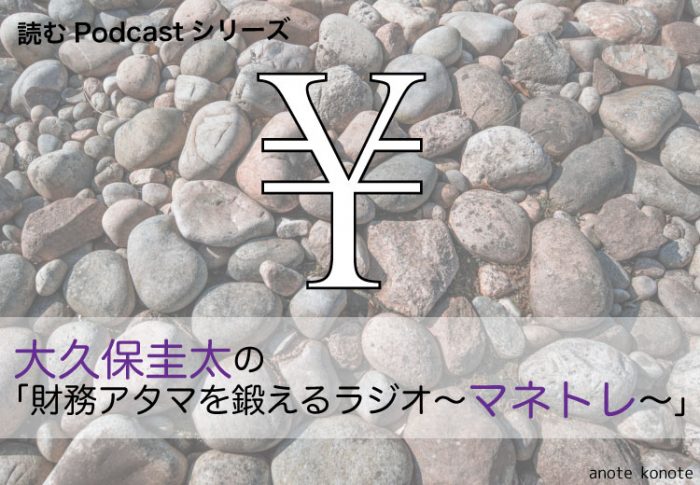企業は会計ルールで計算した法人税などについて決算短信などで開示していますが、この数値と実際の納税額にずれがあるとのことです。「会計と税務では収益の計算方法などが違うため」と書かれていましたが、この計算方法のずれとは、どういうことなのでしょう。たとえばの例で簡単に説明していただきますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。

税効果会計後。理論値に近いのかな。「本来ならこういう数字だよね」みたいな。ただ、会計処理と税務の、たとえば損金算入ができないけど会計上損金にしてるとかを税金上否認するから、そうすると税金が高くなるわけで、高くなったものだけど、来年は損金になると安くなるわけだから、そうすると、そこをマイナスして来年にくり越して、来年、法人税はその分安くなる。そのときは法人税等調整額をプラスして、理論上の法人税額にするっていうこと。

最近見てないからわかんないや(笑)それがほとんど調整されてないのよ、法人税ぐらいで。でも本来、上場企業とかの申告書とかだと、昔つくってたけど、それが3枚も4枚もあんのよ、調整項目が70個あるから。

それで調整していくから、ちゃんとした会計基準と税務がずれるに決まってて。要は税金をきちんと納税させたい国税の思惑が税法にあるわけ。でも会計は、基本的には投資家保護とか、投資家が正しい判断するために会計処理ちゃんとしてねっていう話だから、観点がぜんぜんちがうんで、それを調整するのが税理士の本来の役割なわけで。

逆に中小企業だって、やろうと思えば……って、やってるところもあると思うけど、税効果会計、たとえば「去年1億赤字出してて、今年1億利益出ました」っていったら、えーと、基本的に欠損金を持ってれば今年の納税額はゼロなわけで、そうすると決算書おかしいじゃん、1億利益出て。本来は去年利益が出てないそこで1億円の欠損金に対して、30パーの税効果会計を適用しておくっていうのが正しくて、今期は1億出て、3,000万、法人税が本来かかったよ、っていうので所得を出すっていうのが正しいんだけど。だから、そのずれだね。