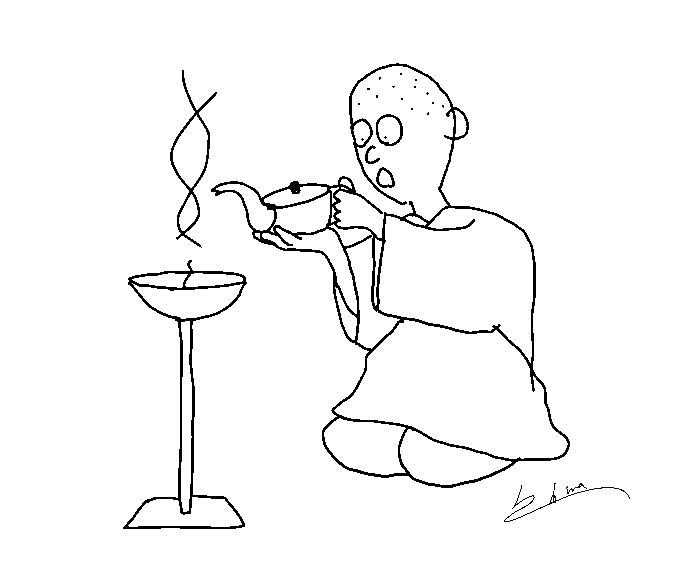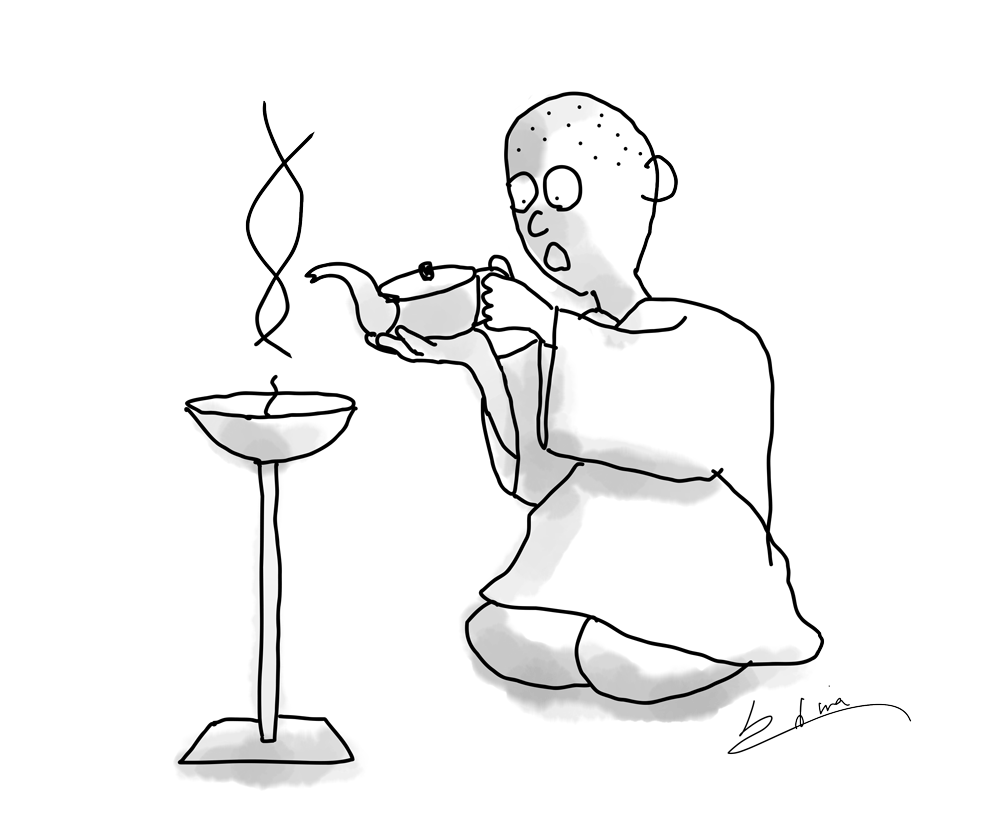このコラムについて
「担当者は売り上げや組織の変革より、社内での自分の評価を最も気にしている」「夜の世界では、配慮と遠慮の絶妙なバランスが必要」「本音でぶつかる義理と人情の営業スタイルだけでは絶対に通用しない」
設立5年にして大手企業向け研修を多数手がけるたかまり株式会社。中小企業出身者をはじめフリーランスのネットワークで構成される同社は、いかにして大手のフトコロに飛び込み、ココロをつかんでいったのか。代表の高松秀樹が、大手企業とつきあう作法を具体的なエピソードを通して伝授します。
本日のお作法/油断禁物
「紹介で来られた方のことなんですが…」
某大手の人事担当Yさんが、コーヒー片手に雑談の場で語ってくれたのは、最近のリファラル採用での「苦い経験談」でした。
近年、大手であっても「若手採用」は簡単ではありません。
「ヤフー」さんは通年採用を、「富士通」「メルカリ」さんはリファラル採用を促進させ、「サイバーエージェント」「ソフトバンク」さんは社員の主体的な学びを促す仕組みを導入して「採用力」を高めています。
そんな流れのなかでの、Yさんからのエピソードです。
◆紹介者頼みタイプの増加
「部門でも評判の社員からの紹介だったんですが、面談で『御社のことはほとんど詳しくなくて…』と言われてしまって。。」
「いやいや、せめてホームページくらいは見ようよ、、と」
Yさんいわく、リファラル採用は候補者との「信頼関係を前提」にしているぶん、マッチング率も高い。
ですが、それは“最低限の準備ができていれば”の話。
「多いのが“紹介者頼み”タイプですね。紹介してくれた先輩の話ばかりで、自分の言葉が出てこない。。」
「『それってあなたの考えですか?』と聞きたくなることもあります」
◆カルチャーフィットの壁
さらに最近は、条件面のズレやカルチャーフィットの問題も増えているそうです。
年収や働き方に対する感覚が、企業と候補者で大きく違っていると、いくらスキルがあっても採用は見送りになることも。
「面談では、“この人、うちのカルチャーで楽しくやっていけそうかな?”って目で見ています。スキルよりも、そっちを重視する場面もありますよ」
◆紹介はスタートライン
リファラル採用というと、“瞬間内定”のように思われがちですが、実際には、「紹介をもらってからが勝負」。
企業との相性、自分の価値観、働き方のビジョン──それらを自分の言葉で語れるかが、分かれ道になるようです。
Yさんは最後にこう締めくくりました。
「紹介だからって、結局は“自分を売り込む力”がなければ、次には進めませんから」
いくら採用難であっても、大手さんの採用現場はやはり「シビア」なのであります。