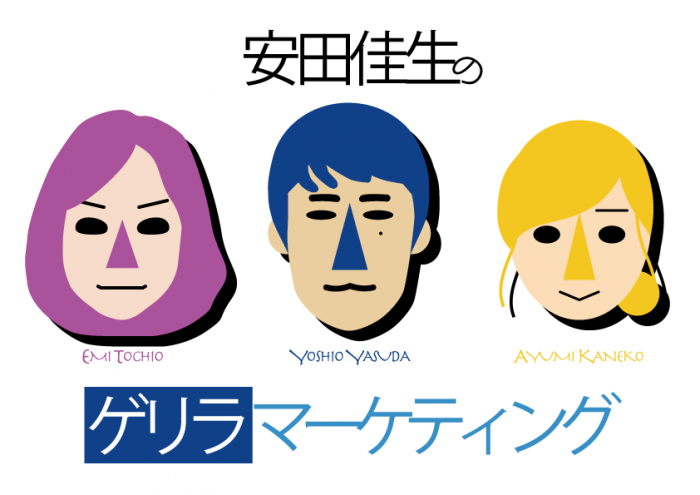うちの子は合わないですが合う人もいて。たとえば社会科見学に行くとか、習字をやるとか、美術・アート的な時間とか、色々体験ができるってすごいなと思う。昔は全然いらないと思ってたけど「素敵な体験してますよね」って今は思う。

だけど非常に画一的で。先生に時間がなくて余計なことが一切できないとか、先生の省力化のためにルールがめちゃくちゃ細かく決まってるとか、そういうのは辛い気がします。カリキュラム自体はよくできているけど、そこから外れた子を救うすべがない。

そもそも子供はまだ何も知らないんだから、「世の中こんなにいろんなことがあるんだ」って気がついて、自分の適性を見つけていくのが教育だと思う。最初からゴールが決まっていて1本道で落ちたらアウト、みたいな感じじゃないですか。

とはいえ何も考えずに近所の小学校に行かせると、気がついた時には選択肢が狭まってそうで。「この3つの中から選んでね」みたいになってる気がするわけですよ。やっぱ親はこどもの可能性を広げたいと思うじゃないですか。

そんなのわかんないですよ。わかんないけど安田さん曰く、ちょっと可能性を狭めてるんじゃないかということで、もっと多様性が欲しいですね。いろんな子供をフォローできるようなシステムだともっと教育しやすい、って感じですかね。

みなさんからの質問をお待ちしています。質問がある方は境目研究家安田佳生のホームページ(安田佳生ドットコム)からお申し込みください。では来週もお楽しみに。
*本ぺージは、2024年5月1日、ポッドキャスト「安田佳生のゲリラマーケティング」において配信された内容です。音声はこちらから
*Spotify、Google Podcasts、Apple Podcast、iTunes、Amazon Musicでも配信中!
ポッドキャスト番組「安田佳生のゲリラマーケティング」は毎週水曜日配信中。