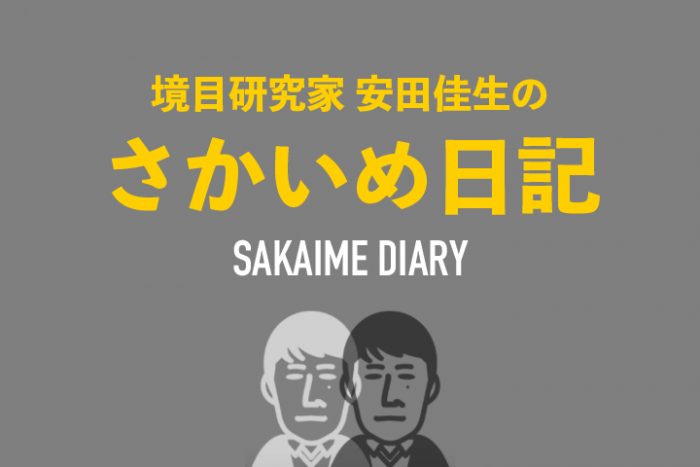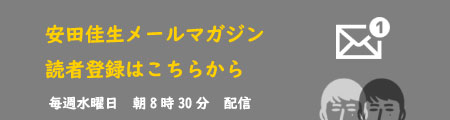いつも相手から依頼が来る仕事と、こちらから仕掛けないと依頼が来ない仕事。前者のほうが楽に稼げている気もするが、それは大きな間違いである。依頼が来るのはクオリティの割に安いからであり、相手の顕在ニーズに合わせた仕事を受けているからである。単価を上げたいならこの逆を行かねばならない。
安くて、量が多くて、美味しい洋食屋を思い浮かべてみよう。もちろん流行っているだろう。客は呼び込まなくても次から次に入ってくる。このままクオリティーを下げず、値上げもせず維持できるなら、集客の心配は不要である。だがこのお店は儲からない。そして働くスタッフはどんどん疲弊していく。
安くて、美味しくて、量が多い洋食を食べたい、という顕在ニーズ。そこに合わせてお店を作れば集客の心配はなくなる。だが儲からない。クオリティを落としたり価格を上げたりすると客が離れていく。だから数をこなす他ない。薄利多売はそこで働くスタッフを追い詰める。持続可能な仕事とは言えない。
ここに集客の落とし穴がある。集客への投資を小さくし過ぎると、儲からない上に持続不可能なブラック仕事が誕生する。フリーランスが1人でやるならそれもありだろう。休みなく働き続けることを受け入れれば仕事は安定する。だが組織化すると必ず破綻する。こんな仕事を希望する人などいないからである。
単価を上げたい、時間に余裕のある働き方がしたい、仕事を選びたい、一緒に働く人を豊かにしたい。もしそう考えるなら根本から発想を変えなくてはならない。相手の中に頼みたい仕事があり発注単価も決まっている。こういう仕事は受けてはならない。相手のニーズを掘り起こし自ら依頼を作り出すのだ。
依頼された仕事を受けるのではなく、こちらが受けたい仕事を依頼させる。当然のことながら啓蒙や集客にコストも時間もかかる。その代わり、こちらが価格と納品クオリティをコントロールできる。時間あたりの収益が増えるので働く人が豊かになる。人が疲弊しないので持続可能なビジネスとなる。
すべては集客と啓蒙への投資にかかっている。すでにあるニーズに合わせて「売れる価格・売れるクオリティ」で商売する。これは経営ではない。単なる安請け合いである。ひとりで働くならまだしも、人を巻き込めば必ず不幸にする。自ら依頼を作り出す気がないのなら組織を作ってはならない。
尚、同日配信のメールマガジンでは、コラムと同じテーマで、より安田の人柄がにじみ出たエッセイ「ところで話は変わりますが…」と、
ミニコラム「本日の境目」を配信しています。安田佳生メールマガジンは、以下よりご登録ください。全て無料でご覧いただけます。
※今すぐ続きを読みたい方は、メールアドレスとコラムタイトルをお送りください。
宛先:info●brand-farmers.jp (●を@にご変更ください。)