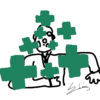人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第33回 会社の中から始めるベーシックインカム

今日は「ベーシックインカム」についてお聞きしてみたいなと。ベーシックインカムって一般的には「全国民が一律にお金を支給される制度」なんですけど、私が考えるベーシックインカムでは、働かない人にお金を配る必要はないと思っていて。

働く、つまり「人の役に立ってお金をもらう」というのは変わらないんですけど、大事なのは「自分の好きなことや得意なこと」で人の役に立つ、ということなんです。1人1人の個性や特徴を活かせる役割があるはずなので。

ああ、なるほど。つまり「稼げる仕事かどうか」は問題じゃないということですね。自分の得意なことで、かつ人の役に立っていることをしてさえいれば、生活が保証されると。いや〜おもしろいですね。実現するには政治的なハードルもありそうですけど。

そういうことです。日本が豊かな国になっていくためには、とにかく生産性を上げていくことが重要です。そういう意味では、無条件で一定額のお金を払う従来の「ベーシックインカム」では解決されない気がして。

ははぁ、確かに。安田さんの仰る仕組みの方が、好きなことや得意なことをやっている分、生産性は上がりそうです。それに「1人1人の能力を平等に評価している」という意味では、コミュニティのあり方としても理想的な気がします。

ええ。そして、ある意味それは「かつての終身雇用や年功序列の時代への回帰」だとも言える。実際、昔の企業ってどちらかというと「皆横並びで平等に」って感じだったじゃないですか。それが日本もどんどんアメリカ型の実力主義社会になってきて、それなのに生産性は全然上がらない。

なるほど。昔のシステムの方がよかった、という考え方もできるわけですね。実際かつては世界企業ランキングの上位を日本企業が独占していたわけですからね。下手にアメリカの真似をしてからおかしくなった、と考える人がいてもおかしくない。

そうそう。でもそれは感覚がズレている気がするんです。「あの頃は人口が増えていたから生産性が高かっただけ」という側面もある。一生懸命いいものを作っていれば、どんどん利益が出る時代だったわけですよ。

そうなんです。結果、実際すごく発展しましたよね。ただ人口減少が始まってくると、利益を生み出す人が足りなくなって、どんどんジリ貧になっていった。さらに言えば、テクノロジーが進歩して一般化することで、高い技術力なんてなくても「いいモノ」が作れるようになってしまった。

日本人の気質が活かせなくなってきたわけですね。…それにしても、「日本人の生産性がなぜ低いのか」という点は意見が分かれるところではありますね。個人的には「イヤイヤ仕事をしている」ことが大きいような気がしますけれど。

まさに同感です。今の日本人は条件で仕事を選ぶことに誰も疑問を持っていない。月給はいくらか、福利厚生はどんなか。そんなことばかりで会社や仕事を選んでしまうんです。でも本来はそうじゃなかったはずで。

「好き」と「得意」が両立しているのがベストですが、少なくとも「得意なこと」をやらないとダメですよ。長く採用のお手伝いをしてますけど、営業が全然好きでも得意でもない人が現場で営業をやっていたりする。なんでそんなやりたくないことをやってるのかと聞くと、「そりゃ生活していくためですよ」と返ってくる。

言いたいことはわかるんですけどね。日本の場合、「生きていくためにはやりたくないこともやらないといけない」という呪縛が強すぎるんですよ。実は私も以前「成果が出ない社員」に対してなんとか頑張らせようとしていたことがあるんです。でも、本人が好きでも得意でもない業務を担当している限り、なかなか難しいんですよね。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。