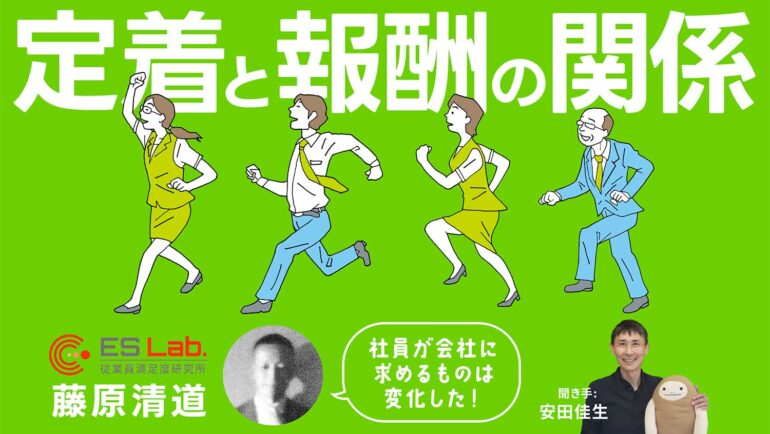人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第4回 外的報酬と内的報酬

ああ、確かに。労働条件と仕事のやりがい、どちらが大事なんですかね。従業員満足度のプロである藤原さんはどう思います?

これはもう「両方大事」ですね。「外的報酬」と「内的報酬」という言葉で表されたりもしますけれど。ベースとして外的報酬(労働条件)はある程度高くないといけません。ここが極端に低ければ、やはり満足度は上がらない。

でも藤原さん、かつては「仕事は辛くて当然」「楽しさなんて求めちゃいけない」と思ってたんですよね(笑)。随分変わったんですねぇ。

でもね、そうやって藤原さんは変われたかもしれないけど、世の中の経営者ってまだまだ「利益至上主義」の人が多いと思うんですよ。先日お話してくれた理念やクレドなんかも、結局は会社のイメージアップのため、つまり利益のために作ってる会社が多いんじゃないですか。

それは非常に重要なポイントです。私自身、従業員満足度研究所の他にもう一社、いわゆる実業をやっている会社を経営していますが、中には地味で面白くない仕事もあるわけですよ。

でもそこは考え方なんです。たとえばパッケージを組み立てる仕事をしている人に、「あなたがこうやって組み立ててくれることでこういうことに繋がっているんだよ」「このパッケージがこんな風にお客様の満足に繋がっているんだよ」と伝えるだけでちょっと変わってくる。

あるいは「シールを貼る」という仕事があったとして、「このシールにはこんな意味があって、これがあることでこんな人たちが喜んでいるんだよ」と伝えてあげる。そうすると、毎日だたシールを貼っていただけのスタッフから、「このシールの位置はもう少し右側の方が良いんじゃないですかね」なんて提案が出てきたりするわけですよ。

なるほどなぁ。とはいえ、ですよ。たとえばマクドナルドで働いている人が、「このお客さんはお腹が空いていそうだから、お肉を2枚入れてあげよう」なんて勝手にできないわけじゃないですか(笑)。つまり、工夫の余地がない会社もあるんじゃないですかね。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。