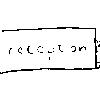有名なビジネス系のマンガを見ていたところ、作中のキャラクターが
「日本では、過去の経済的失策が「労働人口のほとんどが3世代がサラリーマンになる」という悪影響をもたらした」
と語るくだりがありました。
いわく、昔は生家が商売をしていた家庭が多く、そこに育った人は商売感覚をおのずと身に着けていたため、起業して次世代の経済の柱になる好循環があった。しかし、経済状況の変化で自営の割合が減少し、サラリーマンが3代も続いてしまうとその土壌が完全に失われてしまう。それはいずれ社会に重大なダメージを与える、という話でした。
その説が事実かどうかはさておき、環境が人の思考や行動を大きく左右するというのはたしかだと思います。
実家が商売をしていることを通じて商売人として育つのかというのは、正直わかりません。
かつては業種を問わず、子供のうちから家業の手伝いをするのが常識だった世代があり、そこでは親のやっていることから仕事のノウハウを得るのは当然のことだったでしょう。やがて、子供と労働の関係が見直されはじめると、親もむしろ子供に積極的に仕事について伝えることは控えるようになったはずです。(親もヒマではないですから)
親が教えてくれなくとも、誰しも社会に出れば商売に関わることになります。
ありがたいことに、体ひとつでもどこかに潜りこめば、遅かれ早かれ、今度はそこで仕事について学ぶことになるのです。
しかし、個人的には最初に就職してから幾星霜、商売についてなんらかのセンスが気づいたら磨かれていた、という体験は悲しいかな、一度としてありません。
思い返せば、社会に出て間もないころからなんとなく、ふわふわした違和感のようなものはおぼえていたのです。それは現在においてもあまり変わりありません。
ただ、自分含めた同じサラリーマンとしての属性をもつ人々を並べてみると、共通して感じられるのは
「なんだか儲けられなさそうなかんじ」
でした。
お金をやりとりしていても、条件を交渉していても、結果が良くても悪くても、それら我々サラリーマンがビジネスと認識しているものは、あまりに部分的な作業に過ぎません。
ときに、わたくしたちはその作業を「専門性」などと称しますが、それ単独を完成品として買ってくれる人は現れないのです。
ほんとうの意味では一円も生み出していないのに、「りっぱにビジネスしている」という自己への無理解こそが、いま思うと違和感の正体だったのかなー、なんて思ったりいたします。