HR 第3話『息子にラブレターを』執筆:ROU KODAMA
SCENE:032
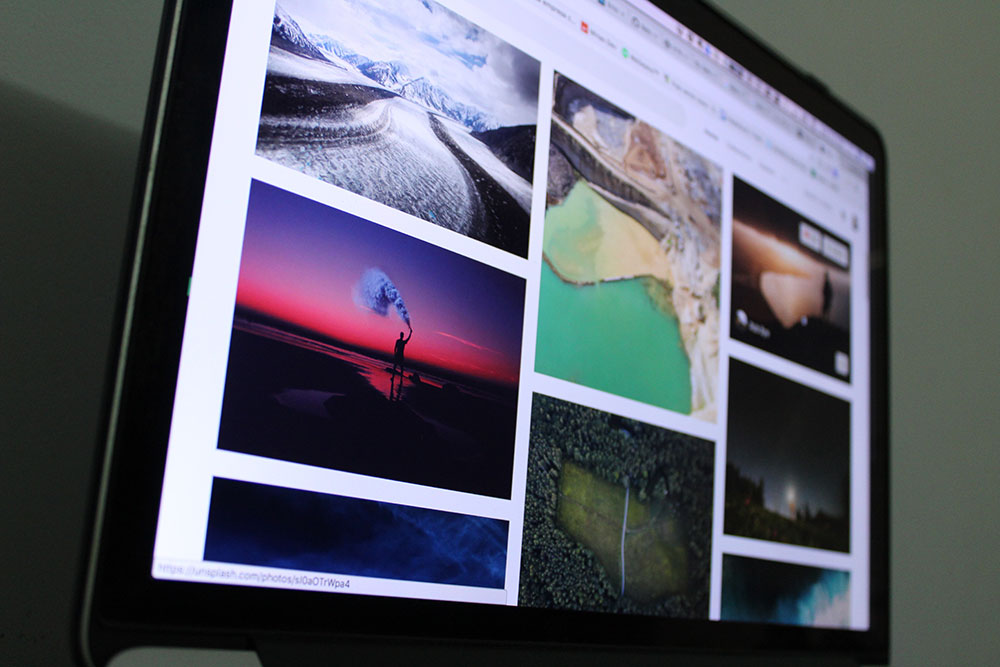
「それで、何か思いついた?」
1時間ほど経った頃、相変わらずソファの上でスマホをいじっていた宇田川室長が聞いた。少し前から答えを用意していた俺は、振り返って言う。
「正直に書いたらどうかと思いました」
「正直に?」
室長は表情を変えずにオウム返しする。視線はまだスマホにある。指が動いているのを見ると、何かを読みながら俺の話を聞いているらしい。
「だから……中澤工業の状況を、全部正直に書くんです」
「ほう」
その気のない反応に、苛立ちを覚える。なにが、ほう、だ。
原稿はメリットで埋め尽くす、マイナスポイントは書かないのが基本、という求人広告で、「全部正直に書く」と言っているんだぞ。原稿作成において、そんな提案をクライアントにしたことなど一度もない。いつだって俺は、「いい所を膨らませて書きましょう」と言ってきた。そうやって作った原稿の方が明らかに効果があるし、そもそも、会社の至らない点をバラすような原稿では決済者のOKがもらえないのだ。
「……中澤工業には、同業他社とくらべて明らかに劣っている点がいくつもあります。給与も、制度面も、労働環境も、全部標準以下だ。それらをすべて隠すことは困難です。だったらもう最初から、全部ぶちまけてしまって、納得した上で応募してもらった方がいいんじゃないかと」
そうだ。中澤工業にはマイナスポイントがあり過ぎる。労働環境だけならまだごまかしもきくが、給与となればそうもいかない。月給20万円の募集を、月給30万円と書くわけにはいかないのだ。それでは虚偽広告になってしまう。だからこの際、何も隠し立てせず素っ裸になってみたらどうか、というのが俺の案だ。最初からすべてをさらけ出すことで、志望動機の強い応募者を集める手法だ。
俺の説明に「ふうん……」と呟いた室長は、スマホから俺に視線を移すと、言った。
「なんか、クーティーズみたいだね」
「……え?」
「つまり君は、中澤工業の採用課題を、クーティーズと同じやり方で解決しようとしてるわけだ」
思わず口ごもる。
図星だった。
クーティーズの原稿を見た時、こんな原稿に応募してくる奴が本当にいるのか疑問だった。だが実際、効果は出た。採用できるかは別として、応募数は非常にいい。あの原稿が変わっていたのは、店の状況があまりよくないことを正直に書いている点だ。それが逆に、求職者にウケた。掲載1日で10件の応募。こういう「事例」がある以上、試してみる価値はあるではないか。
「た、確かに参考にはしました。でも、中澤工業の状況と似ているのも事実です。中澤工業もクーティーズ同様、いろいろな課題を抱えている。それをしっかり表現することで、それでもいい、という人が集まるんじゃないかと思ってですね……」
「ふむ」
「実際、クーティーズは効果が出てるじゃないですか。だから、同じ手法を試さない手はないというか……」
室長は、よっ、っと勢いをつけて体を起こした。
「ま、悪くないと思うよ。しかし、クーティーズのやり方と、そっくり同じというわけにはいかない」
俺は自分が不機嫌な顔になったのを自覚した。
クーティーズの手法――いま隣の席でイヤホンをしながら作業をしている、どう見ても社会人には見えない頭のおかしい制作マン・保科の手法――をパクった、もとい、参考にしたのは事実だ。
だが、そこに根拠があるのだから問題はないはずだ。それに、クライアントに対してしっかり持論を展開する保科と違い、俺はまだ室長の力量を測りかねていた。営業としてどんな実績があり、どれほどのスキルを持っているのかよくわからない室長に、自分の意見を否定されるのはおもしろくない。
「……どういうことですか」
不機嫌を隠さず俺が聞くと、室長は肩をすくめるようにして、答える。
「クーティーズに応募が来てるのは、あれは……業態のアドバンテージがあるからだよ」
「アドバンテージ?」
「いま、クラフト系、手仕事系の飲食店は人気があるからねえ。コンビニやスーパーはちょっと、マクドナルドのクルーでも物足りない、という人にとって、クーティーズみたいなこだわったお店のスタッフ、というのは魅力的に映るんだろう」
「……」
「1日で応募が10件あったからって、それがどんな10件なのかは知れたものじゃない。だから保科くんは、すぐに全員と連絡を取れって言ったんだ。簡易なエントリーシートだけ見てても、その人がどんな人間で、どんな気持ちで応募してきたかなんてなかなかわからないよ」
そんなこと……言われなくたってわかってる。そう思おうとしたが、言い返すことはできなかった。
「ま、要するに、クーティーズには業態が根拠の<ラッキー>があり得るってことだ。でも、かたや中澤工業はどうだろう。業種で見ても職種で見ても、あまりラッキーは起こらないように思わないかい?」
「……そうかも、しれませんけど」
しぶしぶ認める俺に、室長はどこか淡々とした口調で続ける。
「君の言うように、全てを正直に書いた原稿を掲載したとしよう。確かにあの会社の現状を伝えることはできるかもしれないね。でも、これから自分が働く場所を真剣に探している求職者が、わざわざ中澤工業を選ぶだろうか。同情はするかもしれない。でも……それだけだ」
いつも穏やかで、見方によっては「緩んでいる」と言ってもいい室長の表情が、一瞬、キリリと鋭くなった気がした。えっ、と思わず何度か瞬きをする。見れば、室長の顔は既に、いつもの呑気そうな笑顔に戻っていた。
「室長なら、どうするんですか」
不機嫌な気持ちはどこかにいきつつあった。室長の考えを聞きたい。この人なら、営業としてどんな提案をするのか。
「そうだねえ。やっぱり、中澤工業にしかない魅力、を見つけるべきなんじゃないかな」
「魅力、ですって?」
一瞬ふくらんだ期待が、急激にしぼんでいった。

















