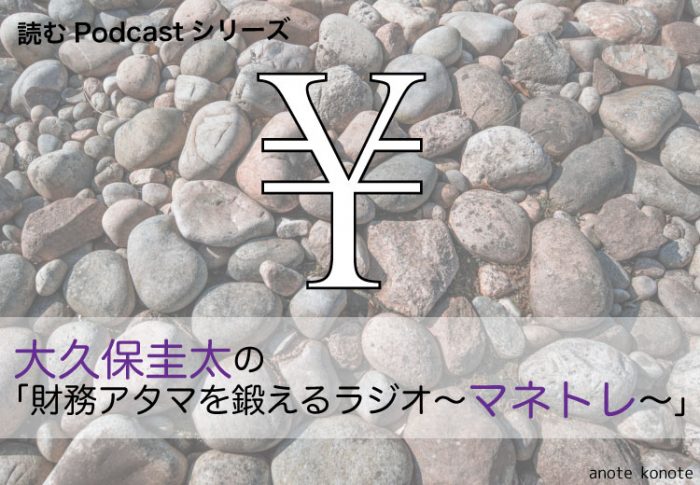で、話してたときに、「いまだにサイコロ給やってんですか?」みたいな話をしたらしくて、そのときに「やっぱり給与って、結局どこまでいっても答えがないから、答えがないものというのを表現するためにも、いまだに『あいまいである』って言うためにもサイコロ給は残してる」って。同じような話ですよね、大久保先生の話と。

これは永遠の課題だと。「永遠の課題」ってあんま好きじゃないけど、ずっと向き合いつづけなきゃいけない問題だと思うのと、でも、やっぱ社員と会社ってひとつだから、「アホみたいに給料上げろって言って、利益出なかったらどうするんや!」「そんなの関係ない!」って子は、もう辞めてもらうしかないだろうし。

たとえばスキルもないのに「息子を医者にしたいから、このぐらい所得がいる」って言ったら、「うちじゃ無理ね」って話も出てくるかもしれないし。まあ、いろんな価値観とか働き方とかがいまはあるわけで、そうなると、「9時5時でこのぐらい働きたいんです。それで旦那の収入も合わせたら、べつに問題ないんです」っていう人もいるわけじゃない?

まあ、お金いらないから安く使うとか、お金いるから高く払うとかじゃないけど(笑)。そこで対話していくっていうことなんじゃないかなと…ふんわり思って。俺もなんか不安だよね。いま一緒にやってくれてるメンバーたちが、べつに生活はできるんだろうけど、どうしていけば……。「いくつまで働くんだろう」とかさ、「俺が死んだらどうなるんだろう」とかさ、いろいろ考えていくと、それは今やれてないから、やらなきゃと思ってるというか、思いついたのが最近なんだけどさ(笑)

でっかい会社だとむずかしいのかもしれないけど、特に中小企業で数十人でやってるんだったら、なんとなくそれは共有できるし。「じゃあ、足んないなら副業したら?」とかさ。スキルがべつにあるわけじゃん。

うん。だから、対立しなければっていうか、まあ、お金を会社に残すか社員に払うかという意味では利益相反するけど、「利益をお互いで出せば、お互いいいわけで」みたいな発想で、分離せずやっていくっていうのがいちばん。まあ、これ、きれい事かもしれないけど、小さい会社ならできるんじゃないかなと思うんだけどね。

きれい事どころか、逆にもっとむずかしい話をしてくださってますよね。普通だったら会社のルールで決めたものに対して「これで」っていう、それこそ給与テーブルみたいなものをボンって出して、こっちの合理性のもとでやるっていうことじゃなくて、いったん個人個人の、少人数だったりするからこその、「ひとりひとりがどうなりたいんだ」というものに対して対話していって、どう作っていくのかという、つくる前段階の話をいましてくださってるじゃないですか。

だって、わかるわけじゃん、だいだいの自分の原資を。まあ、間接部門とかはむずかしいかもしれないけど。そうだとしたらいくら売らなきゃいけないし、売れないなら別のをなにかやんなきゃいけないしとかね。

なるほどね。原資はわかるじゃないですか。まず、この方の質問が、大久保先生、まさにその前提となる考え方のところから来てくださってますけど、そんなのがあったなかで、いわゆる、ある程度の労働分配率がどうで、原資がどのぐらいで、みたいなとこの考え方って業種業界とかによって結構あいまいだったりするし。任天堂がなんでしたっけ、5%とかでしたっけ、「それ、どうやってやんだよ」みたいな世界もあったり、このへんはどうなんですか?

それと働いてる社員の経営計画とが合致しないと、本来は絶対ひずみが生まれるから。だから、わかりやすくいえばMAセンターみたいな、労働分配率はよくわかんないけど、案外高所得でやって、バーンってやって「金欲しいやつ集めろ!」っていったら、同じ価値観の人が集まるからさ。

その労働分配率は、経営計画をつくっていくなかで「何%に抑えないと、利益がこれぐらい残せない」とか、これも基準を聞きたがるけど、それは経営者のなかで決めろよって思ってて。そんなの人に聞く問題じゃねーよ、みたいな。

そう。だって、経営の仕方ってさまざまだし、利益出さないで、みんなで分配するっていう考え方もあるだろうし、きちんと積み上げて投資するために残さなきゃいけないとか、それぞれだと思うんで。原先生が「公益資本主義」っておっしゃるなかで分配率を言わないもんね。

言わない言わない。まあ、ほんとは言ったほうがわかりやすいから熱狂を生むんだと思うんだよね。例えば「○○が10%だ」みたいに言ったら「目指すぞ!」みたいになるけど、「そんなの経営者なんですから、ご自身で決めてください」ってはっきりは言わないけど、そうなんじゃないかなと。

金だけの話してるけど、この価値観というか会社の目的のためにやるんだったら「……があって、その報酬がこうで、こうでいいよね」みたいな。それは高いとか安いとかじゃなくて。だから、やっぱ方向性プラス、現実のキャッシュの問題もできるといいのかなとは、思ってはいるけど。

たしかにね。労働分配率をいくらにすべきかの前に、いまおっしゃってた、たとえば会社の目的に対して「じゃあどのぐらい利益残したいんだとすると、労働分配率をこうしなきゃいけないから、そのためにはどう稼ぐか」みたいな話もあるわけですよね。

そうね。それを当てはめてやってったら、たぶん、ずっと給料上がりつづけて、みたいな。それで収益上がんなかったら、どんどん黒字が減ってって、みたいなことで。結果、途中で辞めたりして新しい子が入るから……でも、それも結構行き当たりばったりだよね、みたいなとこもあるわけじゃん?(笑)。だから、なるべくなら長く働いてもらったほうがいいんだろうし、足りなきゃ副業だったり、逆にいったら、もっと稼げることがあって、でも、こっちの仕事を手伝いたいなら業務委託でやってもらうとかだってあるだろうし、まあ、いろんなパターンがあるんで、なんか、いろいろ考えたらいいんじゃないの?っていう、すげーいい加減な(笑)