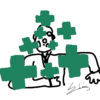この対談について
株式会社ワイキューブの創業・倒産・自己破産を経て「私、社長ではなくなりました」を著した安田佳生と、岐阜県美濃加茂エリアで老舗の葬祭会社を経営し、60歳で経営から退くことを決めている鈴木哲馬。「イケイケどんどん」から卒業した二人が語る、これからの心地よい生き方。
第123回 ご葬儀の「潜在ニーズ」を引き出すのは、担当者の腕次第?
第123回 ご葬儀の「潜在ニーズ」を引き出すのは、担当者の腕次第?

先日ニュースで「ヘビメタが演奏できる葬儀場」があるって見たんですけど、鈴木さんご存知でした?

そう。故人の方がフォークダンスのサークルに入っていたそうで。お仲間が集まって故人の前で踊られたんですよ。そういう何か特別な理由があるのであれば、ヘビメタもやっていいんじゃないかな。きっとそれはご遺族の方にとっても癒やしになると思いますから。

なんか日本って昔から「死=タブー」とされてきて、葬儀もしんみりしていて暗いイメージが強いじゃないですか。でもきっと中には「もっと明るく、楽しくやりたい」と思っている人もいると思うんですよね。そこに「潜在ニーズ」があるんじゃないかなと。

ご葬儀の担当者が「故人様のご趣味は何でした?」ってじっくりヒアリングしていった結果ですね。そういう意味では担当者の力量がめちゃくちゃ大きいんです。

なるほどなぁ。確かに遺族としては「葬儀は厳かにやるのが当たり前」と思っているから、なかなか「みんなでフォークダンスをしたい」という発想にはならないですよね。「ちょっと変わったお葬式」をすることで、周りの人から白い目で見られる…と懸念される人もいそうだし。

ああ、なるほど。でも最近は「家族葬」が増えているので、昔に比べたらかなり自由度が高くなってきたように感じます。

そういうことです。告別式は宗教者がいない場なので、自由度が高いと言えます。とはいえそれも担当者から「ご葬儀の後に踊られてはどうですか?」といったようなご案内をしない限り、ご遺族は「そんなことできるわけもない」と思われていますけどね。

なるほどなぁ。『のうひ葬祭』さんで、故人の趣味嗜好に合わせた「オリジナル告別式」を商品化したらどうでしょう? ご遺族の方たちにとって満足度が高いサービスになると思いますよ。
対談している二人
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。