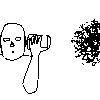庭師でもない。外構屋でもない。京都の老舗での修業を経て、現在は「家に着せる衣服の仕立屋さん(ガーメントデザイナー)」として活動する中島さん。そんな中島さんに「造園とガーメントの違い」「劣化する庭と成長する庭」「庭づくりにおすすめの石材・花・木」「そもそもなぜ庭が必要なのか」といった幅広い話をお聞きしていきます。
第87回 高くても選ばれる庭の作り方

最近はAIの影響でホワイトカラーの仕事が減る一方で、現場の人手不足がどんどん深刻になってますよね。人件費が上がる一方で、外食チェーンではロボット導入も本格化している。

でもそれって、ある意味で「技術を適正価格で売るチャンス」だとも思うんです。コストが上がったから仕方なく値段も上げる、ではなくて、「この技術はそもそもこれだけの価値があるんだ」という価格設定をしてもいいように思うんですけど。

でもdirectnagomiさんの規模であれば、「庭にこだわりたい層」だけに絞っても十分やっていけると思うんですよ。むしろ大事なのは、安さ競争に巻き込まれないことじゃないかと。

ビジネスモデルを変えて、本気で時間とお金をかける人だけを相手にすればいいと思うんです。私も実際そうしていて、100人いたらそのうち3人に刺さるくらいでいいと思っています。むしろそれくらいしか対応できないので。

まったく新しいサービスとして出すことが大事なんだと思いますよ。「これまでの庭とは違う、新しいグレードの庭が登場しました」という。既存の商品とは区別して、新しい価格で別商品として展開する。これが自然な値上げの方法です。

それでいうと、「管理」という言葉はちょっともったいないですね。どうしてもエアコン掃除のような定期点検っぽいイメージになりやすいので。それよりも「手入れ」とか「育てるお手伝い」の方が価値が伝わる気がします。
対談している二人
中島 秀章(なかしま ひであき)
direct nagomi 株式会社 代表取締役
高校卒業後、庭師を目指し庭の歴史の深い京都(株)植芳造園に入社(1996年)。3年後茨城支店へ転勤。2002・2003年、「茨城社長TVチャンピオン」にガーデニング王2連覇のアシスタントとして出場。2003年会社下請けとして独立。2011年に岐阜に戻り2022年direct nagomi(株)設立。現在に至る。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。