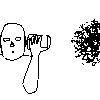人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第72回 「長く生きる」よりも大切なこと

安田さんと一度、「死生観」についてじっくり話してみたかったんです。以前「60歳を過ぎたら病名はいらない」と仰っていたじゃないですか。あの考え方に、私も共感しているところがあって。

なるほど。前回の話にも通じますが、私たちは目の前にある現実を、どこかで見ないようにしている気がするんですよね。「死」というテーマもその一つで。

わかります。病気をして余命宣告されたときも、天地がひっくり返ったような衝撃を受ける人が多いじゃないですか。思っていたより短くて驚くってことなんでしょうが、例えば50歳の人なら「余命50年以内」だろうことは最初からわかっていたわけで。

仰るとおりですよね。20代でそれを意識するのは難しいかもしれないけど、50歳を超えたら「死を前提にどう生きるか」というスタンスで考えるべきです。でもそういう話をすると「またまた」なんて茶化されることが多くて(笑)。

死生観には正解がないからこそ、自分なりの答えを考え続けることが大事で。先ほど余命宣告の話をしましたけど、そこでパニックになってしまう人も多い一方で、覚悟を決めてすごく立派な生き方をされる方もいるじゃないですか。その違いってなんなんでしょうね。

やっぱり「死をどう受け止めるか」という心の準備ができているかどうかじゃないでしょうかね。例えば日本では癌で亡くなる人が一番多いと言われてますけど、高齢者ならそれはもう老衰と呼んでいいんじゃないかと思うんですよ。

そうなんですよ。そもそも病名って、診断した医者がつけるものじゃないですか。病名がつかずに老衰で亡くなるケースも、もっとあっていいと思う。だからこの際「何歳以降は全部老衰ということにする」と自分で決めておいてもいいくらいじゃないかと。

うーむ、それって本当に恐ろしいことですね。言わば「死ぬ権利」を奪ってしまうわけですから。本来なら自分自身の最期についてもっと考えたり選択したりできるはずなのに、それすら許されない。せめて「死について普通に話せる空気」は作っていかないといけないと思いますよ。

同感です。ただそれでいうと、先ほどの話にもあったように、もともとはそういう文化の国のはずなんですけどね。武士道における切腹とか、あるいは戦時中の特攻とか、日本人は昔から死について独自の感覚を持っていたはずで。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。