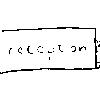人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第88回 人間の「欲の衰退」がもたらす未来のカタチ

今日はぜひ安田さんと話してみたいテーマがあるんです。以前、安田さんが仰っていた「国家や国境があるから争いが生まれる」というお話にすごく触発されまして。

そうなんですよね。歴史を振り返れば、土地を「所有」するという概念を持たなかったネイティブアメリカンやアボリジナルのような人々は、所有欲に駆られた人々によって蹂躙されてしまったわけですし。

確かにそのまま所有という概念のない時代が続いていたら、今のように国防にお金をかけることもなかったかもしれません。でもその代わりに、ここまで科学は発達していないだろうし、あまり刺激のない世界だったかもしれない。

ええ。もうしょうがないというか、巻き戻せない歴史なんですよね。その結果、良かれ悪しかれ国境警備が必要な世界になっている。今もし日本からアメリカの軍隊がいなくなって、完全に国境を放棄したら、大変なことになりますから。

そうそう。だからアボリジニのような崇高な価値観に戻るというよりは、もっとシンプルに、人間が「堕落」した結果、国境が意味をなさなくなるんじゃないかと。頑張って高い家や車を手に入れたいとか、国のために何かをしたいとか、そういう熱い欲がどんどん冷めていった先に、そういう未来があるんじゃないかと思うんです。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。