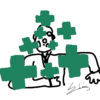この対談について
庭師でもない。外構屋でもない。京都の老舗での修業を経て、現在は「家に着せる衣服の仕立屋さん(ガーメントデザイナー)」として活動する中島さん。そんな中島さんに「造園とガーメントの違い」「劣化する庭と成長する庭」「庭づくりにおすすめの石材・花・木」「そもそもなぜ庭が必要なのか」といった幅広い話をお聞きしていきます。
 安田
安田
direct nagomiさんではお家の庭を作られることが多いと思うんですが、「小学校や中学校の校庭を作ってほしい」というような依頼もあるんですか?
 中島
中島
ああ、学校はまだありませんが、幼稚園の園庭は以前勤めていた造園会社で作らせていただいたことがあります。小川のような水遊びできる場所を作りましたね。パチャパチャと遊べるくらいの浅いものですが、危なくないように丸い玉石を張って。
 安田
安田
へぇ、小川のある園庭ですか。いつでも水遊びができるわけですね。そういう場合、水源はどこから持って来るんですか?
 中島
中島
その幼稚園には井戸があったので、ポンプで汲み上げて循環させるようにしました。水が汚くならないように濾過するようにして。
 安田
安田
そんなことまでできるんですね! ちなみに、学校となるともっと広い庭になりますけど、「中島さんにお任せで!」となったらどんな校庭にしたいですか?
 中島
中島
そうですね……例えば角の一部を使って、「自然と人が集まる場所」を作りたいです。「ゆっくり読書ができるような空間」とか。
 安田
安田
いいですねぇ。「読書ができる校庭」ですか。校庭というと塀に囲まれている印象があるんですが、中島さん流だとあまり目隠ししすぎてしまうのもよくないわけですよね。
 中島
中島
そうですね。部分的には塀も必要でしょうけど、人通りの少ないところは目隠しで少し木を植える程度にしたいですね。
 安田
安田
私もそのくらいがいいと思います。以前旅行先で見た沖縄の竹富島の小学校は、塀も何もなくて。広い野原のようですごく素敵でした。防犯ももちろん大事ですけど、情操教育も必要ですからね。
 中島
中島
ええ、僕もそう思います。情操教育ということでいうと、大きな木を植えるのもいいですよね。例えば欅は15m以上になるので、広い敷地の中でも存在感を出せます。他には桜なんかもおすすめです。
 安田
安田
 中島
中島
そうですね。そこまで大きくしたくない、ということであれば、6〜7mの大きさで止まる木もいいかもしれません。雑木林のような雰囲気にして。
 安田
安田
ああ、なるほど。どんな木を植えるか考えるだけでも楽しそうです。そういえば私が小学生の頃は子どもが多くて、校舎に入りきらないからと、どんどん増築していたんです。そのために立派な木を切ってしまったりしていて。仕方ないとはいえ、今思うともったいないなぁと。
 中島
中島
昔は子どもが多かったですからね。今はむしろ廃校が増えていますけど。
 安田
安田
そうそう。だから使わなくなった校舎は間引いてしまって、どんどん木を植えていくのもいいんじゃないかなと思います。
 中島
中島
ああ、いいですね。季節を感じる木を植えれば情操教育にもつながるでしょうし。
 安田
安田
そうですよね。都内でも昔ながらの古い校舎を残している学校があるんですが、雰囲気があってすごく素敵なんですよ。でもなかなかそういうところは少ないんですよね。
 中島
中島
確かに今は、校舎は無機質なコンクリート造りで、校庭はただグラウンドがあるだけというところが多いですよね。
 安田
安田
そうなんですよ。そんなところで過ごして情緒が育つのかなぁと心配になります。最近は「夕焼けを見たことがない」という子どもが増えているとも聞きますし。
 中島
中島
そうなんですか! えっ……夕焼けってまだありますよね?
 安田
安田
もちろんです(笑)。でも、それを楽しんだり愛でたりする環境じゃないということなんでしょうね。お母さんが「夕焼けがきれいだね」って子どもに言うから、その子に「夕焼けってきれいなんだ」っていう情緒が生まれるわけで。
 中島
中島
なるほどなぁ。せっかく四季のある国に生まれているのに、もったいない気がしますね。
 安田
安田
仰るとおりです。和歌や俳句にも季語を使いますし、四季を感じる心ってすごく大事だと思うんですよ。それが学校をはじめとして無機質な建物が増えたことで、感性が乏しい大人を量産してしまっているんじゃないかと。
 中島
中島
せめて学校の校庭だけでも、もっと四季が感じられるようにしていけたらいいですね。
 安田
安田
ええ、本当に。もし自分の子どもが通う学校の校庭を、中島さんが作るとしたら素敵だなぁ。
対談している二人

中島 秀章(なかしま ひであき)
direct nagomi 株式会社 代表取締役
Facebook
高校卒業後、庭師を目指し庭の歴史の深い京都(株)植芳造園に入社(1996年)。3年後茨城支店へ転勤。2002・2003年、「茨城社長TVチャンピオン」にガーデニング王2連覇のアシスタントとして出場。2003年会社下請けとして独立。2011年に岐阜に戻り2022年direct nagomi(株)設立。現在に至る。