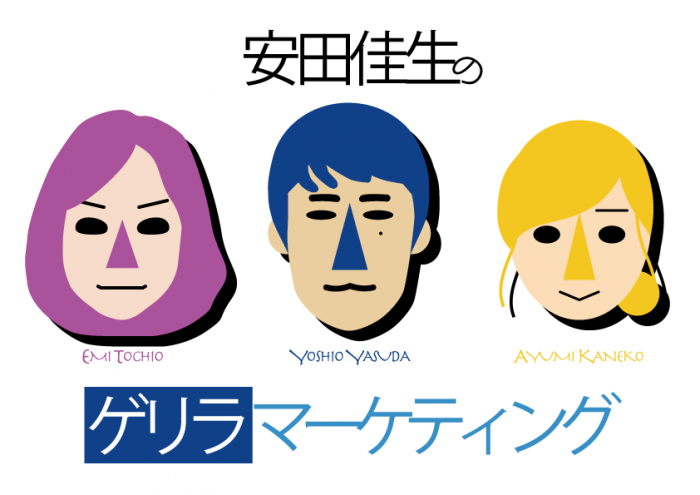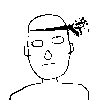金子
金子(笑)。はーい、では本日のご質問です。美術作家・40代の方からご質問いただいてます。はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。以前の放送で、「小学校がいまの社会に求められていることとずいぶんズレてきてしまった」とおっしゃられ、栃尾さんも強く共感されているのを聴いて、それがとても気になっています。私はいずれ小学校向けの造形教室を開こうかと考えているのですが、美術や造形に限らず、学校では習えない、いろいろなことを試せたり遊べたりする場にしたいと考えています。改めて、学校と社会がどうズレてきてしまったのか、また、学校外ではどんなことが学べればよいのか、何かお考えやアイデアがあればお願いいたします。ということです。

そうですねぇ、えーと……難しい。最近思ったのは、教育って「強制する」みたいな前提になっている、小学校とか中学校、公立のところは特にですね。それが結構問題なのかなって最近は思ってきてまして、造形とか美術教室も、「こういうふうに描きましょう」って先生が教えちゃうケースがあるんですよね、「太陽をここに描きます」とか、「人の顔はここに描きます」とか。で、そういうクラスの絵を見ると、全員があまりにも似てるんですよ。まあまあ上手だけど全員が似ていて、結構気持ち悪いみたいな状況で。「自由に描きなさい」って言う人は、子どもが自由気ままに描いてるから、クオリティもバラバラだけど個性あふれてますよね。そういうほうが長い目で見て、あと、全体的に見て伸びると私は思うので、そういうことが学校に足りないのかなと。

僕は最近、個人の方のフリーランス化の相談とかをよく受けるんで、なんていうんでしょう、「どういう商売したらいいか」みたいなことを考えるときに、小学生時代からの教育のクセがついちゃってるなってよく感じるのは、学校の中で教えることとか評価することって、学科が5つ6つしかないじゃないですか。

で、小学生から教える「役に立つ」は、「これを覚えておけば将来仕事ができて、お金稼ぐのに苦労しませんよ」っていうことだと思うんですけれども、つまり「いい会社に入れるよ」とか、そういうことだと思うんですけど、そのスタート時点があまりに偏ってるんで、学校で習うこと以外はお金に直結しないっていうか、仕事にならないっていうふうに思ってる人が多いんですよ。

学校で一生懸命勉強する以外、たとえば学校だったら音楽とか体育とかもありますけど、運動とか音楽で仕事して稼ごうと思ったら突出して能力が高くないといけないわけなんで、それ以外の人はいわゆる5教科で頑張るしかないよっていう、そういうことを植え付けられてる気がしまして。

実際にはそれ以外の、その他のことで将来的に自分の職業にするっていうことはいくらでもできるんですけれども、なんていうか、本当にいま、「すでに世の中でお金になっていること以外は仕事じゃない」っていうふうに思い込んでる方が多くて、それは学校教育の弊害だなあとすごく感じますね。

はい。ただ、結構いまの子どもって手を動かすとか、そういうのが少ないと思うので、そういう意味で、やっぱり造形教室っていうのはすごいチャンスだと思いますね。子どもってそういう抽象的なものを取り入れるよりも、たとえば「砂場で砂を触ってわかる」みたいなことがすごい多いので、そういうのは、すぐにはわからないけど、めちゃくちゃその子の力になるんじゃないかなとは思ってます。
*本ぺージは、2020年11月4日、ポッドキャスト「安田佳生のゲリラマーケティング」において配信された内容です。音声はこちらから
*Spotify、Google Podcasts、Apple Podcast、iTunes、Amazon Musicでも配信中!
ポッドキャスト番組「安田佳生のゲリラマーケティング」は毎週水曜日配信中。