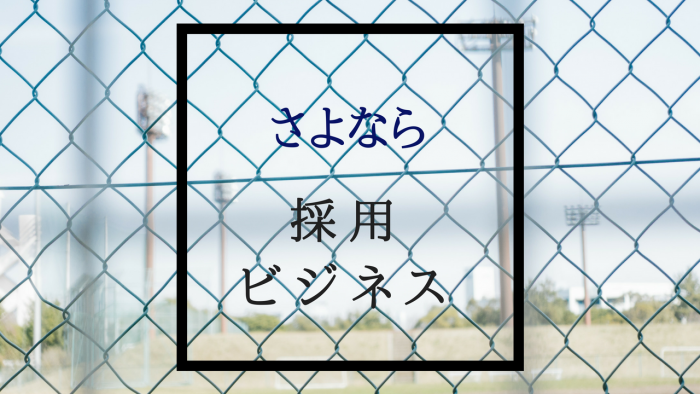7年前に採用ビジネスやめた安田佳生と、今年に入って採用ビジネスをやめた石塚毅による対談。なぜ二人は採用ビジネスにサヨナラしたのか。今後、採用ビジネスはどのように変化していくのか。採用を離れた人間だけが語れる、採用ビジネスの未来。
前回のおさらい ①求人広告型と成果報酬型の採用が今の時代に合わない理由、②ハローワークの現状 第2回「ハローワークこそがブルーオーシャン」

いわゆる登録型と呼ばれるビジネスモデルがナビだと思います。釣り堀に求職者や転職予定者を集め、そこに対して釣竿を1本出させることにいくら課金させるのか。これが今にいたるビジネスモデルですよね。釣り堀にどれだけいい魚が集まっているかどうか。日本は釣り堀型がずっと強かったですから。

求人情報の認知のされ方が、かつてよりも安く、ほとんど無料で認知できるようになった。そのきっかけについてIndeedはものすごく功績がありますよ。日本の採用史を私がまとめるとしたら、Indeedの登場に1~2ページは割り当てますね。

もちろん、スマートフォンの普及が前提にありますよ。でも低コストでいろんな人に求人認知をしてもらえることを加速したという意味では、功績はすごく認めます。ただ仰る通りで「転職したいからIndeed」っていう風には、あまりなっていないですね。

ですよね。スマホで検索したら結果的にIndeedの求人情報が出てくると。つまり凄いのはIndeedじゃなくてGoogleなんじゃないかと。だとしたら、求人も集客も根っこは同じはず。Googleに広告費を払っている人もいますけど、払っていなくても、自然に検索されてお客さんを連れてきてもらえるお店もありますよね。

近いことはもう起こっていますね。特にハローワークをうまく使うと、そういうことは頻繁に起きます。ハローワークは公的なサイトなので、情報は上位にあげますというのはIndeedのルールですし、Googleでも結構上位にあがるんです。

そうなんですか!でもIndeedってそんなに凄いんですかね。Indeedの価値はグーグル検索の上位に出ることじゃないですか。もしGoogleがIndeedの情報を上位表示しなかったら、Indeedの効果は激減する。つまり、結局はGoogleが凄いんじゃないの、という気がするんですよ。

確かにそうです。ただ、もうひとつ付け加えると、Indeedの功績として認めたいのは、テキスト情報のみの求人情報を根付かせたこと。ナビは、なるべく画像を沢山載せたほうが、求職者のウケがいい。掲載ページが多くなればなるほど、単価が高いという理屈じゃないですか。ところが、文字情報だけでも、今の求職者は情報を取ってしまうんですよ。文字情報だけの求人認知を日本に短期間で根付かせた功績ってあるなと。

ほんと、その通りなんです。人モノ金って言いますけど、お金や商品に比べると、人に関するリテラシーは低すぎます。決算書を適当に作る会社はありませんけど、採用ページや求人票の作り方なんて、かなりいい加減ですから。

労働局から人材に関しての報告書を求められることなんて一切ないんですよ。何人採用して、定着しましたか、っていうことも法律で何も報告義務がない。報告義務がないので国家資格者がチェックする機能もない。だから中小企業は特にビックリするくらい、いい加減なのが実情です。

採用の改善って、当たり前のことを当たり前にやれば、割とそれだけで人が採れるんですよ。だから私はまず、ハローワーク対策をしっかりやろうと言っているわけです。お金を出す前に、まずは求人票をしっかりと作りましょう、と。
石塚毅
(いしづか たけし)
1970年生まれ、新潟県出身。前職のリクルート時代は2008年度の年間MVP受賞をはじめ表彰多数。キャリア21年。
のべ6,000社2万件以上の求人担当実績を持つ求人のプロフェッショナル。
安田佳生
(やすだ よしお)
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。