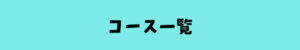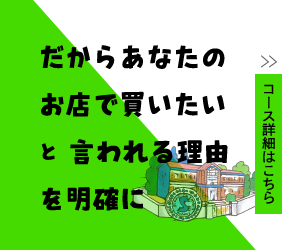大人の入口というコンセプト
– – – 目次 – – –
形に残る「お店」を持ちたい

安田
ワイキューブの新卒社員だった辻本さんと、こうやって対談する日が来るとは。

辻本
よろしくお願いします。

安田
すごい経営者になって。とても感慨深いものがあります。

辻本
ありがとうございます。

安田
ワイキューブとは畑違いの、飲食業での起業ですよね。

辻本
はい。当時は止められました(笑)

安田
すみませんでした(笑)飲食って経験がないとすごく難しいだろうと思って。

辻本
想像してたより難しかったですね。

安田
まず材料の仕入れや管理があり、社員や顧客のマネジメントもあり、料理というクリエイティブな部分も必要で。全部バランスよくできなきゃいけない。

辻本
そうですね。

安田
バランスが良ければ流行るわけでもないし。

辻本
そうなんですよ。

安田
なぜ飲食をやろうと思ったんですか。

辻本
もともとワイキューブの仕事は無形商材だったじゃないですか。ノウハウを提供するという。

安田
そうですね。

辻本
人生を逆算して考えたときに、「形に残るものが欲しいなあ」というのがあって。

安田
へえ〜

辻本
父親が建築をやっていた影響かもしれないです。「自分の店」という、形に残る仕事をどうしてもやりたくて。とくにお酒を飲むのが好きだったので飲食業にしました。

安田
「自分のお店を持ってる」ってかっこいいですよね。

辻本
そういうイメージでした。

安田
しかも人気店だったら、さぞかっこいいと思います。壁にぶつかったりとかはなかったですか?

辻本
いやあ、もうほぼほぼ、ずっと壁なので(笑)

安田
最初はどんな壁だったんですか?

辻本
まずは「告知しているのにお客さんがまったく来ない」という壁ですね。毎日駅前に行ってチラシ配って。でも立地も悪かったですし、なかなか歩いて来てもらえない。

安田
いまから20年ぐらい前ですよね。

辻本
ちょうど20年前ですね。
スマホなき時代のチラシ戦略

安田
飲食店に行くのに、まだスマホなんて使わない頃。

辻本
まだスマホではなくてガラケー。Webサイトはつくりましたけど、当時はまだGoogleマップもないですし。どうしても紙ベースでの告知がメインでした。

安田
人通りがないと新規店舗は成り立たない時代でしたね。

辻本
ただ表通りは家賃も高くて。そんな余裕はなかったです。

安田
やる前から、集客の厳しさは予想できてたんですか。

辻本
厳しいのは覚悟してました。格安で借りられる場所でやるしかなかったので。

安田
ですよね。

辻本
なので、とにかく毎日チラシを配りまくって。

安田
チラシで呼び込むには、なにか目玉商品が必要だと思うんですけど。何をフックに集客をかけていたんですか?

辻本
当時はそれが分かっていなくて。配っていたチラシも本当にピント外れで。

安田
どんなチラシだったんですか。

辻本
「仲間4人で始めました」みたいなチラシで。それって、お客さんに何のメリットもないじゃないですか。

安田
そうですね。

辻本
自己満足のチラシをつくって配っていただけ。お客さん側からのメリットというものはまったく書いていないんですよ。

安田
「生ビール半額」とかはやらなかったんですか?

辻本
「生ビール290円」というのはチラシに書いてました。

安田
それは売りになるじゃないですか。

辻本
いや、それで知らない店に入る人なんていなかったです。

安田
ビールが安いのは魅力的ですけどね。

辻本
わざわざ遠くまで歩いていって、聞いたことないお店に入るわけですよ。「生ビールが安い」という程度では“てんびん”が釣り合っていない。

安田
何分ぐらい歩くんですか?

辻本
駅前から徒歩8分ですね。

安田
けっこう微妙な距離ですね。

辻本
駅と駅のちょうど真ん中でしたから。

安田
ということは、狙いはその近所に住んでいる人ですか。

辻本
いや狙いは学生だったんです。店を出した街に大学が3つあって。僕らとしては、居酒屋しか知らない若い子たちに、バーで過ごす時間の価値を提供したかった。
コンセプトと異なる商品サービス?

安田
いわゆるオーセンティックなBARですか?

辻本
若い人たちにとっての「バーの“入口”」みたいなコンセプトでした。

安田
ということはお酒がメイン?つまりご飯を食べてから2軒目に行くところ。

辻本
いや、それがですね。両方取りたかったので、「お酒はバー並みにあるけど、ご飯もある」みたいな。

安田
両方を狙ったわけですか。

辻本
そうなんです。これは自分のミスでした。

安田
両方狙ったのは間違いだったと。

辻本
いえ。事業計画書にコンセプトを書かなかったことが。そのせいで軸がブレて、価格を売りにする店になってしまいました。

安田
コンセプトというのは?

辻本
お店をバーの入口として経験してもらって、「その人たちの今後の人生が豊かになっていく」というコンセプト。

安田
「食べ物があるバー」というのはコンセプト的に問題なかったわけですか。

辻本
そこは狙っていた部分なので。

安田
居酒屋しか行ったことがない学生さんに、「バーに行くにはちょっと敷居が高いから、その中間ぐらいのお店をつくってあげよう」というイメージですか。

辻本
そうです。

安田
そのコンセプトを忘れちゃって、安売りに走ったと。

辻本
そうなんですよ。

安田
いまから考えて、そのコンセプト自体は間違っていなかったですか。

辻本
軌道に乗ったあとは繁盛したので、間違っていなかったと思ってます。

安田
自分が社会人になってバーを経験して、「あ、こんな世界があったのか。学生にもこういうのを教えてあげたいな」みたいな。そこがスタートなわけですね。

辻本
まさにそのとおりですね。社会人になってバーに連れていってもらって。

安田
よくBARに行きましたよね。

辻本
はい。同期と一緒にバーへ行ったりすると、すごく前向きな話になるんですよ。ガヤガヤした居酒屋へ行っちゃうと、どうしても愚痴っぽくなっちゃうので。

安田
バーって大人の世界ですからね。

辻本
そういう大人の世界を垣間見て「これはいけるかな」と。

安田
なぜ普通のバーにしなかったんですか。

辻本
居酒屋とバーの段差ってあまりに激しいので。

安田
確かに。

辻本
バーを知らないまま年を取っていっちゃう人は多いんじゃないかなと。そこをつなぐ階段みたいな店を若い人たちにつくってみたかったんです。