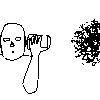このコラムについて
経営者諸氏、近頃、映画を観ていますか?なになに、忙しくてそれどころじゃない?おやおや、それはいけませんね。ならば、おひとつ、コラムでも。挑戦と挫折、成功と失敗、希望と絶望、金とSEX、友情と裏切り…。映画のなかでいくたびも描かれ、ビジネスの世界にも通ずるテーマを取り上げてご紹介します。著者は、元経営者で、現在は芸術系専門学校にて映像クラスの講師をつとめる映画人。公開は、毎週木曜日21時。夜のひとときを、読むロードショーでお愉しみください。
『ドライブ・マイ・カー』に見るお役所仕事の素晴らしさ。
たまには新しい映画の話をしたい。濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹原作の作品で、2021年のコロナ禍の中で公開されヒットを記録した。カンヌ映画祭で脚本賞も受賞し、世界的な評価も高い作品である。
演劇の演出も手がける役者の家福(西島秀俊)は、ドラマの脚本家である音(霧島れいか)とたがいの仕事を尊重し合い、夫婦として暮らしている。しかし、若い頃に幼い子どもを亡くしてから、その関係の奥底にはなにか冷たいものが流れている。音はドラマの撮影の度に若い役者と肉体関係を持ち、家福はそのことを密かに知っている。それでも、この夫婦関係を壊すつもりは二人にはない。ないからこそ、映画はスリリングな緊張感を観客に伝えながら進んでいく。
この映画には様々な見せ場がある。主人公、家福と彼の車のドライバーを務めるみさき(三浦透子)の徐々に理解し合い共鳴し合う関係。妻の浮気相手でありながら、「僕は空っぽなんです」と告白し、家福が知らなかった妻の物語を語り始める高槻(岡田将生)の粗暴な繊細さ。また、様々な言語が飛び交う家福演出の『ワーニャ伯父さん』の練習風景で、言葉から抑揚がそぎ落とされ、言葉本来がもつ力が呼び起こされていく様子。見どころが山のようにあって、約3時間の上映時間がとても短く感じられる。
そんな中で、私がもっとも引っかかったというか、なるほどと思ったのは、演出家である家福を招聘して開かれる演劇祭の関係者の二人の存在である。彼らはどうやら市役所か県庁の人間、もしくは非営利団体の人たちのように見える。毎年開かれる広島の演劇祭を仕切っている人たちのようで、韓国人の男性と日本人の女性らしい。どちらも年齢は三十代の半ばから四十代と言ったところだろうか。
この二人がきちんと演出家の家福の仕事に寄り添いながらも、ルールとして譲れないところは決して譲らないという極めてお役所仕事的な仕事ぶりを見せつける。「演劇祭の間、ご自身で車を運転していただくことはできないんです」と困惑する家福に半ば強引にドライバーを付ける。役者が事件を起こすと「中止にするか、家福さんが出演するかのどちらかです」と「いま判断することですか」と怒る家福に迫る。お役所仕事と言ってしまうと、昨今のお役所の都合だけで仕事をする、仕事が出来ない人たちという印象があるかもしれないけれど、本来お役所仕事という言葉は、ダメなものはダメという融通の効かなさを伝えた物言いである。
しかし、この映画の中ではこの二人の男女のお役所仕事が主人公である家福を救う。沈着冷静を装いながらも感情に揺れる家福に、きちんとルールに従った判断を強いることで、結果、家福は落ち着いて芝居の稽古に集中することができ、演劇は無事上演されるのだ。
もしかしたら、これは会社経営でも同じなのかもしれない。感情を揺さぶるような熱い仕事をしっかりと成功させるためには、その仕事を客観的に見守る規範のようなものが必要なのかもしれない。その熱い情熱と冷ややかなまでの客観性が、経営者一人のなかに内包されている場合もあるだろうし、経営者にないどちらかを誰かが補填している場合もあるのだろう。この映画を見ているときに、そんなことをふと考えさせられたのだった。
著者について
植松 眞人(うえまつ まさと)
兵庫県生まれ。
大阪の映画学校で高林陽一、としおかたかおに師事。
宝塚、京都の撮影所で助監督を数年間。
25歳で広告の世界へ入り、広告制作会社勤務を経て、自ら広告・映像制作会社設立。25年以上に渡って経営に携わる。現在は母校ビジュアルアーツ専門学校で講師。映画監督、CMディレクターなど、多くの映像クリエーターを世に送り出す。
なら国際映画祭・学生部門『NARA-wave』選考委員。