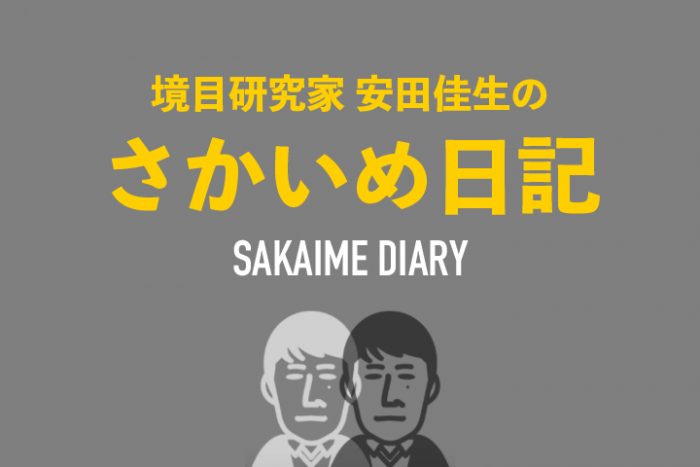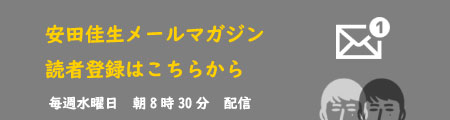誰でも一度くらいは触ったことがあるルービックキューブ。目の前にあれば子供も大人もチャレンジしたくなる。よく出来たパズルだ。バラバラになったキューブを揃えることができれば一目置かれる存在になれる。だがこのパズルを自分の頭で解いていくことは非常に困難である。普通の人にはまず出来ない。
だからその手際を見せられると「なんと頭がいい」「天才か」と思えてしまう。だがこのパズルは頭を使わなければ簡単に解けてしまうのである。手順通りにただ動かすだけ。知らない人には信じられないかもしれないが、手順さえわかっていればたった5分でバラバラになったキューブの6面が揃う。
6面が綺麗に揃えばもちろん嬉しい。だがそれはパズルを解いたと言える状況ではない。単に指示された手順通りに動かしただけなのである。知的労働にはこれと同じような罠が潜んでいる。頭を使って仕事をしているように見えて、実は単なる作業を繰り返しているだけ。これは真なる知的労働とは言えない。
ビジネスとは答えが変化し続ける世界である。ルービックキューブのように同じ手順がいつまでも通用するわけではない。ここで重要なのは自分の頭を使って答えを見つけ出す力。だがそれをちゃんと評価できる組織は稀だ。組織において評価されるのは、いかに短時間で、いかに多くのキューブを揃えたか。
手際がよく生産性が高い人は仕事ができる人に見える。あっという間に6面揃えてしまうプレイヤーのように。だが実際にその人が頭を使っているのかどうかは分からない。組織が評価すべきは自ら手順を見つけ出すことの出来る人材である。難しいのはそのプロセス(成長過程)を評価できるかどうか。
自分の頭で考える人は要領の悪い人に見える。なぜもっと効率よく成果が出せないのだと評価を下げられる。だがよく考えてみてほしい。あと一歩で手順を見つけ出せそうな人と、覚えた手順でスイスイと6面を揃える人。どちらが頭を使って仕事をしているか。どちらが将来的に大きな価値をもたらすか。
短期的な売上や利益を指標にすると自分の頭で考えなくなる。手順通りに6面を揃えるほうが楽だし評価も高いから。だがそれは単なる作業に過ぎない。あっという間に模倣され価格が下落する。独自の価値を生み出したいのなら評価すべきは自分の頭で考える人。真なる知的労働の判断を誤ってはならない。
尚、同日配信のメールマガジンでは、コラムと同じテーマで、より安田の人柄がにじみ出たエッセイ「ところで話は変わりますが…」と、
ミニコラム「本日の境目」を配信しています。安田佳生メールマガジンは、以下よりご登録ください。全て無料でご覧いただけます。
※今すぐ続きを読みたい方は、メールアドレスとコラムタイトルをお送りください。
宛先:info●brand-farmers.jp (●を@にご変更ください。)