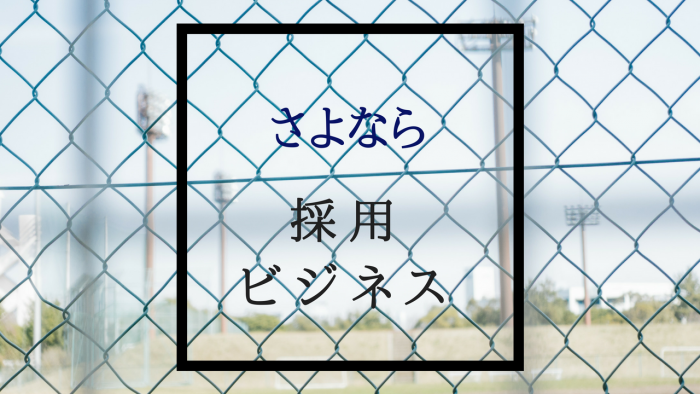7年前に採用ビジネスやめた安田佳生と、今年に入って採用ビジネスをやめた石塚毅による対談。なぜ二人は採用ビジネスにサヨナラしたのか。今後、採用ビジネスはどのように変化していくのか。採用を離れた人間だけが語れる、採用ビジネスの未来。
前回のおさらい ①リクルートがもつビッグデータ、②口コミ信頼度を確保できるか、③良い会社の作り方が分からない? 第4回「リクルートがIndeedの次に狙うもの」

取引先や取引先になるかもしれない人。その会社にものを売りたい人、あるいは買いたい人が見に来る。そういう人たちに対して会社や商品を魅力的に伝える。それがHPの役割じゃないですか。採用ページはもっと分かりやすい。だって求職者しか見ないわけですから。にも関わらず求職者目線に立っていないんですよ。その仕事につくメリット、幸せ、ベネフィットが何なのか、情報として載っていないんですよね。

採用だけに限らないですけどね。例えば先日、あるお店の壁に「お客様に感動を」という紙が貼ってありました。それを貼ってどうするの?と思っちゃいましたね。それは顧客に宣言することではなく、感じ取ってもらうべきことですから。でもそのままHPに書いてる会社多いですよね。お客様に感動を、って。

うーん、まさにその通りなんですけど。リアルな話をすると、多くの経営者が、人と企業の需給バランスや求職者の変化についていけない。人は知名度と給料を担保すれば集まるという、ぬぐいがたい感覚が根源にあるような気がしますね。

それでもなぜお金を出し続けるかというと、楽だからだと思うんです。採用業者に任せているだけでは、もはや採用はうまくいかない。どうやったら採れるかを社長が自ら考えないといけない。分かっているけど大変なんで、今までの流れに乗っかっている。

経営者ってやればやった分、形になるものに惹かれるじゃないですか。例えば、売上や利益の改善は測定もしやすい。しかしながら、人に選ばれる会社とか、人が集まる会社の測定の仕方って、簡単そうだけど難しいですよね。

多いですね。年齢に関係なく、経営者歴が長い人ほどそういう傾向を感じますね。20年超えた方って変えようと思ってもなかなか変われない。かつての人と組織の作り方に囚われ過ぎている。たまに講演やセミナーを聞いて、そうなのかなと思いつつも、興味の優先順位が低いので改善まで着手しない。ところが年齢に関係なく、経営者歴の短い方は、そのへんの反応がいい。

いままでの洋服ってSMLしかなくて、そのどれかに人間が合わせないといけなかった。それが逆転の発想で、服が人間のサイズに合わせて仕上がってくる。もしかしたら仕事もこうなるかも、と思いましたね。これまでは営業職・事務職・技術職みたいな中から選ぶのが常識だったじゃないですか。でもこれからはZOZOSUITのように、一人一人に合わせて仕事を作っていく時代なんじゃないかと。70億人いるとしたら70億種類の仕事がある。だから営業マン5人募集みたいな求人ではなく、5人募集する時には5種類の求人をつくるべきだと思います。

私もそう感じますね。リクルートも、なんとかドアなんて買収するより、スタディサプリ(公式サイトへ)を使って、小中学生の頃から勉強と仕事を繋げてほしい。こういう勉強をしてこういう結果が出る君なら、こういう仕事が向いているよ、とか。仕事のZOZOSUITみたいなものを作ってほしい。求職者目線って言いますけど、究極いうと一人一人にあわせて仕事をつくらないといけない。

大手企業さんが総合職1000人にむけて、1000個の求人広告を作れるかと言うと、そんな効率の悪いことできない。リクルートだって、そんな面倒くさいことやるより、マスでガサッと儲ける方に行くでしょう。

すごくそう思います。私が現場でやっているのも、まさにそんな仕事ですよ。求人広告をうまく作るのではなく、誰かにとってのより魅力的な仕事を作り出す。それがこれからの採用ビジネスの根幹なのかもしれません。
次回第6回へ続く・・・
石塚毅
(いしづか たけし)
1970年生まれ、新潟県出身。前職のリクルート時代は2008年度の年間MVP受賞をはじめ表彰多数。キャリア21年。
のべ6,000社2万件以上の求人担当実績を持つ求人のプロフェッショナル。
安田佳生
(やすだ よしお)
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。