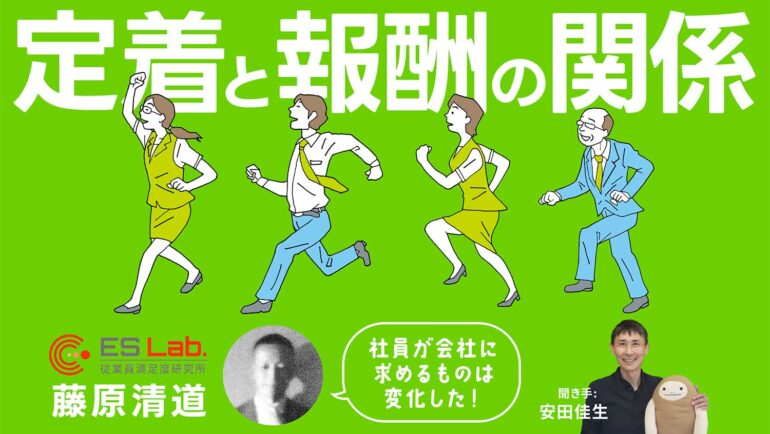人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第3回 まず「面接」から見直そう

前回は「生活レベルを上げないことで本気度を伝えた」というような話を伺いました。そしてそうやって組織改善を進める藤原さんのもとに、経営者仲間からの相談が集まってくるようになった。

そうですね。とはいえ、最初は「相談」って感じじゃなかったかな。私が従業員満足度を重視した経営をしていると知って、「そんなことに一生懸命になって意味あるの?」というように言われることも多かったです。

仰るとおりです。ただ少しずつうちの組織が良くなっていって、実際に採用でもいい人材が採れたり、定着率も上がって、かつ業績も伸びているのを見て、「ちょっとやり方教えてくれない?」となっていきまして。

理念も大事ですが、採用についてアドバイスすることが多かったですね。それこそ安田さんの書籍も読んで、自社の採用手法を変えてうまくいっていたので。

そうなんですよね。ですから伝え方は工夫していました。「いい人材を育てよう」と言っても響かないので、「利益アップのためには人材が必要で、だからこういう育て方をする必要があって、でもそもそも適性のある人材じゃないと伸びない。だから入り口の採用・選考が非常に重要なんだよ」と。

仰るとおりです。面接ってもっとロジカルにやる必要があって。いま安田さんが仰ったように、実際に現場でどういう業務を任せるのか、それにはどういう適性が必要で、どんな経験が活きるのか、そういう所まで含めて面接で確かめる必要があるわけです。

すごーく長いLPみたいな構成にして、理念とかサービスについてかなり熱っぽく語っているようなページです(笑)。10人いて10人に刺さる内容ではないけれど、マッチした1人は「ぜひ御社で働かせてくれ!」という熱量で応募してくれる、そんなイメージで。

書いてはいますが、ことさら詳しくは書いていませんね。なんというか、それって大手を振って宣言することでもないように思うんです。「うちの会社は社員をものすごく大事にしています」なんてホームページをよく見ますが、私は違和感を覚えるんですよ。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。