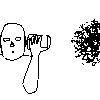人は何のために働くのか。仕事を通じてどんな満足を求めるのか。時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。その中で「従業員満足度」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道(ふじわら・せいどう)さんに、従業員満足度を上げるためのノウハウをお聞きします。
第58回 金融リテラシーの前に問うべき「人間性の成熟」

藤原さんはXでよく「金融リテラシー」について触れていますよね。確かにリテラシーは高めないといけないと思うんです。特に最近は新NISAなどで投資を始める人も増えてきましたし。…ただ、私はこの流れ自体にちょっと危機感を覚えるんですよね。

お金だけを運用して稼ぐ人がどんどん増えていったら、そのうち世の中は成り立たなくなるんじゃないかと思うんですよ。単純な話、全員が投資ばかりやるようになったら、お店や会社は誰が運営するんだっていう。

そうなんです。私自身も経営をしてきた人間として、それはよくわかる。ただね、お金って本来「交換の道具」として生まれたはずじゃないですか。物々交換の不便を解消するために作られたもので、お金自体を使って儲けることは想定されていなかったと思うんです。

そうなんです。それにね、投資や金利ビジネスっていうのは、結局「種銭」が大きい方がどうしたって有利でしょう? そうなると金融大手や大きなファンドが一人勝ちしてしまうわけですよ。それは能力の差というより、単純に扱う金額の差でしかない気がして。

仰るとおりなんです。国はある意味無制限に通貨を発行できるシステムを持っているわけで、これはもう一個人が勝てる相手では到底ない。冒頭の話で言えば、国こそが一番危険な存在とも言えてしまうのかもしれない。

うーむ。実際歴史を振り返ると、金融システムがあったからこそ大きな資金調達が可能になり、その結果大きな戦争が起こってしまったとも言えますもんね。20世紀の世界大戦などは、まさに巨額の資金を動かせたからこそ起こったわけで。

うーん、そういう話をお聞きすると、尚更この流れはよくないんだと感じてしまいます。やっぱり「お金を動かして稼ぐビジネス」は、ゼロとは言わないまでもしっかり制限した方がいいのかもしれない。あるいは「どこの国にも個人にも属さない通貨」を作って、各国が相互監視しながら低金利を維持するとか。

暗号資産はまだ「貨幣」と呼べるほど流通しているわけではないですが、確かに考え方としては近いですよね。ただ、むしろそれらが投資の対象になってしまって、「お金でお金を稼ぐ」ことに利用されている現実もあるわけじゃないですか。
対談している二人
藤原 清道(ふじわら せいどう)
従業員満足度研究所株式会社 代表
1973年京都府生まれ。旅行会社、ベンチャー企業を経て24歳で起業。2007年、自社のクレド経営を個人版にアレンジした「マイクレド」を開発、講演活動などを開始。2013年、「従業員満足度研究所」設立。「従業員満足度実践塾」や会員制メールマガジン等のサービスを展開し、企業のES(従業員満足度)向上支援を行っている。
安田 佳生(やすだ よしお)
境目研究家
1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。