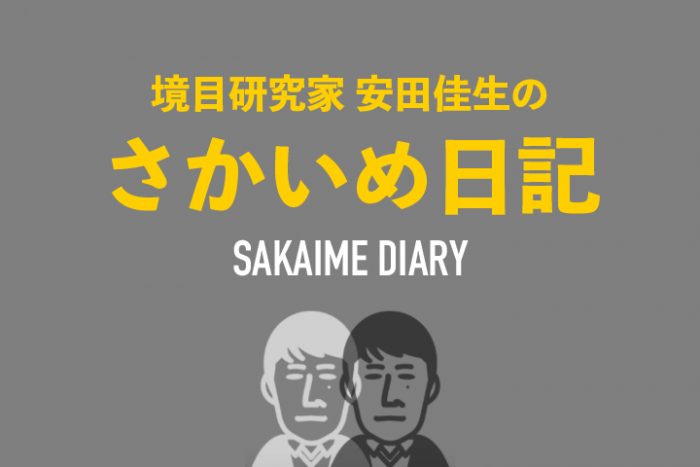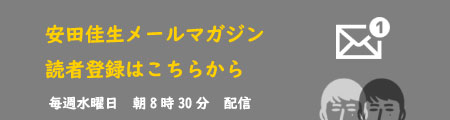老朽化した橋や道路の整備が進まない。駅前高層ビルなど大型工事のストップも相次いでいる。資材の高騰と人不足がその原因だ。決められた予算では資材を買えない。人も雇えない。これまでなら下請け業者を安く叩くことで成り立たせてこられた。しかしそれも限界。人はいないし残業もさせられない。
輸入に頼る日本にとって円安による資材高騰は厳しい。しかしそれ以上に厳しいのが人不足である。資材高騰はどこかで止まるだろうが人不足は加速する一方だ。現場の下請けを泣かせようにも、そこに人がいない。募集しても集まらない。大手ゼネコンが大儲けするという図式はもう崩壊しているのである。
この金額で受けられなければもう仕事は出さない。そう言われれば受けるしかなかった。安い賃金で人を使い残業させるしかなかった。しかし、もう受けられない。下請け企業は決して偉そうに断っているわけではない。断らざるを得ないのである。では建設予算そのものが1.5倍、2倍と上がっていくのか。
どう考えても予算には限界がある。止まった現場を動かすには業界の仕組みを変える以外に方法がない。上に行けば行くほど、元請けに近い会社ほど儲かる。ここを変える。下に行けば行くほど、現場に近い会社ほど儲かるようにする。大手ゼネコンの社員より現場で働く職人の報酬を高くしていく。
そんなこと出来るはずがないと思うだろうか。仕事を発注する側と受ける側。発注する側の方が立場は上に決まっているではないかと。だがそれは人がいた時代の話である。人がいなければ仕事は受けられない。受けられなければ売り上げが立たない。一番儲かっていた元請けから利益を下げていくしかない。
これは建設現場に限った話ではない。小売も、流通も、サービス業も人不足である。ユニクロが新卒の年収を500万円にしたように、大企業が初任給を35〜40万円にしているように、組織の下に行くほど報酬が増えていく。なぜなら現場には人が必要だから。現場に人がいないと仕事が回らないから。
元請けに近い会社ほど儲かる。組織の上に行くほど収入が増える。ヒエラルキーに比例していた待遇が人不足によって逆転する。無駄に給料が高い管理職の報酬を下げて若手に回す。無駄に利益が大きかった元請けの利益を下げて現場の人間に回す。人不足という重力によって報酬は下へ下へと降りていく。
尚、同日配信のメールマガジンでは、コラムと同じテーマで、より安田の人柄がにじみ出たエッセイ「ところで話は変わりますが…」と、
ミニコラム「本日の境目」を配信しています。安田佳生メールマガジンは、以下よりご登録ください。全て無料でご覧いただけます。
※今すぐ続きを読みたい方は、メールアドレスとコラムタイトルをお送りください。
宛先:info●brand-farmers.jp (●を@にご変更ください。)