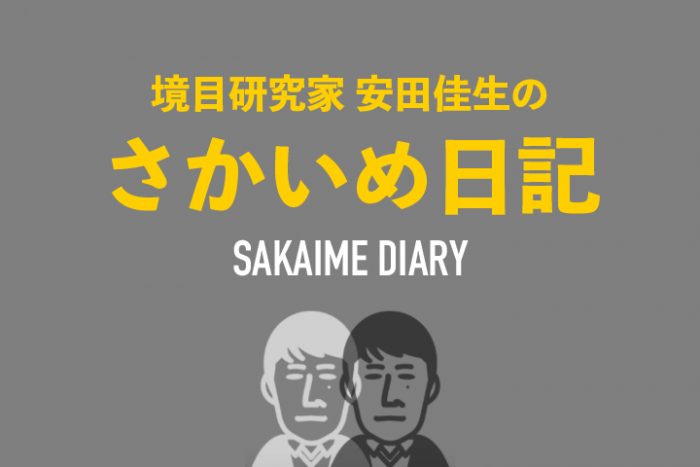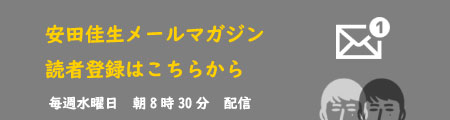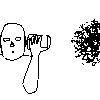大手飲食チェーンでは現場からどんどん人が消えている。まず受付に人がいない。自分でチェックインして指示された席に向かう。オーダーももちろん無人。設置されたタブレットから食べたいものを注文する。出来上がった食事はロボットが届けにくる。いずれは調理からも完全に人が消えるだろう。
これは飲食だけの話ではない。アパレルチェーンからも、建設や介護の現場からも、どんどん人が消えていく。経済効率を考えれば「人が作業する」ことは無駄でしかないのである。採用、育成、社会保険、休日休暇などに莫大なコストがかかる。人が消えれば販売価格は下がり会社の儲けは増えていく。
経済効率だけを考えれば人が調理することも接客することも無駄である。だがそれを望む人にとっては付加価値となる。あえて新品のデニムを傷つけ汚す手作業。あえて手間と時間をかけて人が行う調理。あえて不便な場所を訪れ非効率を味わう体験。経済効率における無駄が実は経済を支えているのである。
これまで中小企業は大企業を手本としてきた。終身雇用も、週休二日制も、効率的な経営も、大手を見習ってきたものだ。だが日本社会は変化した。この先ただ大手を追随することは自殺行為である。大手で不要とされる無駄をいかにビジネスに取り入れていくか。ここが中小にとっての最重要ポイントとなる。
まずターゲットを明確にすること。無駄の評価は人によって180度変わる。人は自分にとって快適な無駄には快く対価を支払う。楽しい無駄であれば同じ給料でもそこで働きたいと思う。だが同じ無駄が別の人にとっては不快であり不満の原因となる。誰にとっての快適な無駄なのかを決める必要があるのだ。
そんなニッチなニーズで会社が成り立つのか。社員が食べていけるのかと不安になるかもしれない。だがそんな心配は不要である。冷静に考えれば人が生きていくために不可欠なものは知れている。死なないことが目的ならそんなにお金はかからないのである。だが人が生きていくためには楽しみも必要だ。
無駄のない人生は味気ない人生である。旅行に行くことも、おしゃれをすることも、美味しい食事も、楽しい遊園地も、無駄でしかない。逆に考えるなら無駄があるから人生は楽しい。無駄を提供することは人を喜ばせること。これぞ商いの原点と言える。無駄を売るビジネスの可能性は無限大なのである。
尚、同日配信のメールマガジンでは、コラムと同じテーマで、より安田の人柄がにじみ出たエッセイ「ところで話は変わりますが…」と、
ミニコラム「本日の境目」を配信しています。安田佳生メールマガジンは、以下よりご登録ください。全て無料でご覧いただけます。
※今すぐ続きを読みたい方は、メールアドレスとコラムタイトルをお送りください。
宛先:info●brand-farmers.jp (●を@にご変更ください。)