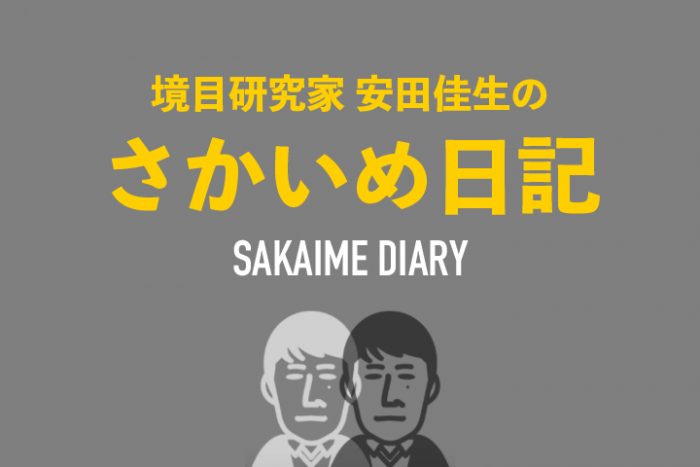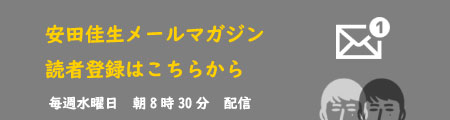雇用という壁はとてつもなく高い。壁のこちら側には雇う人たち。あちら側には雇われる人たち。永久に混じり合うことのない二つの民族が同じ国の中で暮らしている。それが会社という歪な組織なのである。どう説得しても雇われている側の人たちに経営意識は芽生えない。これは仕方のないことである。
そもそもの成り立ちが違うのだ。たとえば国境を隔てて対立する二つの国があったとしよう。どちらにも言い分があり、それぞれの歴史がある。相入れない関係だが分かりあうことは不可能ではない。相手の立場を慮ることで理解は進むだろう。だがそれは相手国と同じ感情や思考になるということではない。
経営者にも雇われる人の気持ちは理解できるし、社員にも雇う人の気持ちは理解できる。だが同じ気持ち、同じ思考、同じ価値観にはならない。社員はあくまでも報酬のために役務を提供している立場。この前提は変えようがない。会社の利益より自分の利益を優先するのは当然のことではないか。
一方、経営者はまったく事情が異なる。会社の中で唯一、身銭を切っている立場なのだ。会社が儲からなくても給料をもらえる人たちと、会社が儲からなくても給料を払わなくてはならない人たち。ここには絶対に超えられない壁が存在する。壁の向こう側は言語も文化も歴史も価値観も違う国なのである。
社員とは分かり合えない、などと言うつもりはない。立場が違うという事実をしっかり受け止めようと言いたいのだ。給料が出なければそこにいる理由がない人たちと、身銭を切り続けてもそこにいなくてはならない人たち。二つの異なる民族を同じ価値基準で判断しようとするから問題が起こるのである。
人が集まらないのは人不足だからではない。雇われる人たちが魅力を感じない仕事だから集まらないのだ。育てた人材が辞めていくのは恩義を感じていないからではない。そこに居続ける理由を感じないから辞めるのだ。みんなの会社ではない。雇っている人たちの会社なのだ。それを忘れてはならない。
儲からなくても給料をもらい続ける人たちと、儲からなくても給料を払い続ける人たち。儲かれば働かなくても報酬を受け取れる人たちと、儲かっても働かないと報酬がもらえない人たち。リスクを報酬に変える人たちと、ワークを報酬に変える人たち。どこをどう考えても同じ価値観になりようがない。
尚、同日配信のメールマガジンでは、コラムと同じテーマで、より安田の人柄がにじみ出たエッセイ「ところで話は変わりますが…」と、
ミニコラム「本日の境目」を配信しています。安田佳生メールマガジンは、以下よりご登録ください。全て無料でご覧いただけます。
※今すぐ続きを読みたい方は、メールアドレスとコラムタイトルをお送りください。
宛先:info●brand-farmers.jp (●を@にご変更ください。)