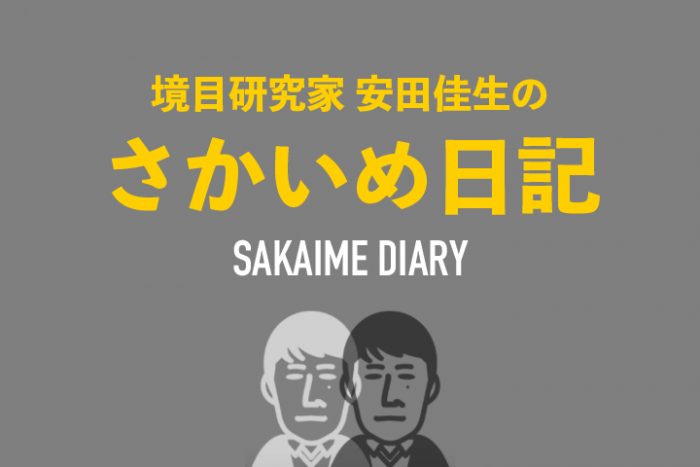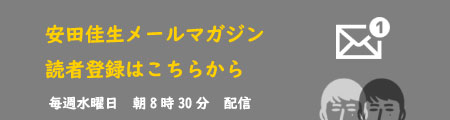仕組みで売れる。手間やコストを割かなくても注文が入ってくる。これは一見、良い事づくめであるように見える。確かに仕事は楽だし販促費もかからない。だがそれが命取りになってしまうケースもある。たとえば誰かが作った仕組みに乗っかっているパターン。これはかなり危ないと言わざるを得ない。
安定して仕事をくれる発注元がある。これはもちろん悪いことではない。だがそこに依存していると生殺与奪権を握られてしまう。悪い条件でも飲まざるを得なくなったり、相手の状況に巻き込まれて連鎖倒産することもあり得る。では自分で作った仕組みなら安泰なのか。いや、そうとも限らないのである。
たとえばYouTubeを介しての仕事依頼やGoogle検索を介しての問い合わせ。その仕組みを作り上げたのは自分自身であるが、このようなプラットフォームは永久に続く保証がない。ではポスティングや人を介した販売ネットワークはどうだろう。仕組み自体がなくなることはないが売れ続ける保証はない。
だったら何をやってもダメではないかと言われそうだが、おっしゃる通り何をやってもダメなのである。どんなに素晴らしい仕組みも永遠には続かない。それどころか賞味期限がどんどん短くなっている。下請け100%はいつ崩壊してもおかしくない状態だし、どんな仕組みもずっと機能し続ける保証はない。
これは販売だけの話ではない。商品そのものにも賞味期限があることを忘れてはいけない。どんな仕組みも、どんな商品も、必ずどこかで機能しなくなり売れなくなる。機能する期間はどんどん短くなっている。この大前提を決して忘れてはならない。にも関わらず多くの社長がこの前提を無視している。
今の商品が売れなくなった時の仕込み。それが商品開発。今の方法で売れなくなった時の仕込み。それが販売戦略。この二つに一体どれくらいの投資をしているだろうか。売れなくなってから慌てても手遅れなのである。新商品も新たな販売戦略もそう簡単には機能しない。時間もお金もかかる投資なのだ。
うちの業界では難しい。我々の環境は変えられない。このような言葉が出る経営者は単にやってこなかったのである。当然起こり得る機能の限界に対して何も手を打たなかった。ただそれだけ。少なくとも利益の20%くらい、未来への仕込みとして毎年投資し続ける。それが生き残る会社の最低条件である。
尚、同日配信のメールマガジンでは、コラムと同じテーマで、より安田の人柄がにじみ出たエッセイ「ところで話は変わりますが…」と、
ミニコラム「本日の境目」を配信しています。安田佳生メールマガジンは、以下よりご登録ください。全て無料でご覧いただけます。
※今すぐ続きを読みたい方は、メールアドレスとコラムタイトルをお送りください。
宛先:info●brand-farmers.jp (●を@にご変更ください。)