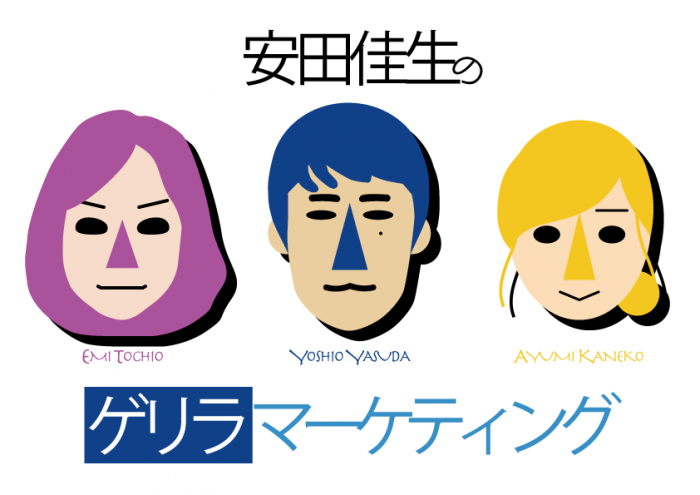大変なんで、墓じまいといって、墓をしまって都会のちっちゃいとこに持っていくるとか、最近はバーチャルなお墓とか「バーチャル位牌」みたいなやつがありまして、テレビみたいなモニターがあって、名前入れると映像で位牌が出てくるわけですね。

たとえばお寺だったら、お寺継ぐ人が「そんなのやりたくない」って言うかもしれないじゃないですか。そもそも供養って、たぶん、あと2・3代たっちゃったら誰を拝んでるのかすらわかんなくなっちゃって、誰が拝んでるか・誰を拝んでるかに相関関係ほとんどなくなるじゃないですか。

「私が拝みます」って引き受けた人の次の世代の、さらにその次の世代ぐらいになってきたら、引き受けた覚えもないし、そもそも、たくさんの人をいっぺんに供養するんで、誰がそこにいるのかすらわかんないし。

それをもって供養って言うんだろうか?みたいな。つまり、供養の放棄というか、「もう供養しない」ってことだと思うんですけど。だけど、お盆に……まあ、僕なんかはあんまり信心深くないんで、お盆とか、ちっともお墓参りとかしないんですが。そもそも、うちはお墓ないんですけどね。両親の遺言で「墓つくるな」って言われたんで。だけど、ちょっと後ろめたさがあるじゃないですか、普通は。だから、その後ろめたさをなくしてあげるっていうビジネスなのかなって思うんですよ。

でも、たとえば供養するとか墓つくるっていうのが、いま、当たり前じゃないですか。でも、これもたぶん、どっかで誰かが始めたわけで、たとえば「お墓を建てる」っていう常識がいま現在の人間にゼロだとしたらね、そうしたら、「墓を建てよう」っていうのはニュービジネスになるわけですよね。

そこにあるからやって当たり前、みたいになっちゃうんですけど、ないものもいっぱいあって。だから、誰かが始めて、なんとなく続いてるだけかもしれないですよね。バレンタインデーのチョコも、チョコレート屋さんがチョコを売るために考えたって言われてますが、永代供養は何なんだろうかっていうふうに考えた次第でありまして。

そうですね。

あ、残る人がね。どうなんでしょうね、いまの奥さんに捨てられ、「子どもとも会わないでくれ」って言われて、ひとりになって野垂れ死ぬっていうのも、ま、それはそれでいいかなって感じですかね。

どちらかというと、僕はいっぱい書いて残したりするほうなんですけど、インターネットっていう永久に残るメディアの中に、自分の言葉とか自分が考えたことが残っていくっていうことのほうが大事ですね。

ということでグダグダしましたが、本日は以上です。ありがとうございました。
*本ぺージは、2019年10月23日、ポッドキャスト「安田佳生のゲリラマーケティング」において配信された内容です。音声はこちらからhttp://yasudayoshio.com/podcast/#/top
ポッドキャスト番組「安田佳生のゲリラマーケティング」は毎週水曜日配信中。