カテゴリー: 安田佳生コラム
-
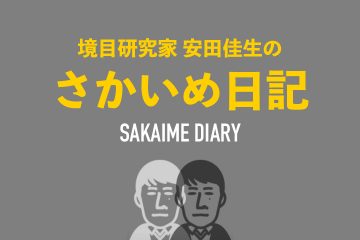
2025年6月11日
過去と未来は繋がっていない
何を馬鹿なことをと言われそうだがこれは事実である。過去と未来は1ミリたりとも繋がっていない。ある人にそう言われて初めて気がついた。前回0点だった過去は次回のテストの点数には一切関わりがない。繋げているのは自分自身だ。前回…
- 安田佳生コラム
-
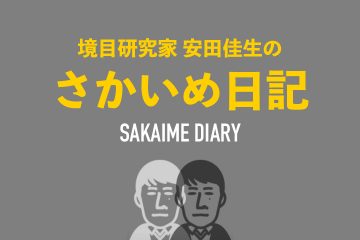
2025年6月4日
シン社長の時代
とことん拡大してスケールメリットで収益率を高めていくか。とことん縮小してめちゃくちゃ儲かるスモールビジネスをやるか。どちらかに振り切らないと一人当たりの収益が最大化されない。収益を最大化させられない会社は社員の給料を増や…
- 安田佳生コラム
-
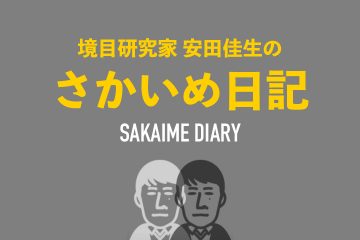
2025年5月28日
恩返しの原理
子育てに見返りを求める親はいない。だけど子は親に恩返ししようとする。それが人間という生き物。自然界の動物は育ててくれた親に恩など返さない。人間の世界には血が繋がっていない親子もいて、見返りを求めず子育てをする。そうやって…
- 安田佳生コラム
-
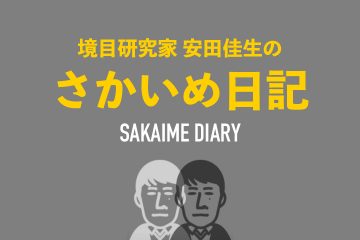
2025年5月21日
次の一手
人を増やすのか増やさないのか。顧客を絞り込むのか絞り込まないのか。価格を上げるのか上げないのか。この三つの質問にどう答えるかで次の一手が決まる。人をどんどん増やし、顧客を絞り込まず、価格をできるだけ据え置き、業界トップレ…
- 安田佳生コラム
-
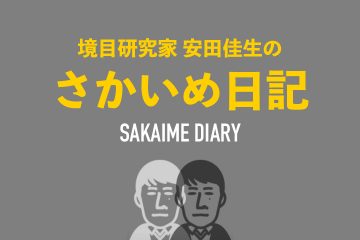
2025年5月14日
稼げない肩書き
経営コンサルタントの倒産が相次いでいるそうだ。2024年度だけで151件。この統計に入らない小さな事業者の廃業を入れると何十倍という数になるだろう。そもそも経営コンサルタントと名乗る人の平均年収は100万円前後と言われて…
- 安田佳生コラム
-
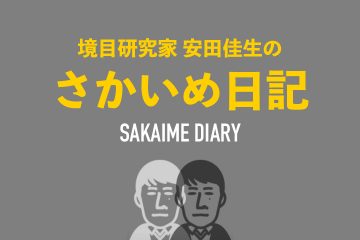
2025年5月7日
真なる知的労働とは
誰でも一度くらいは触ったことがあるルービックキューブ。目の前にあれば子供も大人もチャレンジしたくなる。よく出来たパズルだ。バラバラになったキューブを揃えることができれば一目置かれる存在になれる。だがこのパズルを自分の頭で…
- 安田佳生コラム
-
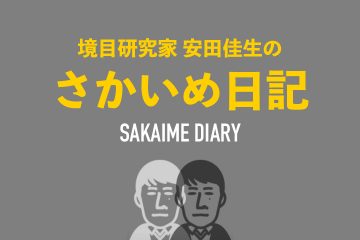
2025年4月30日
二極化する組織づくり
安く仕入れて高く売る。人に関しても商品に関してもこの発想で利益を増やすことはもう無理である。それが可能なのは業界トップの規模を持つ会社だけ。拡大し続ける覚悟がないのであればビジネスモデルを見直すしかない。スケールメリット…
- 安田佳生コラム
-
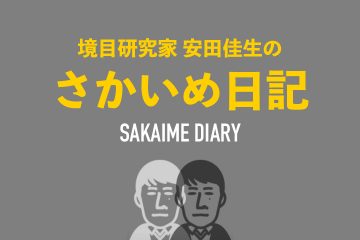
2025年4月23日
快楽のゼネレーションギャップ
大きな会社に入ってガンガン出世したい。立派な家を建てて家庭的な妻を迎えたい。仕事を最優先にするのは家族の幸せのため。皆がこれを常識として受け入れている時代があった。今はほぼ真逆である。仕事はしっかりやるがプライベートも充…
- 安田佳生コラム
-
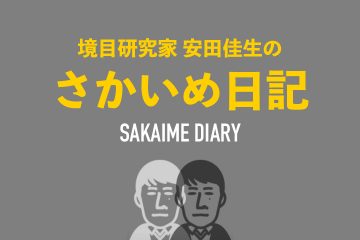
2025年4月16日
平均年収1000万円を実現せよ
日本人の平均年収はたった420万円。いくらなんでも低過ぎないだろうか。円安になるのも、物価が高いのも、生活が苦しいのも、すべて年収が低いから。一人当たりの税負担や社会保障費が高いのも平均年収が低いから。すべての原因はそこ…
- 安田佳生コラム
-
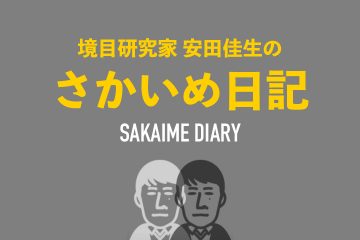
2025年4月9日
組織図を見れば未来が見える
人不足はもう待ったなしである。何度も申し上げているように、この先、中小企業から人が消える。より大きな会社(同じ職種で報酬が高い会社)へと人がどんどん移動していく。この変化に対応するため中小企業はどちらかに舵を切らねばなら…
- 安田佳生コラム
-
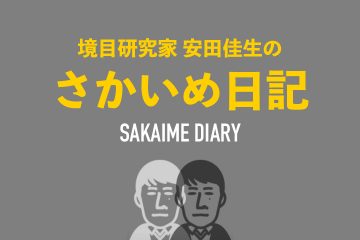
2025年4月2日
75歳まで働く時代
定年再雇用者の賃金がどんどん引き上げられている。正確に言えば定年前の基準に戻されている。だがその配分は平等ではない。スキルが高い人にはより多くの報酬が支払われ、その分スキルが低い人の報酬が減らされる。言うまでもないが、こ…
- 安田佳生コラム
-
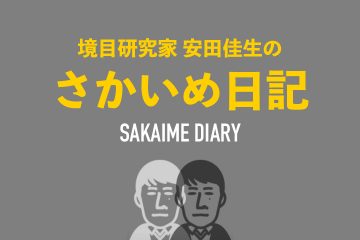
2025年3月26日
上にAI下にロボット
国も会社も人不足。この先数十年、いや、もしかしたら永遠に、少子化が解消される未来は来ないかもしれない。若者の婚姻数がどんどん増え結婚した夫婦がみんな2人以上の子どもを産む。そんな未来を想像できる人がいるだろうか。もう人口…
- 安田佳生コラム

